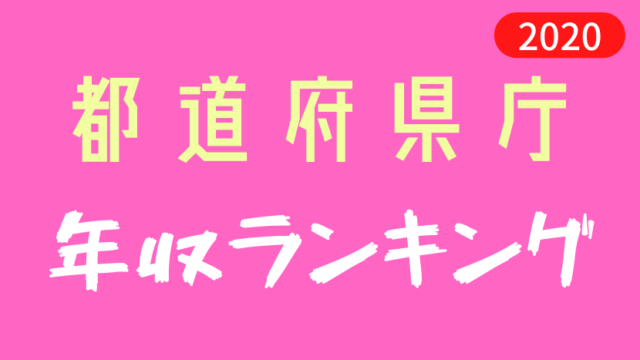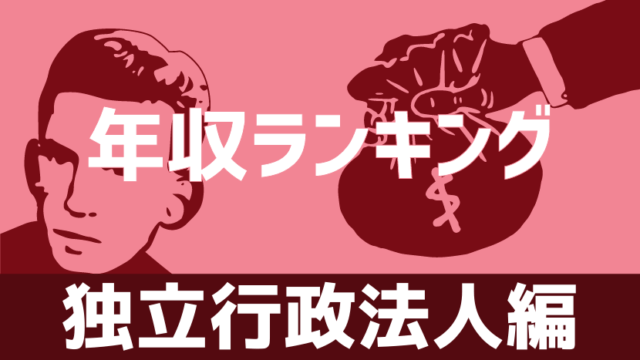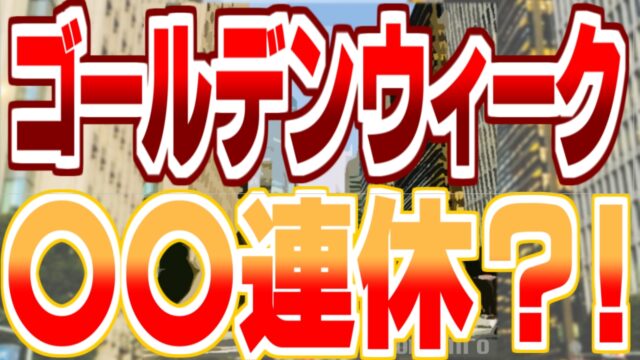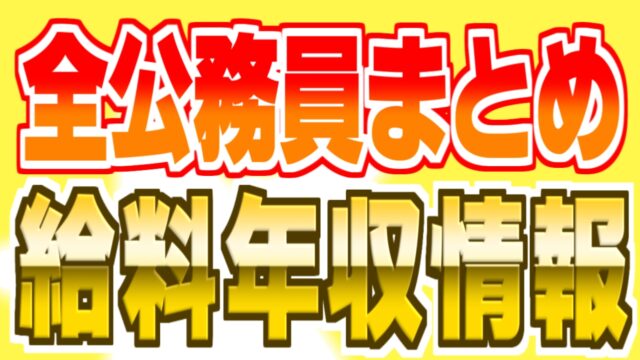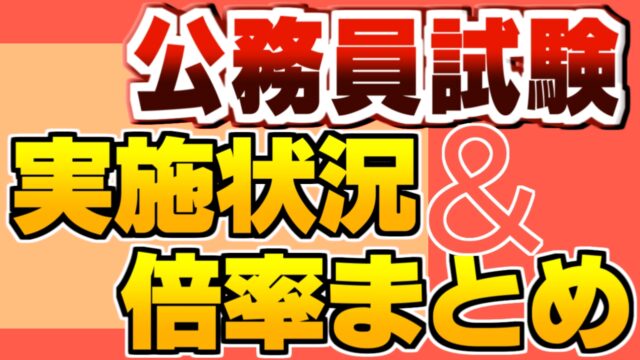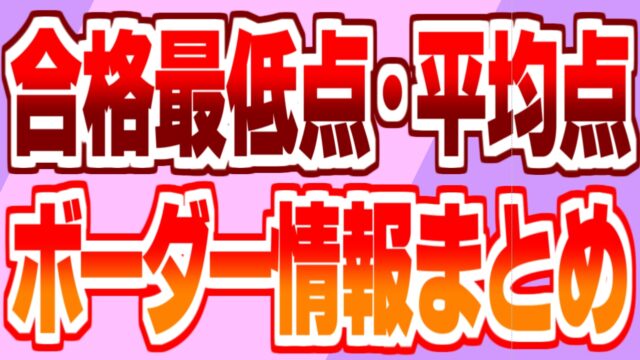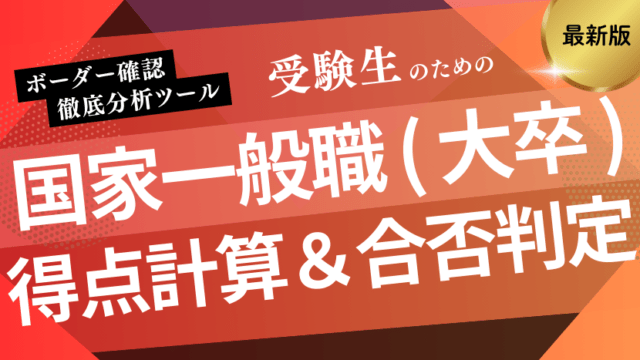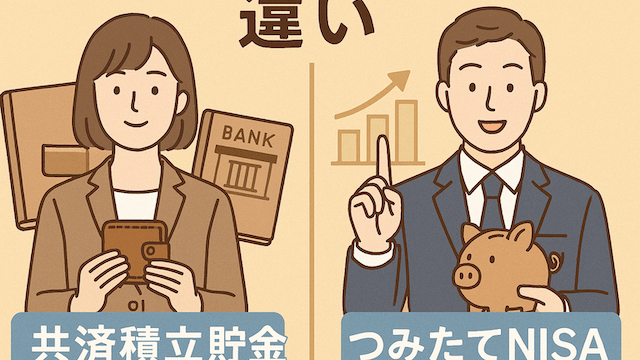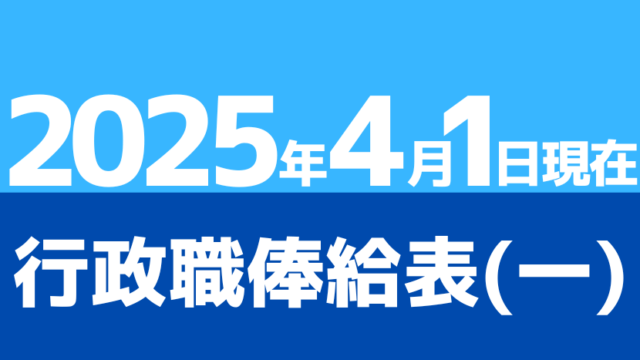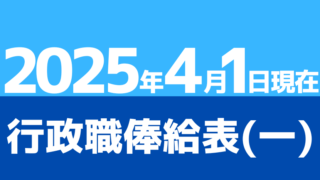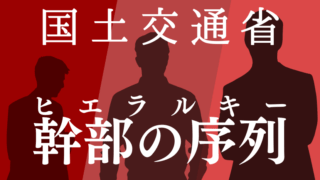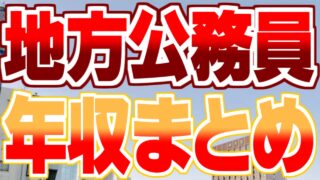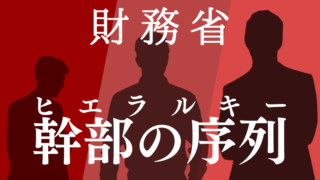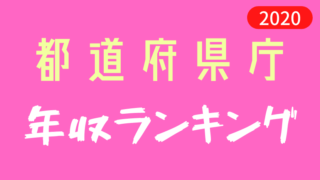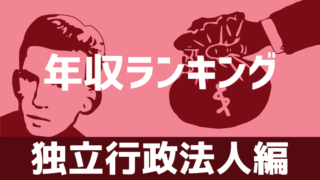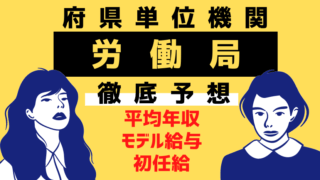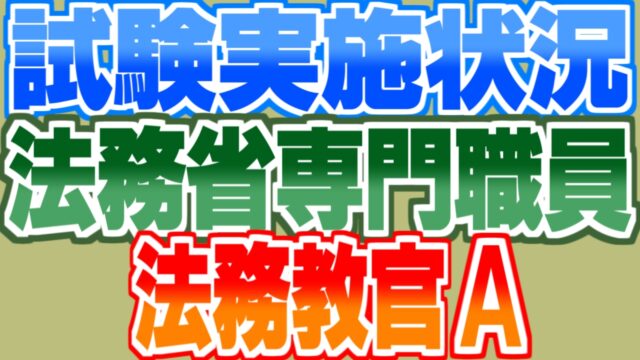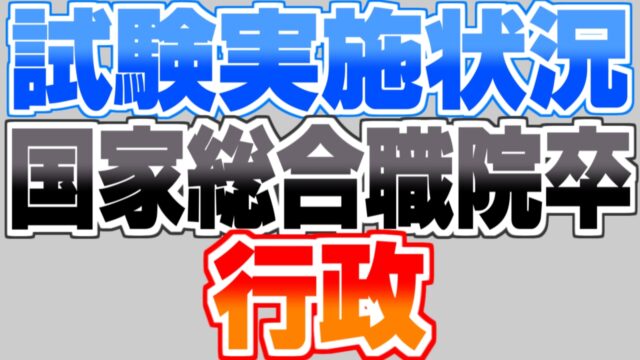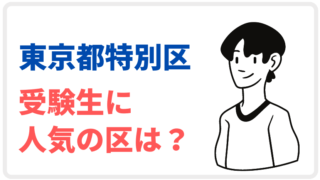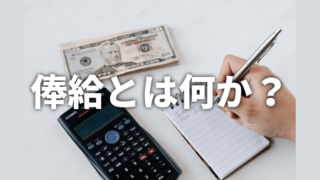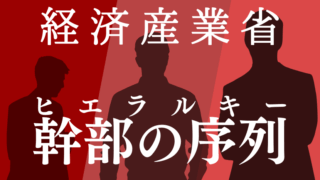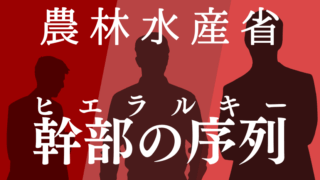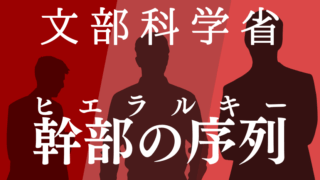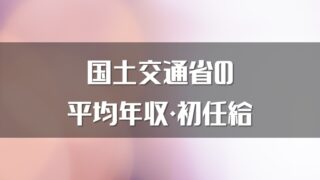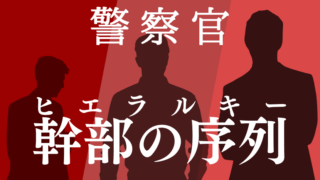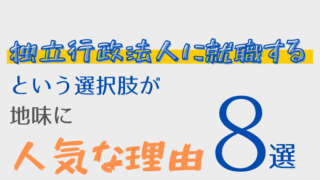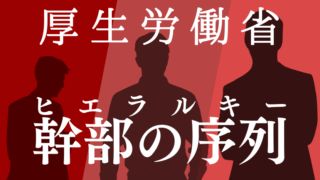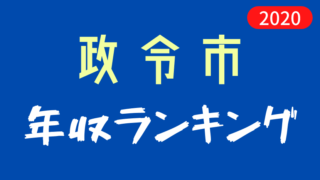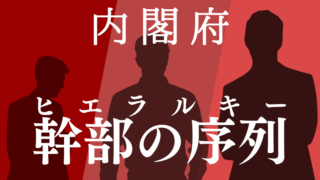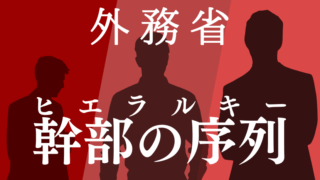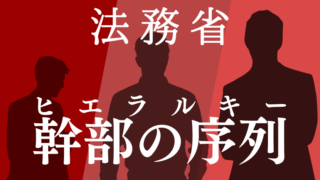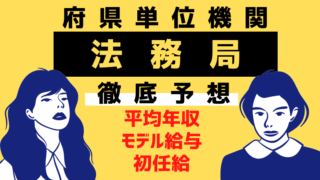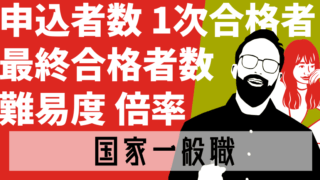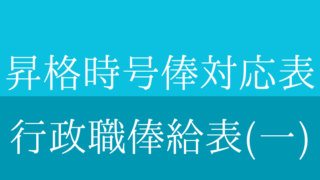目次
皆さんは、公務員の給与がどのように決まっているかご存じでしょうか。
公務員の給与は、人事院勧告という仕組みによって毎年見直しが行われています。
この記事では人事院勧告の基本から、公務員の給与決定の仕組みや人事院勧告のスケジュール、公務員として知っておくべきポイントまでをわかりやすく解説します。
公務員給与決定の仕組みと目的
 人事院勧告とは、人事院が国会および内閣に対して行う、国家公務員の給与やその他の勤務条件の改善に関する勧告のことです。
人事院勧告とは、人事院が国会および内閣に対して行う、国家公務員の給与やその他の勤務条件の改善に関する勧告のことです。
簡単に言えば、民間企業で働く人と国家公務員の給与水準をできるだけ近づけ、公務員にも適正な給与水準を確保するための制度です。
公務員の給与決定は「給与法定主義」といって法律に基づき行われますが、人事院勧告はその給与を社会一般の情勢に適応させるために設けられた仕組みです。
国家公務員は「労働基本権」(労働組合との交渉権やストライキ権など)が制約されています。
その代わりに、公務員にも民間と同様に適正な給与を受け取る権利を保障するため、人事院という独立機関が毎年給与などの見直しを勧告する役割を担っています。
要するに、人事院勧告は公務員自身が賃上げ交渉できない代わりに、人事院が第三者の立場で給与改善を提案する制度なのです。
人事院勧告の目的は、公務員の待遇(処遇)を適切な水準に保つことにあります。
特に国家公務員の場合、景気や民間給与の動向に応じて給与水準を見直すことで、公務員の給与が世間とかけ離れないようにする役割を果たしています。
このように、公務員給与決定の仕組みの中で人事院勧告は重要な位置づけを持っており、毎年必ず実施されています(法律上「毎年少なくとも1回」報告・勧告することが義務づけられています)。
人事院勧告の対象範囲(給与・手当・勤務条件)
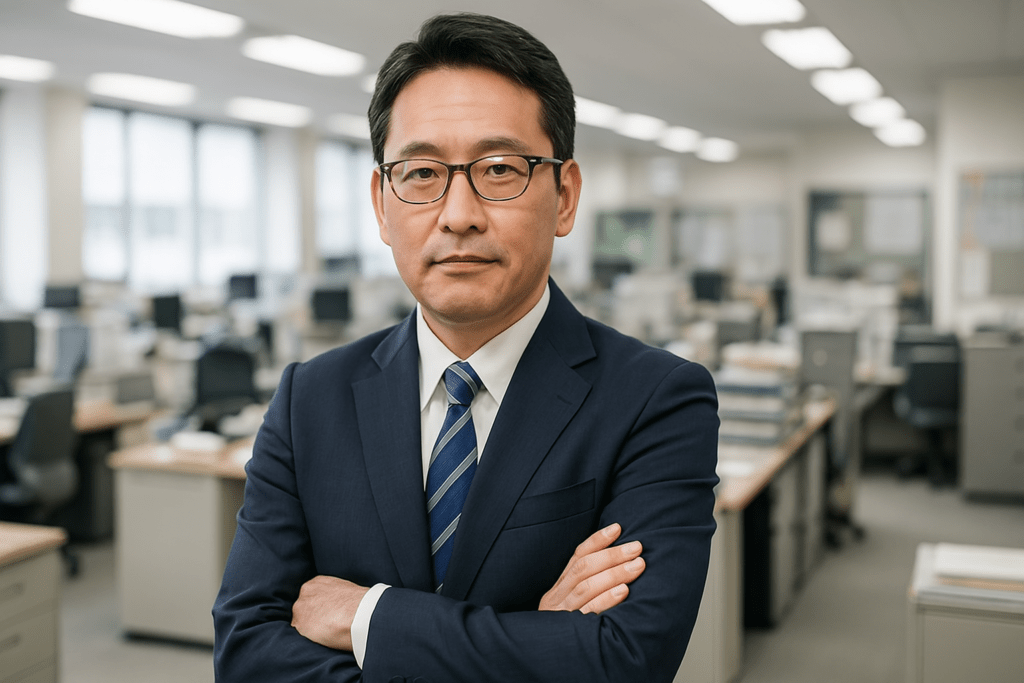 人事院勧告の対象となるのは、国家公務員のうち一般職で「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員です。
人事院勧告の対象となるのは、国家公務員のうち一般職で「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員です。
具体的には、各府省で勤務する行政職や専門職など約28万5千人の国家公務員が該当します。
これは公務員全体(国家公務員約59万人+地方公務員約275万人)のうちおよそ8%程度にあたります。
対象となる職種には、一般行政職員のほか外交官、税務職員、刑務官、海上保安官、国立病院の医師・看護師など幅広い職種が含まれます。
一方、国会議員や大臣などの特別職、裁判官、自衛官などは給与法の対象外ですが、これらの給与も慣例的に人事院勧告の内容に準じて調整されることが多いです。
また、地方公務員については各地方公共団体の人事委員会が国家公務員の人事院勧告を参考に給与勧告を行う仕組みになっており、結果的に地方公務員の給与にも影響を与えています。
人事院勧告の内容(勧告対象)には、主に給与(基本給)とボーナスに相当する特別給(期末・勤勉手当)の改定が含まれます。
加えて、必要に応じて各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、超過勤務手当〔残業代〕、寒冷地手当等)や、勤務時間・休暇制度などの勤務条件についても改善勧告が行われることがあります。
例えば、令和6年(2024年)の人事院勧告では基本給引き上げに加え、通勤手当の上限額引き上げ(新幹線通勤の要件緩和)など制度の見直しに関する勧告も行われました。
このように人事院勧告は、公務員の給与水準だけでなく広く処遇全般(給与とその周辺の待遇条件)の改善を対象としています。
なぜ人事院勧告があるのか
 人事院勧告制度が存在する背景には、前述のとおり国家公務員法の規定があります。国家公務員法第28条の「情勢適応の原則」では、国家公務員の給与や勤務条件について、社会一般の情勢に適応するよう随時変更できる旨が定められ、その変更に際して「人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない」と規定されています 。
人事院勧告制度が存在する背景には、前述のとおり国家公務員法の規定があります。国家公務員法第28条の「情勢適応の原則」では、国家公務員の給与や勤務条件について、社会一般の情勢に適応するよう随時変更できる旨が定められ、その変更に際して「人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない」と規定されています 。
また同条項で、人事院は毎年少なくとも1回は俸給表(給与表)が適切かどうかを国会と内閣に報告する義務があり、給与水準に大きな乖離(5%以上の差)が生じた場合には併せて勧告を行わなければならないとも定めています。
この法律の趣旨は、先にも触れたように労働基本権制約の代償措置として公務員給与の公平を確保することにあります。
一般の企業であれば労使交渉によって賃金が決まりますが、公務員は法律でストライキなどが禁じられているため、直接交渉で給与を決めることができません。
しかし公務員も生活者として適正な給与が必要であることから、人事院が間接的に労使交渉の役割を果たし、民間の状況を踏まえて給与改定を提案する仕組みが用意されたのです。
人事院勧告制度はこのような法律上の裏付けを持ち、長年にわたり運用されています。
さらに、公務員給与は最終的に国会の議決による法律(給与法改正)で決定されるため、人事院勧告はあくまで「勧告」であって法的拘束力はありません。
しかし、政府はこの制度を基本的に尊重する姿勢をとっており、勧告どおりに給与改定が実施されるのが原則となっています(財政状況が非常に厳しい場合などには勧告の実施が見送られた例もありますが、そのようなケースは例外的です)。
こうした点からも、人事院勧告は公務員の給与決定において制度上重要な役割を担っていることがわかります。
民間給与との比較方法(民間給与実態調査の仕組み)
 人事院勧告の特徴の一つが、民間の給与水準との比較に基づいていることです。
人事院勧告の特徴の一つが、民間の給与水準との比較に基づいていることです。
毎年、人事院は全国の企業を対象に「民間給与実態調査」という大規模な調査を行い、民間従業員の給与データを収集します。
この調査では、企業規模50人以上・事業所規模50人以上の民間事業所から約11,000事業所を抽出し、約46万人分の給与情報を集めています。
一方で国家公務員側も同様に、全府省の職員約28万人の4月分の給与データ(職種・役職段階・学歴・年齢などの属性別)を集計する「国家公務員給与実態調査」を行います。
この官民それぞれの給与データを、「ラスパイレス方式」と呼ばれる手法で比較するのが人事院勧告の肝となります。
ラスパイレス方式とは、民間と公務員の仕事内容・役職段階・学歴・年齢などが同程度のグループ同士で給与を比較し、その差異を算出する方法です。
個々の職員ごとではなくグループ単位で精密に比較することで、公務員と民間の給与をできるだけ公平に比べることができます。
この比較により、例えば「民間の方が平均して月額○○円高い」という官民較差が判明すれば、その較差を解消するように公務員給与の引き上げ(または引き下げ)を勧告します。
実際、人事院は「毎年、公務と民間の給与を精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に給与勧告を行っている」と説明しています。
また、給与(月例給)だけでなくボーナス(期末・勤勉手当)についても民間の支給実績を調査し、官民の年間支給月数を比較しています。
直近1年間(前年8月~当年7月)の民間企業における賞与支給状況を調べ、民間の平均年間賞与(月数換算)を算出した上で、公務員の年間ボーナス支給月数をそれに見合った水準に調整するよう勧告します。
例えば民間の平均が年間4.5ヶ月分で、公務員が現行4.4ヶ月分であれば、0.1ヶ月分引き上げるといった具合です。
このように月例給とボーナスの双方で民間準拠(民間の水準に合わせる)の方針が徹底されており、勧告内容は民間給与の動向を色濃く反映したものとなっています。
人事院勧告の年間スケジュール・流れ
 人事院勧告は毎年ほぼ定型的なスケジュールで実施されます。年間の大まかな流れ(スケジュール)は次のとおりです。
人事院勧告は毎年ほぼ定型的なスケジュールで実施されます。年間の大まかな流れ(スケジュール)は次のとおりです。
春(4月)
人事院が民間給与実態調査と国家公務員給与実態調査を実施します。
民間企業と公務員それぞれの4月分の給与データを収集し、職種や年齢など条件別に集計します。
この調査では、各府省や企業への訪問や資料提供を受けて詳細なデータを集めます。
初夏~夏
調査結果をもとに、人事院の中で官民給与の詳細な比較分析が行われます。
同時に各方面からの意見聴取も実施され、職員団体(労働組合に相当する職員団体)や有識者、各府省から給与に関する要望や意見を受け付けます。
これらの情報を踏まえ、人事院内で勧告内容の検討が進められます。
夏(8月)
人事院は毎年8月上旬に勧告内容を取りまとめ、記者会見を開いて「人事院勧告」を公表します。例年、勧告日は8月初旬となっており、令和5年(2023年)は8月7日、令和6年(2024年)は8月8日に勧告が発表されました。
勧告の内容(改定率や月数など)やポイントは人事院から国会・内閣に公式に報告され、同時に公開されます。
勧告後(秋)
人事院勧告を受けて、政府はその扱いを検討します。
内閣は総理大臣や関係閣僚による「給与関係閣僚会議」を開催し、勧告に基づいて公務員給与をどう改定するか方針を協議します。
通常、政府は「人事院勧告制度を尊重する」との基本方針のもと、勧告どおり実施する方向で閣議決定を行います。
秋~初冬
政府方針が決まると、内閣は人事院勧告の内容を反映した給与法改正案を作成し、国会に提出します。
国会(主に秋の臨時国会)でこの給与法改正案が審議され、与野党の承認を経て可決・成立します。
ここまでくれば法的に給与改定が決定したことになります。
改定の実施
可決された給与改定内容は法律に基づき実施されます。
改正給与法の施行日は多くの場合その年の4月1日まで遡及して適用され、公務員には4月に遡った差額分も含めて支給が行われます(実際の支給は法成立後の時期に遡及分をまとめて支給)。
例えば令和5年人事院勧告では8月勧告・秋成立の給与法改正により、改定後の給与が同年4月に遡って適用されました。
このように、公務員は年末までに勧告に基づく給与調整が反映された給与・賞与を受け取ることになります。
以上が人事院勧告から実際の給与改定までの一連の流れです。
まとめると、毎年春に調査 → 夏に勧告 → 秋に法改正 → 年内に実施というサイクルで、公務員の給与は定期的に見直されています。
勧告後の給与改定
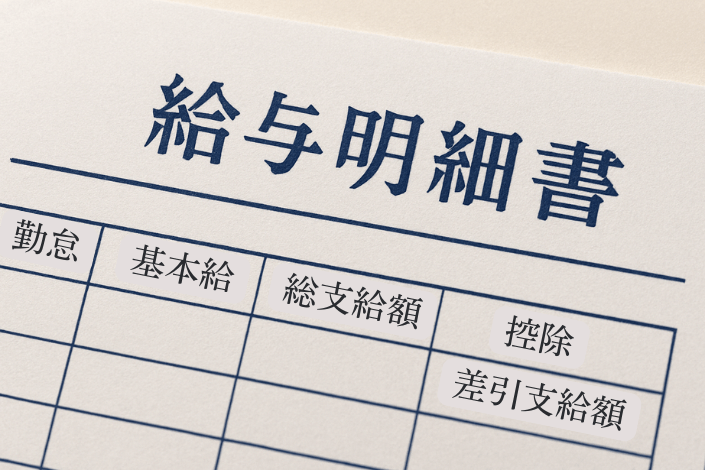 人事院勧告は先述のように法的拘束力はありませんが、政府・国会がこれを尊重して実施するのが通例です。
人事院勧告は先述のように法的拘束力はありませんが、政府・国会がこれを尊重して実施するのが通例です。
勧告どおりに給与法が改正されれば、公務員の給与・手当は勧告内容に沿って改定されます。
では、具体的に勧告がどのように給与に反映されるのか、もう少し見てみましょう。
基本給の改定については、勧告で示された官民較差にもとづき、各俸給表(行政職や専門職など職種別に定められた給与表)の水準を一律に引き上げる形で実施されます。
例えば「月例給を平均3,869円(0.96%)引き上げ」という勧告の場合、各等級・号俸の金額をそれぞれ所定の額ずつ底上げする改定が行われます。
若年層ほど額面引き上げ額を大きくするといった配分調整が行われるケースもありますが、基本的には全職員が勧告相当の増額恩恵を受けます。
ボーナス(期末・勤勉手当)の改定については、年○ヶ月分と定められている支給月数を増減させる形で実施されます。
例えば「ボーナス0.10ヶ月引き上げ」という勧告なら、期末・勤勉手当の年間支給月数が現行の4.40月から4.50月に改められます。
これにより夏季・冬季のボーナス支給額が増えることになります。
なお、ボーナスの改定も法律上は給与法の改正(附則等で支給月数を変更)によって行われます。
手当等の改定については、それぞれの手当ごとの根拠法令や人事院規則の改正によって実施されます。
人事院勧告で手当の見直しが示された場合(例えば住居手当の見直しや通勤手当上限額の変更等)、政府は関係法令の改正案を準備し、国会での成立を経て施行されます。
勤務時間や休暇制度等について勧告が出た場合も同様に、関係する法律や制度の改正手続きがとられます。
このように、人事院勧告は制度上は「勧告」ですが、実際には公務員給与改定の指針そのものと言える存在です。
勧告後の政府の対応は毎年ニュースになりますが、基本的には「人事院勧告どおり実施」「◯◯円アップ・ボーナス◯ヶ月増へ」といった形で報じられ、公務員の皆さんの給与にも反映されます。
例えば令和6年(2024年)は勧告史上33年ぶりという大幅な月給約1万円超の引き上げが勧告され、政府もそれを尊重して給与改定を行うことを閣議決定しています。
このように、人事院勧告の内容は実際に公務員の給料やボーナス額に直結しているのです。
まとめ
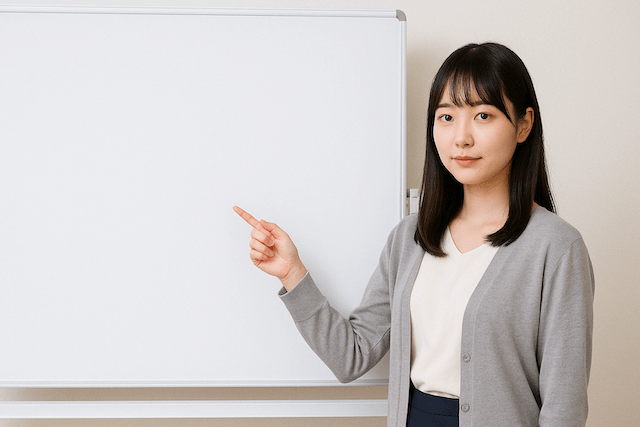 最後に、現役の若手公務員として人事院勧告について押さえておきたいポイントをまとめます。
最後に、現役の若手公務員として人事院勧告について押さえておきたいポイントをまとめます。
毎年夏の人事院勧告に注目
人事院勧告は毎年ニュース等で報じられます。
特に8月上旬に「国家公務員給与○%増」「ボーナス○ヶ月分に」といった報道が出ますので、チェックしておきましょう。
公務員給与は民間給与に連動している
勧告の背景には民間の給与動向があります。
「公務員の給料は勝手に決まる」のではなく、景気や民間企業の賃上げ状況を反映して決まる仕組みになっています。
民間の昇給が高水準なら公務員も上がり、逆に民間が低調なら公務員給与も据え置きや僅少改定になる傾向があります。
労働基本権の制約と代償措置を理解する
公務員には団体交渉による賃上げ要求の道が制限されています。
そのため労使交渉の代わりに人事院勧告制度があることを覚えておきましょう。
地方公務員や特殊な職種にも波及がある
地方公務員は各自治体の人事委員会勧告によって給与改定が行われますが、その際には国家公務員の人事院勧告結果が参考にされています。
特殊法人職員等も国家公務員給与に準拠しているケースがあります。
以上、人事院勧告の基本から流れ、ポイントまでを解説しました。
人事院勧告とは何かを理解することで、公務員の給与決定の仕組みがクリアになったのではないでしょうか。
今後も毎年の人事院勧告に注目してみてください!