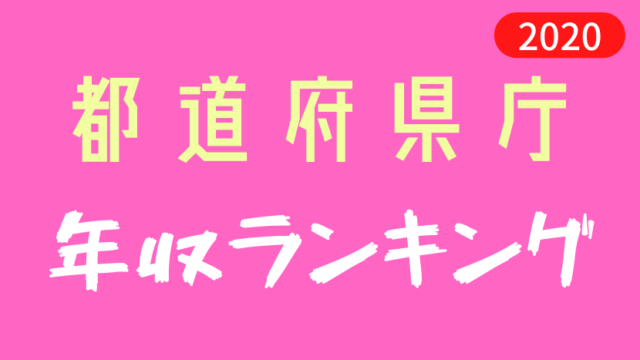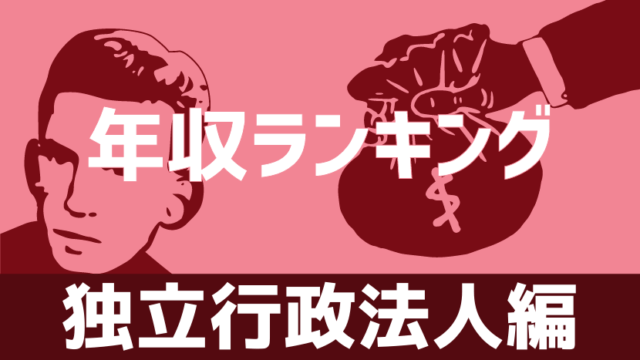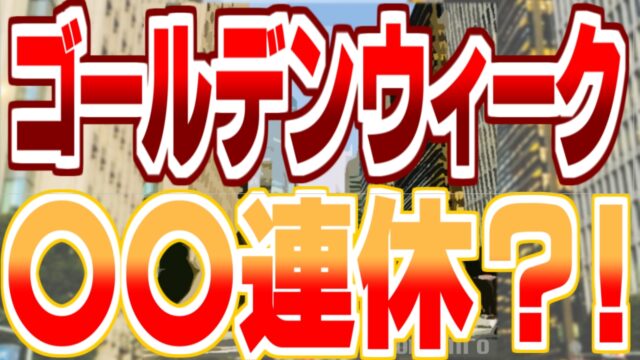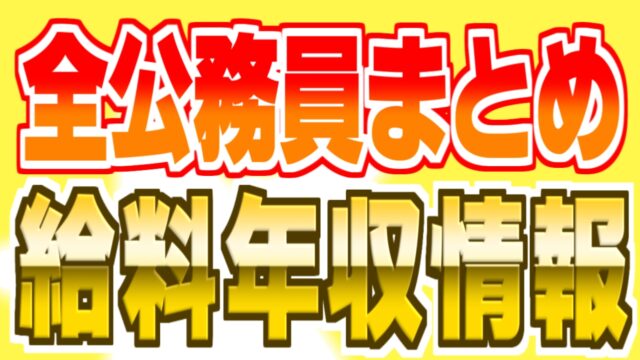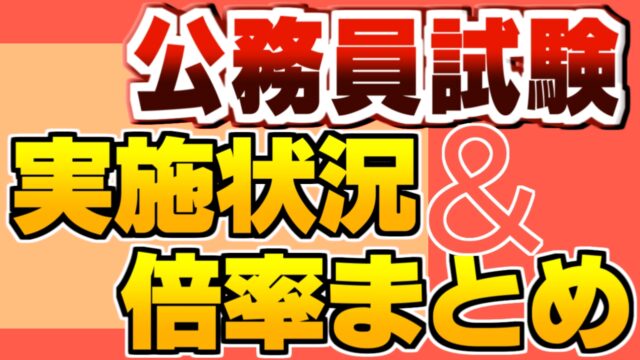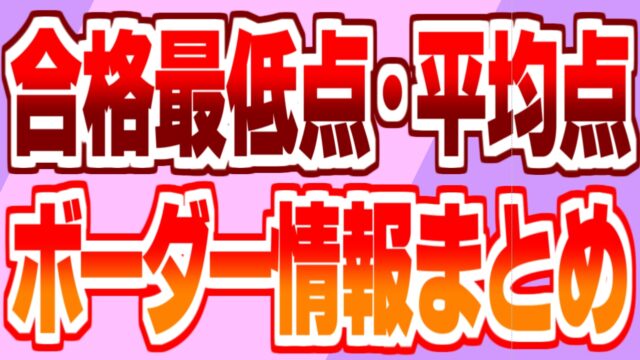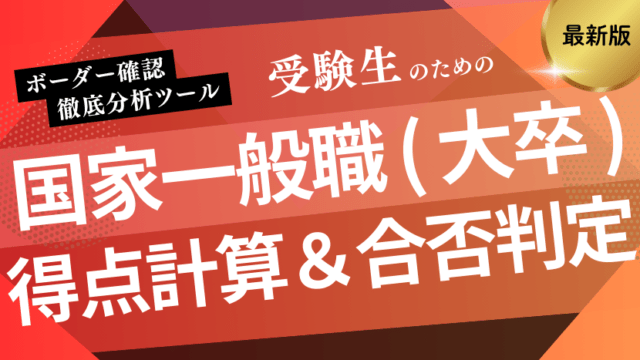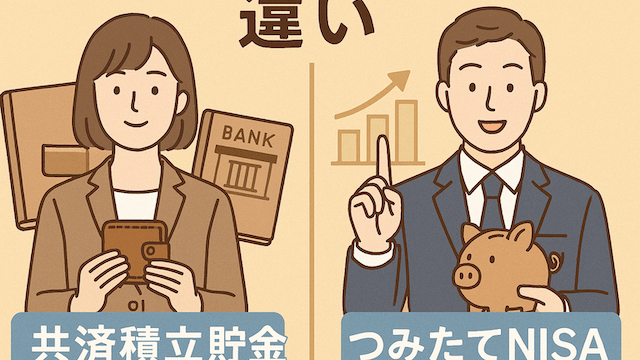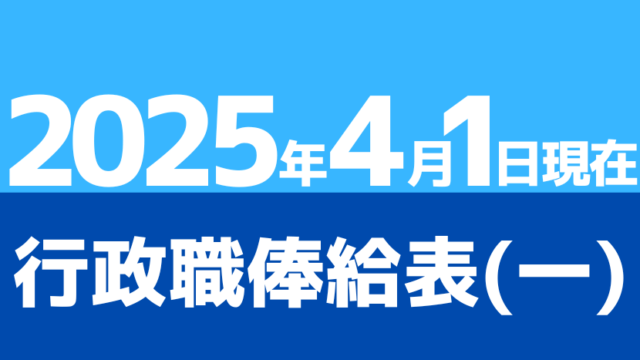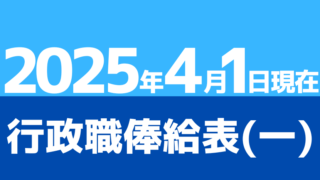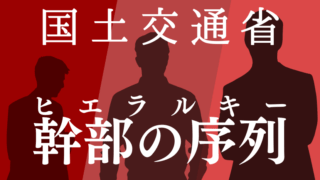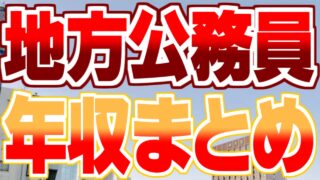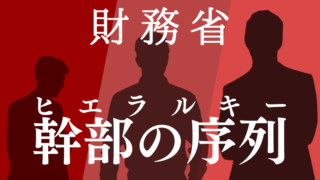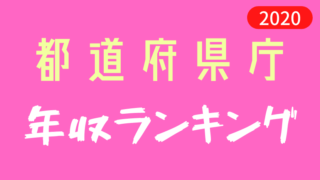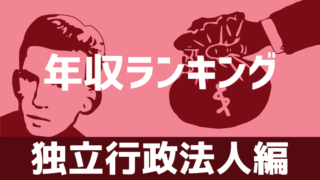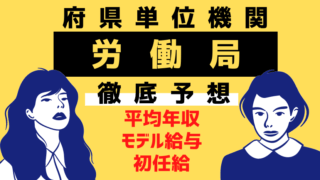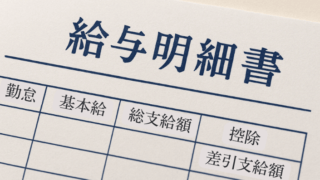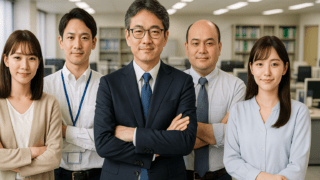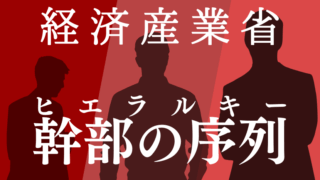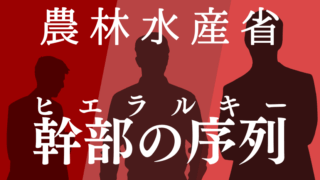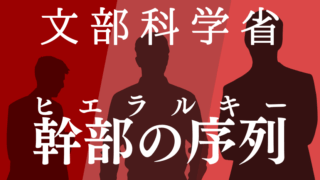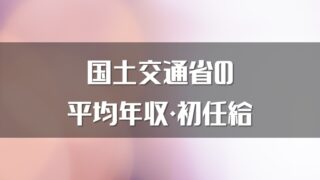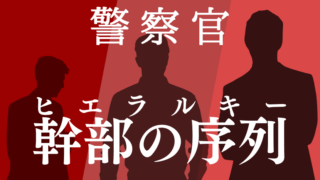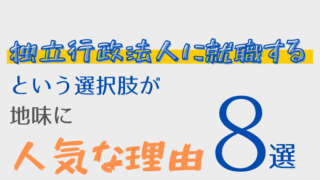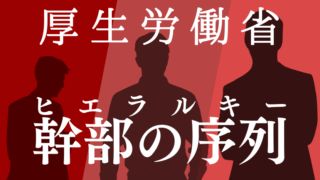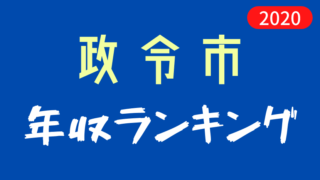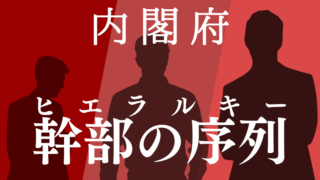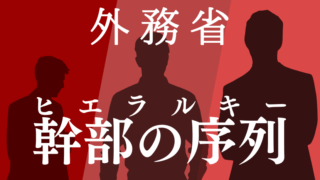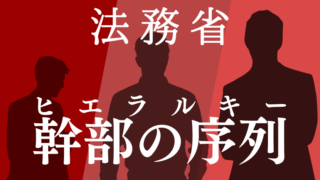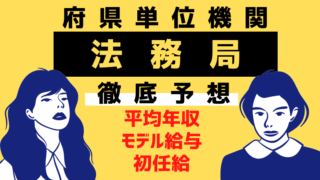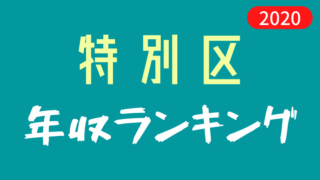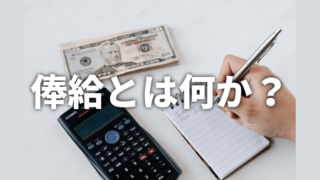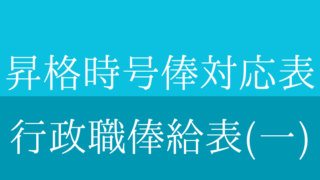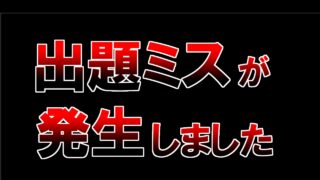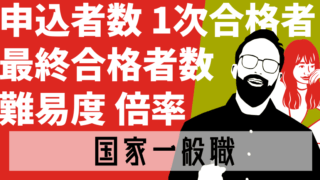目次
公務員には職場の福利厚生として共済積立貯金という有利な貯蓄制度があります。
一方で近年は新NISA(つみたてニーサ)と呼ばれる投資による資産形成制度も注目されています。
では、共済積立貯金と積立NISAの違いやそれぞれのメリット・デメリットは何でしょうか。
資産運用初心者の公務員の方にも分かりやすいように、両者を比較しながらどちらを選ぶべきかを解説します。
共済積立貯金の特徴とメリット・デメリット
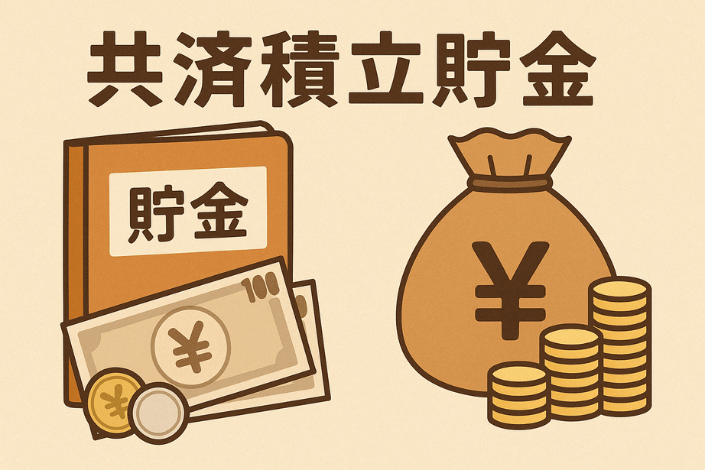 まず、公務員限定の貯蓄制度である共済積立貯金について見てみましょう。
まず、公務員限定の貯蓄制度である共済積立貯金について見てみましょう。
共済積立貯金は国家公務員共済組合や地方公務員共済組合(教職員含む)が運営する貯金制度で、組合員である公務員が毎月の給与やボーナスから一定額を天引きして積み立てる仕組みです。
組合がその資金を運用し、利益を組合員に還元することで資産形成を支援する福利厚生の一環となっています。
共済積立貯金のメリット
1.利率が銀行預金より高い
共済積立貯金は預金金利が銀行よりも高めに設定されています。
例えば、ある地方公務員共済組合の積立貯金利率は年1.52%(令和5年4月1日現在)にもなり、銀行の定期預金(金利0.40%程度)と比べて大幅に有利です。
このように高利回りで効率よく貯蓄できる点は大きな魅力です。
しかも利息は半年ごとに複利で計算されるため、実質利回りもわずかに上乗せされます。
2.元本割れの心配がほぼない
共済積立貯金は預けた元本が市場の変動で目減りするリスクがありません。
運用は国債や地方債など安全性の高い資産が中心で、元本は安定して守られています。銀行預金と同様に預けっぱなしで確実に増えていく安心感があるため、リスクを取りたくない人には心強い制度です(※預金保険による保証は後述のとおりありません)。
3.給与天引きで手軽に継続できる
毎月の給与や賞与から自動的に積立が行われるため、意識しなくても確実に貯金が続けられます。
一度手続きをすれば半強制的に天引きされるので「つい使ってしまって貯金できない」という心配がありません。
忙しい公務員でも手間をかけずにコツコツ貯められる利点があります。
4.公務員限定の優遇制度
共済積立貯金は公務員(共済組合員)しか利用できない特権的な制度です。
民間では真似できない高利率が享受できるため、公務員であることのメリットの一つと言えます。
福利厚生として用意された制度なので安心感もあり、将来に向けた財産形成に役立てることができます。
共済積立貯金のデメリット
1.資産が大きく増えにくい
安全性と引き換えに、リターンは投資商品ほど大きくありません。年1%前後の利息では大きなインフレや長期の資産形成にはやや物足りない可能性があります。
将来の老後資金などを考えると、共済貯金だけでは大きく増やすことは難しいでしょう。
2.預金保険制度の対象外
共済積立貯金は銀行預金とは異なり預金保険(ペイオフ)の対象ではありません。
万一、共済組合が経営破綻した場合、銀行預金のように元本が保証される仕組みがない点には注意が必要です。
ただし実際には国や自治体がバックにあり運用も堅実なため、破綻リスクは極めて低いと考えられます。
3.利用できるのは公務員に限られる
文字通り共済「組合員」のみが利用できる制度なので、公務員を退職して民間企業へ転職した場合などは新たに積み立てができなくなります(積立金は退職時に精算することになります)。
利用者が限定される分、転職の予定がある人にとっては長期継続しづらい点もデメリットと言えるでしょう。
4.積立額に上限がある
共済積立貯金には各共済組合ごとに預けられる上限金額が定められています。
例えば神奈川県の市町村職員共済組合では上限3,000万円、埼玉県で2,500万円などと制限があり、一定以上は積み増せません。
ただし上限額は高めに設定されており、多くの人にとって当面影響はないでしょう。また利率も金利環境に応じて見直され、近年は引き下げ傾向とも言われます。
新NISAの特徴とメリット・デメリット
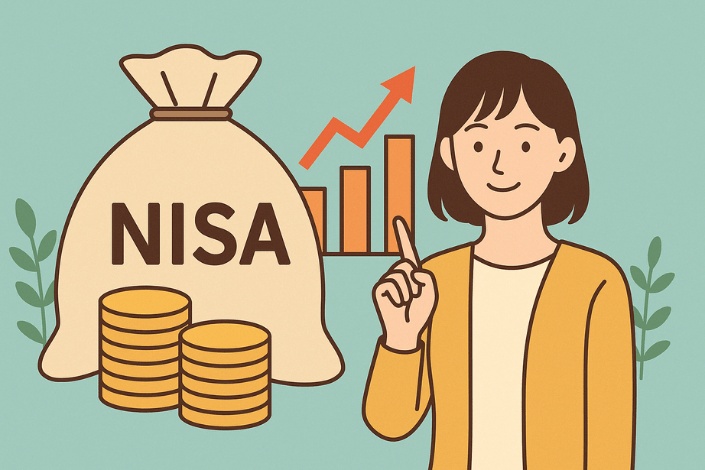 次に、新NISA(少額投資非課税制度)について押さえましょう。新NISAは少額からの長期・分散投資を支援するために政府が設けた非課税制度です。
次に、新NISA(少額投資非課税制度)について押さえましょう。新NISAは少額からの長期・分散投資を支援するために政府が設けた非課税制度です。
証券会社などで専用のNISA口座を開設し、投資信託(投資のプロが運用するファンド商品)を中心にコツコツ積み立てることで資産形成を図ります。
運用で得られた利益に税金がかからない優遇措置が特徴で、公務員を含め誰でも利用できる制度です(※副業扱いになる心配もなく、年末調整や確定申告も不要です)。
新NISAのメリット
1.運用益が非課税でお得
新NISA最大の特徴は、投資で得られた運用益(利益)が非課税になることです。
通常、金融商品で利益や分配金を得た場合は約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座での運用益には税金が一切かかりません。
税金を差し引かれず利益を丸ごと受け取れるため、長期的に見ると大きな節税効果が期待できます。
資産運用初心者でも、この非課税メリットは見逃せないポイントです。
2.長期投資で高い利回りが期待できる
投資信託の内容や市場の状況によりますが、新NISAで購入できる主なファンド(例えば株式インデックスファンドなど)は、年平均3~5%以上の利回りが期待できると言われています。
過去の実績では年間で3~10%程度のリターンが得られたケースもあり、これは共済貯金の利率(1%前後)より高い水準です。
複利効果も働くため、長期間積み立てることで大きな資産成長が見込めます。
3.少額からコツコツ投資できる
新NISAは毎月少額(例えば毎日500円など)からでも始められます。
銀行口座から自動引き落としで投資信託を買い付ける設定にすれば、共済貯金のように半自動で積立可能です。
無理のない範囲でコツコツ積み立てられるので、資産運用の経験がない初心者でも始めやすいでしょう。
毎月定額を積み立てることでドルコスト平均法の効果により価格変動リスクも平準化できます。
4.必要なときに引き出せる柔軟性
新NISAで購入した投資信託は、必要があれば途中で売却して現金化することも可能です(引き出し制限のあるiDeCoと違い、資金の流動性が確保されています)。
非課税枠から外れてしまう点には注意が必要ですが、急な出費ができたときにも対応できる柔軟性はメリットと言えます。
基本的には長期運用が前提ですが、「いつでも換金できる」という安心感は心理的な支えになるでしょう。
新NISAのデメリット
1.元本割れのリスクがある
投資である以上、新NISAでは市場の状況によっては元本(投資したお金)が目減りするリスクがあります。
価格変動により、一時的に評価額が投資元本を下回る(含み損になる)こともあり得ます。
預貯金とは異なり、元本と利息が確約されていない点はデメリットと言えます。
ただし長期に分散投資を行えばリスクは軽減され、期間が長いほどプラスに転じる可能性は高まります。
2.利益が保証されない
共済貯金のようにあらかじめ決まった利率で確実に増えるわけではなく、将来のリターンが不確実です。
市場環境によっては思ったほど増えない、あるいはマイナスになる可能性もゼロではありません。
せっかく積み立てても結果が読めない点に不安を感じる人もいるでしょう。資産運用にはある程度の割り切りと長期目線が必要になります。
3.口座開設や商品選びの手間
新NISAを始めるには、証券会社でNISA口座を開設し、自分で投資信託の商品を選ぶ必要があります。
共済貯金のように人任せで簡単に始められるわけではなく、多少の手続きと投資商品の勉強が求められます。
しかし近年はネット証券で口座開設も簡単になり、商品も金融庁が厳選した長期向け投信のみなので初心者でも商品選びで大きく失敗しにくい環境が整っています。
4.年間投資額に上限がある
新NISAには年間で投資できる額に制限があります。
旧制度では年間40万円まで、2024年開始の新NISA制度では「つみたて投資枠」として年間120万円までと上限が決まっています(非課税保有期間も無期限に拡大されました)。
一般的な公務員の収入であれば上限額まで投資できれば十分とも言えますが、
もっと大きな額を運用したい場合はNISA枠を超える部分に別途課税口座で投資する必要があります。
共済積立貯金と新NISAの違いを比較
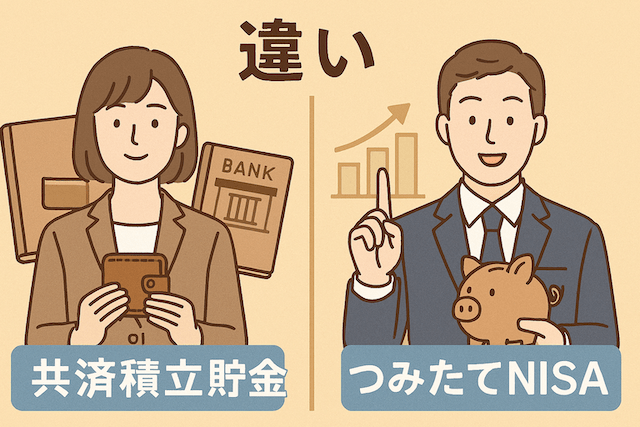
以上の特徴をまとめて、共済積立貯金と新NISAの違いを分かりやすく整理してみましょう。
安全性・元本保証の違い
共済積立貯金は市場リスクがなく元本割れしない安定した商品です。ただし預金保険の対象外である点には注意が必要です。
一方、新NISAは投資商品のため元本保証はなく、価格変動リスクがあります。安全性を最重視するなら共済貯金、有る程度リスクを取っても増やしたいならNISAといった違いがあります。
利回り・リターンの違い
共済貯金の利率はおおむね年0.2~1%台で推移し、銀行預金より高いものの上限は決まっています。
一方、新NISAで投資するファンドは市場次第で数%~十数%のリターンも期待でき、長期的な資産増加率はこちらが上回る可能性が高いです 。つまり、堅実に小さく確実に増やすのが共済貯金、大きなリターンを狙って積極的に増やすのがNISAと言えます。
税金面の違い
共済貯金の利息には20.315%の税金がかかり、利息の約2割は手取りになりません(利息は源泉徴収される)。
これに対し、新NISAは運用益がすべて非課税のため、利益を丸ごと受け取れます。
税制面ではNISAが圧倒的に有利で、「税引後利回り」の差は思った以上に大きくなります。
流動性・使い勝手の違い
共済貯金は職場で手続きすれば比較的いつでも解約・引き出しが可能ですが、基本的には長期貯蓄を目的とした仕組みです。
新NISAも原則長期運用を目指すものの、投資信託を売却すれば資金を引き出せるため緊急時の現金化も可能です。
ただしNISA枠で売却すると非課税枠が減ってしまう点には留意しましょう。
どちらも積立型で途中で積立額の変更は柔軟にできますが、共済貯金は手続きが職場経由、NISAはネット等で自分で管理といった違いもあります。
利用対象者の違い
共済積立貯金は公務員という立場の人だけが利用できます。
一方、新NISAは公務員を含め日本国内在住の成人であれば誰でも利用できます。
したがって公務員であっても将来ずっと公務員でいるとは限らない場合、NISAのほうが継続性が高いと言えるかもしれません。
公務員に新NISAがおすすめな理由
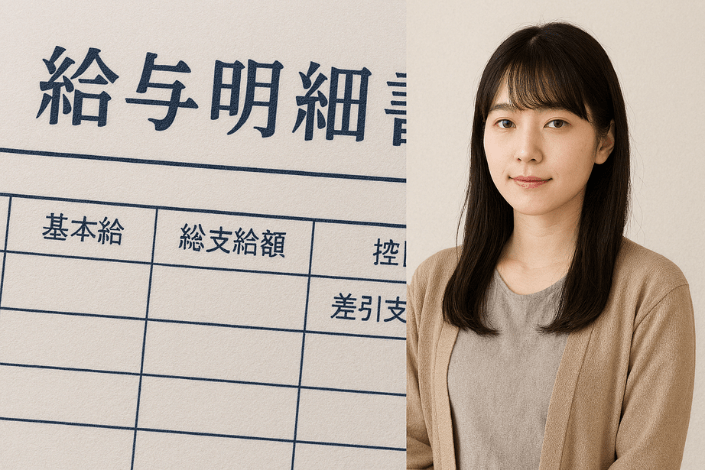 公務員の方にも新NISAはぜひ検討していただきたい有力な選択肢です。
公務員の方にも新NISAはぜひ検討していただきたい有力な選択肢です。
もちろん保守的な運用を好む人にとって共済貯金は魅力的ですが、安定した公務員だからこそ逆に積極的な資産形成にも挑戦しやすいとも言えます。
ここでは、公務員に新NISAをおすすめできる主な理由を整理します。
将来の資産形成に有利
公務員は退職後に年金があるとはいえ、昨今の情勢では公的年金だけで豊かな老後を送るのは難しいとされています。
新NISAで若いうちから長期投資を続ければ、老後資金や将来の備えとして大きな資産を築ける可能性があります。
安定収入がある公務員だからこそ、毎月決まった額を投資に回しやすく、計画的に資産形成を進められます。
共済貯金より高いリターンが期待できる
前述の通り、共済積立貯金の利率は1%前後ですが、新NISAで購入できる投資信託の期待リターンはそれを上回ります。
特に物価上昇(インフレ)があると、低金利の預貯金では実質目減りしてしまうリスクがあります。
新NISAであればインフレに負けない利回りを得られる可能性があり、長期的に見て資産を増やすには理にかなった選択肢と言えます。
非課税メリットを活かせる
公務員も給与所得がある以上、運用益非課税のメリットは大きいです。
通常は利息や運用益に20%程度課税されますが、新NISAならその税金分も手元に残ります。
例えば共済貯金で利息が出ても約2割は税金で引かれますが、NISAなら全額が自分のものになります。
税制優遇を活かさない手はなく、公務員だからといって遠慮する必要はありません。
長期分散投資でリスクを抑えやすい
資産運用に不安を感じる公務員の方でも、新NISAなら仕組み上リスクを抑えやすくなっています。
長期かつ毎月積立(時間分散)し、さらに投資信託自体も国内外の株式や債券に分散投資する商品が多いです。
プロが運用するファンドに任せることで個別株を売買するより安全ですし、「ほったらかし」で運用できる点も忙しい公務員には適しています。
少額から始めて徐々に慣れていけば、大きな失敗リスクなく運用スキルを身につけることもできるでしょう。
以上の理由から、公務員にも新NISAは十分おすすめできる制度です。
実際、「公務員だけど新NISAをやっている」という人も年々増えています。資産形成の手段として前向きに検討してみる価値があるでしょう。
共済積立貯金と新NISAを併用する上手な方法
 ここまで見てきたように、共済積立貯金と新NISAはそれぞれ異なるメリットがあります。
ここまで見てきたように、共済積立貯金と新NISAはそれぞれ異なるメリットがあります。
実は両方を併用することも可能であり、公務員の中にはどちらも活用して資産運用している方も多くいます。
では、二つをどう組み合わせると効果的でしょうか。
短期の安心資金+長期の成長資金に分ける
基本的な考え方は、手元資金を「安全な貯蓄部分」と「積極的な運用部分」に分けることです。例えば毎月の貯蓄額を「半分は共済貯金、半分は新NISA」と配分すれば、一方で安全資金を確保しつつ、もう一方で将来に向けた資産増加も狙えます。
共済貯金に一定額を積んでおけば、万一投資の評価額が下がっても心の支えになります。
逆に市場が好調で資産が増えているときは、共済貯金の安定利息が物足りなく感じるかもしれませんが、そのバランスが重要です。
目的やリスク許容度に応じて配分を調整
個人の状況によって最適な併用バランスは異なります。
保守的な運用を好む人は共済貯金を7割・NISAを3割といったように安全重視にし、積極的に増やしたい人はNISAを重め(例えばNISA7割・貯金3割)にするなど配分を工夫しましょう。
若い公務員で時間に余裕があるならNISA比率を高めに、定年が近い人やすでに十分貯蓄がある人は安全資産を厚めにする、といった考え方も一つです。
自分のリスク許容度とライフプランに合わせて無理のない範囲で割合を決めてください。
まずは共済貯金で土台作り、その後NISAを拡大
資産運用初心者でいきなり投資は不安…という場合、最初は共済積立貯金で緊急予備資金や生活防衛資金となるまとまった額を貯めておくのも良い方法です。
例えば数年間で給与天引きにより数十万円の貯蓄ができたら、その一部を取り崩してNISAの初期投資に充てるという使い方もできます。
共済貯金で貯めたお金を元手にNISAで運用すれば、心理的な不安も和らぎ資産運用をスタートしやすくなるでしょう。
併用することで「守り」と「攻め」のバランスを取ることが可能です。
共済積立貯金と新NISAは対立する選択肢ではなく、公務員ならではの強みを活かして両方上手に使うことで、安定感と資産成長力を両立できます。
まとめ
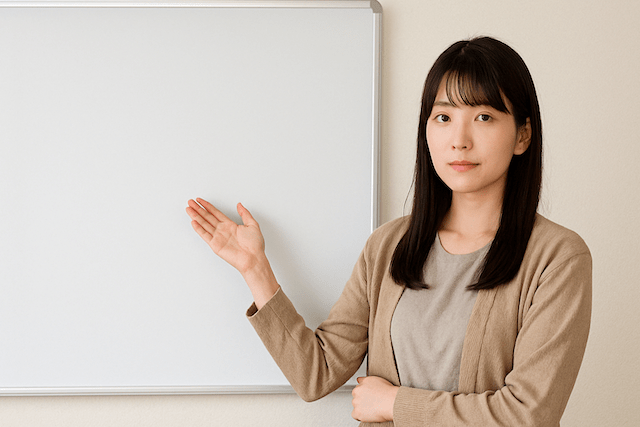
公務員の共済積立貯金と新NISAは、それぞれ優れたメリットを持つ資産形成手段です。
元本の安全性や確実な利息を重視するなら共済積立貯金が適していますし、長期的な資産拡大や非課税メリットを活かしたいなら新NISAが魅力的です。
どちらが「正解」ということはなく、ご自身のリスク許容度や将来の目的に応じて選ぶことが大切です。
保守的な方はまず共済貯金で着実に貯め、慣れてきたら新NISAを少額から始めてみるのも良いでしょう。
逆に資産形成に意欲的な方は早いうちから新NISAをフル活用し、同時に共済貯金も緊急予備資金用としてキープするという併用がおすすめです。
共済積立貯金と新NISAの違いを正しく理解した上で、それぞれのメリットを最大限に活かし、公務員生活の強みを活かした賢い資産運用を実践してみてください。