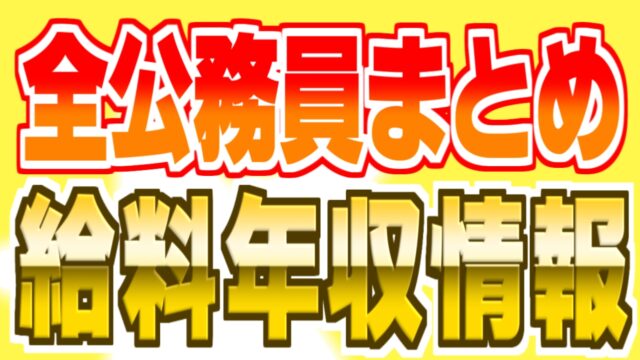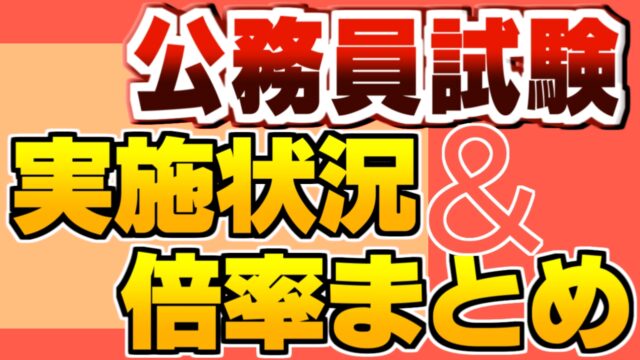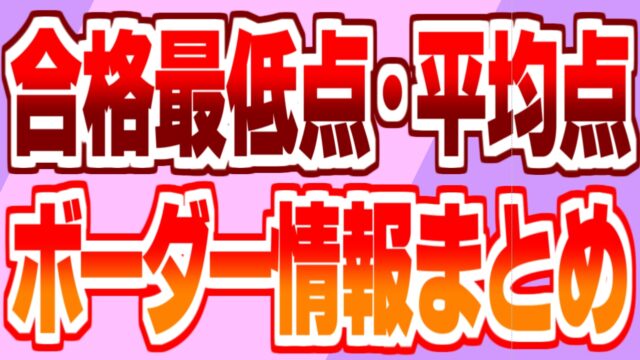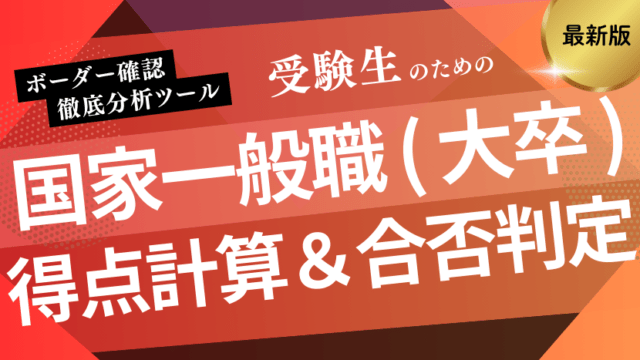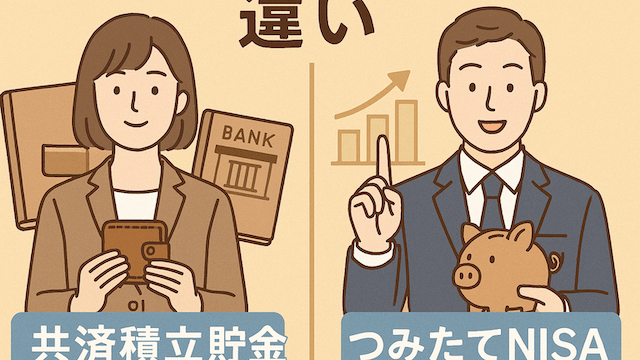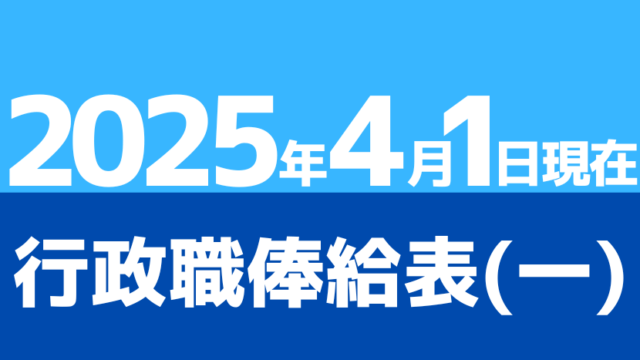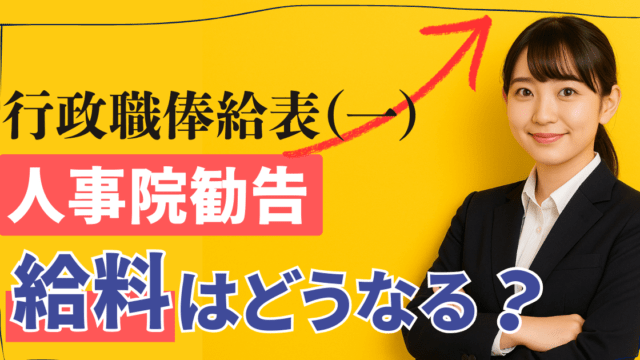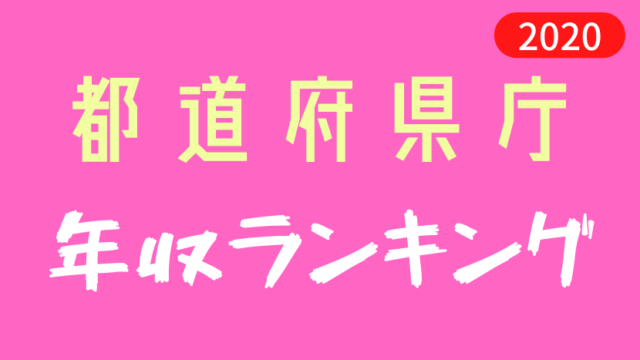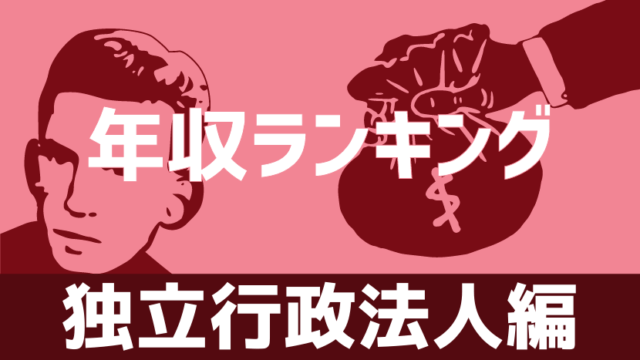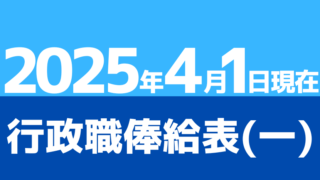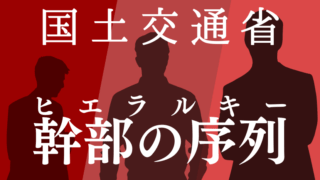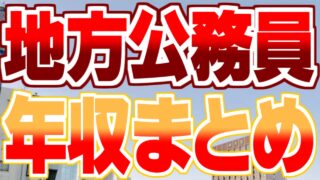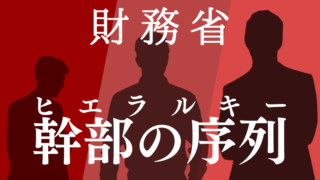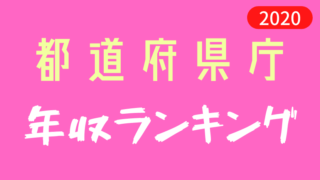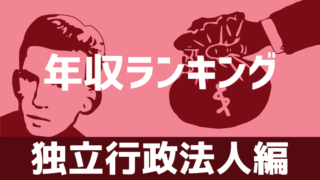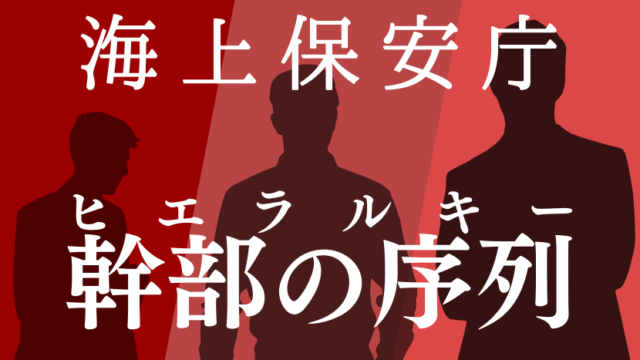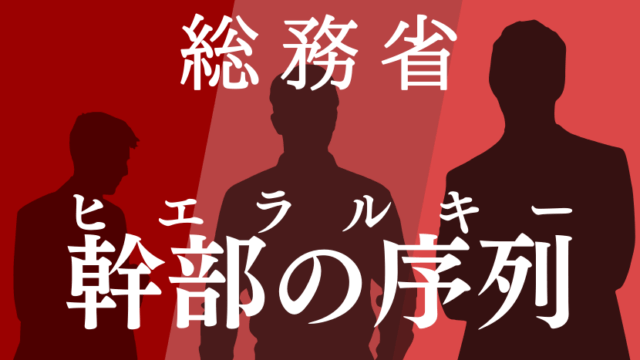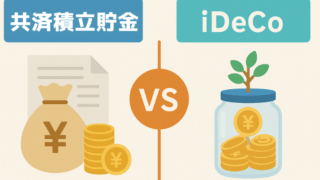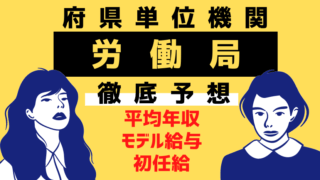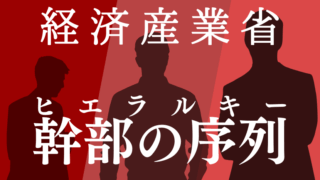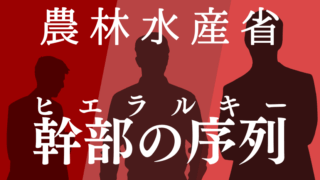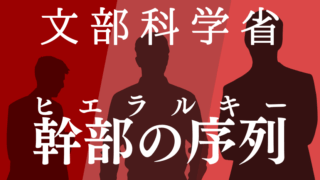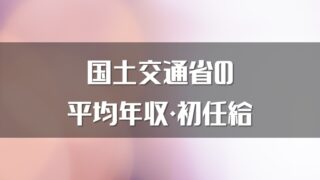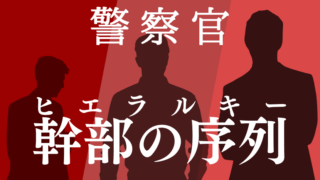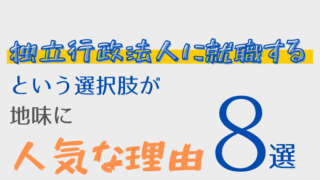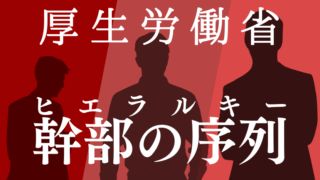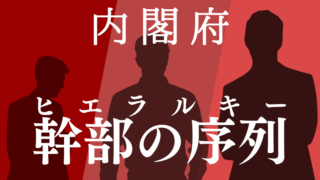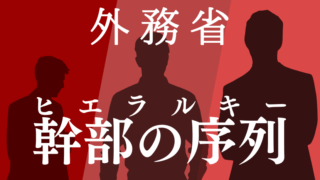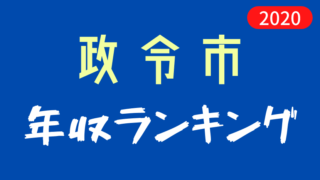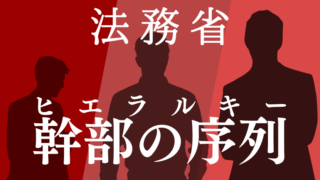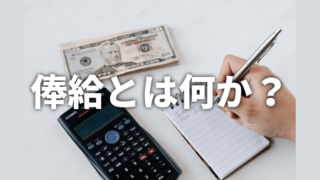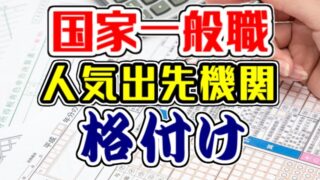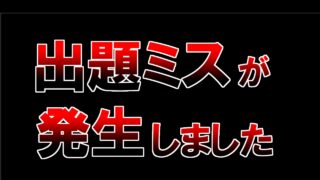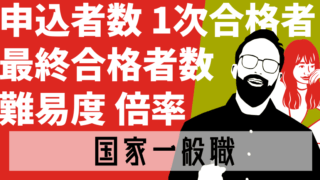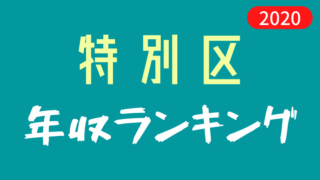目次
はじめに
「早慶まで行って公務員って負け組なの?」――そんな言葉がネット上で散見される中、自分の進路選択に自信が持てなくなる人が増えています。
特に、周囲が総合商社や外資系、コンサル、メガベンチャーに進む中、「安定」を理由に公務員を志すことに、引け目を感じてしまう人も少なくありません。
しかし、進路選択において本当に大切なのは、肩書きや他人の評価ではなく、自分がどんな人生を送りたいかという軸です。
本記事では、「早慶卒で公務員は負け組なのか?」という問いを出発点に、公務員という選択肢の価値を多角的に検討していきます。
なぜ「早慶で公務員は負け組」と言われるのか?
周囲との比較意識(大手民間・外資など)

早慶といった難関私大に通う学生は、就職市場において高い評価を受けやすく、外資系コンサルや総合商社、大手金融機関など、いわゆる“花形”の業界に進む人が多数派です。
大学内でも、そうした企業の内定獲得が一種の「成功モデル」とされる風潮があります。
そのような環境の中で、公務員という進路を選ぶと、「え、なんで?」という反応を受けることがあります。
特に、国家公務員でもなく地方公務員となると、「せっかく早慶に行ったのに、もったいない」「勝ち組ルートを外れた」といった目で見られることがあるのです。
年収・キャリアの成長スピードの違い
もうひとつ、公務員が「負け組」と見なされやすい理由に、年収やキャリアの成長スピードがあります。
民間の大手企業では、20代のうちから年収600〜800万円を稼ぐ人もおり、成果を出せば若くして役職に就くことも珍しくありません。
インセンティブ制度も充実しており、実力主義の世界で自己成長を実感しやすい環境が整っています。
一方、公務員は基本的に年功序列。若いうちは年収が抑えられ、30代でようやく500万円前後になるケースが一般的です。
成果を出してもすぐに昇進・昇給するわけではなく、制度上、スピード感に欠ける側面があります。
この点を「成長機会が少ない」「挑戦がない」と感じる人もおり、そうしたイメージが「負け組」論に拍車をかけているといえるでしょう。
実際のデータから見る「公務員就職の早慶卒の現実」
早慶からの公務員合格者数の推移

早稲田大学や慶應義塾大学からは、毎年多くの学生が国家総合職、国家一般職、地方上級などの公務員試験に合格しています。
例えば、国家総合職試験では、早稲田大学や慶應義塾大学の合格者数は上位に位置しており、東京大学や京都大学に次ぐ実績を持っています。
また、地方上級試験においても、早稲田大学や慶應義塾大学の合格者数は多く、特に東京都や神奈川県、埼玉県などの自治体での採用実績が豊富です。
これらのデータから、公務員という進路が「選ばれていない」わけではなく、むしろ一定の人気と実績を持つ選択肢であることがわかります。
公務員内での早慶卒のキャリア形成
公務員としてのキャリアにおいても、早稲田大学や慶應義塾大学の卒業生は重要な役割を担っています。
中央省庁や地方自治体では、早稲田大学や慶應義塾大学出身者が管理職や幹部職に就く例が多数あります。
例えば、外務省や防衛省などの中央省庁では、早稲田大学や慶應義塾大学出身の幹部職員が活躍しており、政策立案や国際交渉などの重要な業務を担当しています。
また、地方自治体においても、早稲田大学や慶應義塾大学出身の職員が局長や部長などの要職に就くケースが見られます。
「勝ち組/負け組」で判断していいのか?
価値観の多様化と人生100年時代

現代は「人生100年時代」と言われるようになり、キャリアのあり方も多様化しています。
高年収や出世競争だけが幸福の尺度ではなく、安定性や社会貢献、余暇の充実、家族との時間など、重視するポイントは人それぞれです。
その点、公務員は「安定した雇用」「手厚い福利厚生」「社会的信頼」といった“勝ち組”的な要素も多く備えています。
特に、長期的な視点でライフイベント(結婚、育児、介護など)を見据えたとき、公務員の働き方は大きなメリットになります。
「後悔」している人の傾向とは?
とはいえ、公務員として働く中で「思っていたのと違った」と感じる人もいます。
その多くは、激務部署への配属や、成長志向とのギャップに悩んだケースです。
また、周囲の民間企業で活躍する同期への劣等感や、転職市場でのスキルの汎用性に不安を抱くこともあります。
一方で、満足している人の多くは、「社会の役に立ちたい」「地元に貢献したい」「安定した生活がしたい」といった価値観が、公務員という職業と一致しています。
つまり、満足度の差は「職業そのもの」よりも「その人の価値観との一致」による部分が大きいのです。
早慶卒で公務員を選ぶことの意義
民間ではできない「政策」「公共」に携わる醍醐味

公務員の仕事は、民間企業では決して経験できない、国家や自治体の運営、公共サービスの提供、政策の立案といった“社会の根幹”に関わるものです。
自分の業務が直接的に社会全体に影響を及ぼすというスケール感と責任の重さは、公務員ならではの醍醐味といえます。
特に、中央省庁や自治体の企画部門では、「何を変えるべきか」「どうすれば持続可能か」といった本質的な問いに向き合う仕事が多く、学生時代に培った論理的思考力や行動力が大いに活かされます。
出世や年収だけでなく、「社会をどうよくするか」という観点で働きたい人にとって、公務員は非常に魅力的なキャリアなのです。
将来的な柔軟性(出向・転職・起業など)
かつてのように「一度公務員になったら一生安泰」という固定観念は崩れつつあります。
最近では、官民人材交流制度などを通じて、民間企業への出向を経験する公務員も増えており、視野を広げた上で再び行政に戻る柔軟なキャリア形成が可能になっています。
また、近年は自治体職員がスタートアップを起業したり、民間に転職したりといった事例も増加しています。
「一つの組織に留まり続けることが成功」ではなく、「自分の軸を持ちつつ柔軟に動くこと」が重視される時代に、公務員というキャリアは十分に戦略的な選択肢となり得ます。
後悔しないための進路選択とは
「他人の評価」で選ばない

「早慶まで行って公務員はもったいない」「勝ち組になりたいなら民間へ」といった声は、インターネットや身の回りから日常的に聞こえてくるかもしれません。
しかし、そうした意見はあくまで“他人の基準”に過ぎず、それが自分にとっての最適解とは限りません。
仕事に何を求めるかは人それぞれです。収入か、安定か、社会的意義か、ワークライフバランスか――求めるものによって最適な進路は異なります。
大切なのは、「どんな仕事が自分に合っているか」を考えることです。
進路に“正解”はありません。あるのは「自分が納得できる選択肢」だけです。
他人の評価に惑わされず、自分自身の軸で選んだ道こそが、長い人生を通じて後悔の少ない進路になります。
まとめ

早稲田や慶應といった難関大学から公務員を目指すことは、決して「負け組」の選択ではありません。
むしろ、安定性や社会貢献性といった観点から、自分の価値観に合ったキャリアを築く賢明な選択とも言えます。
大切なのは、他人の声ではなく、自分自身の軸を持つこと。納得のいく進路こそが、後悔のない未来につながります。