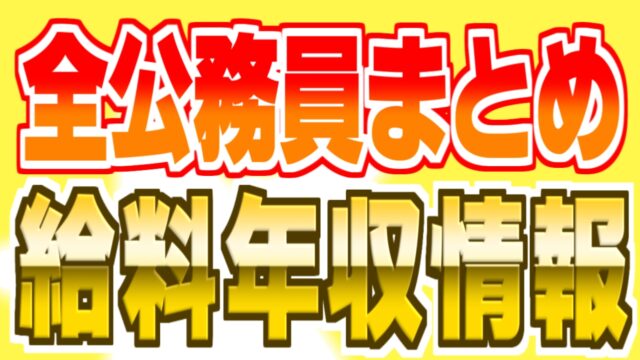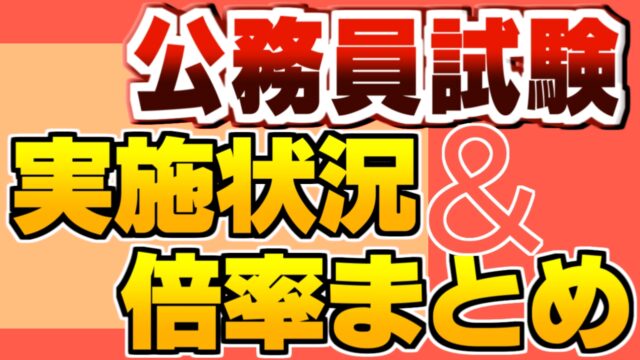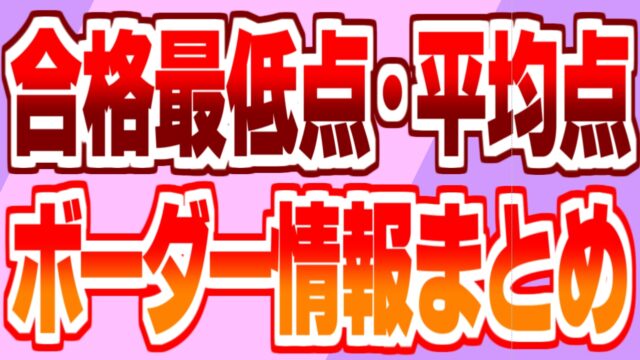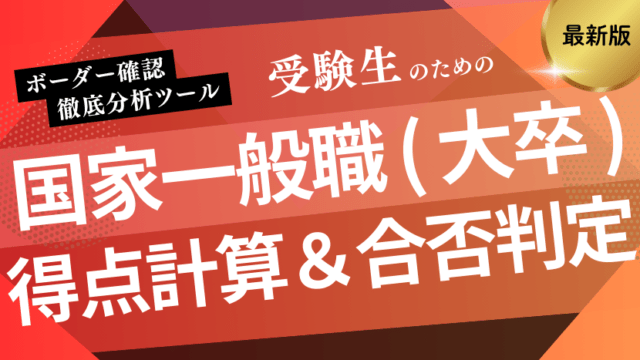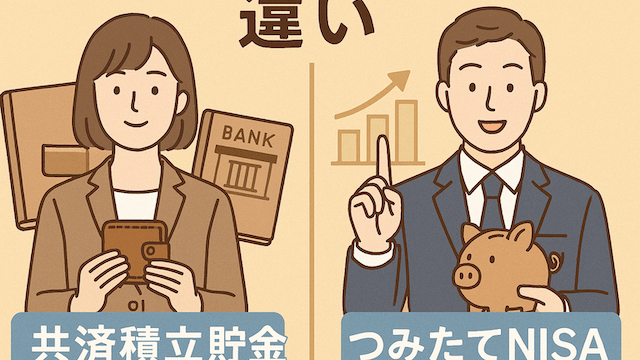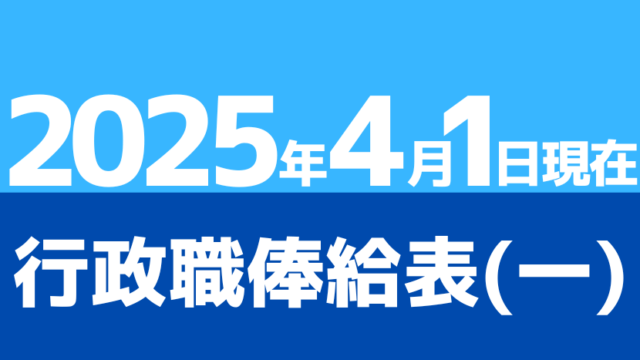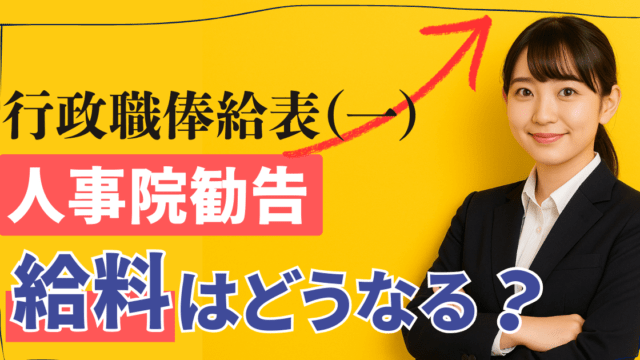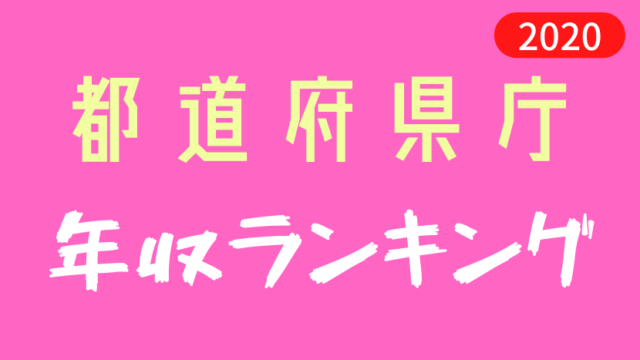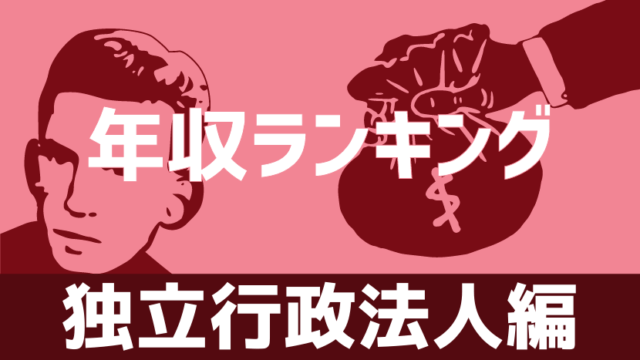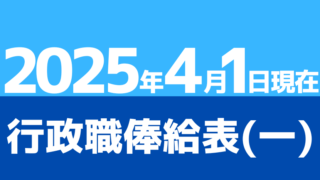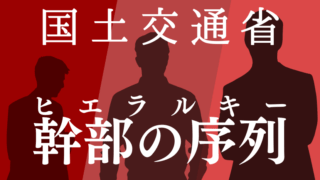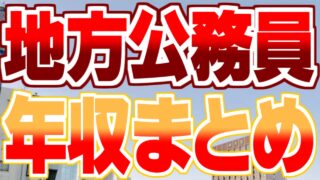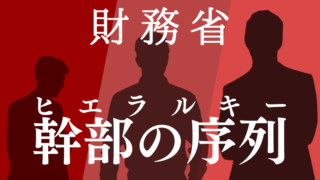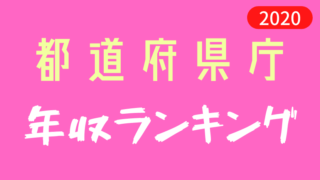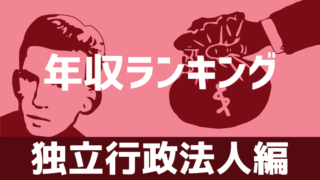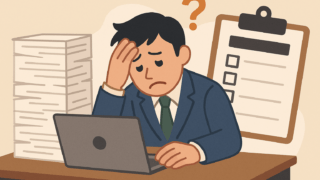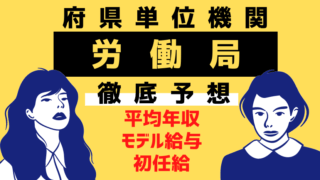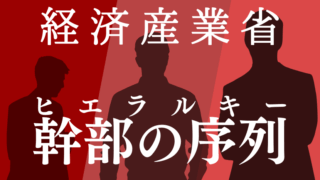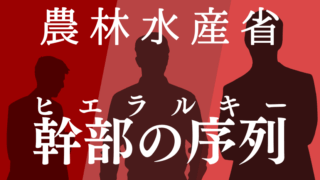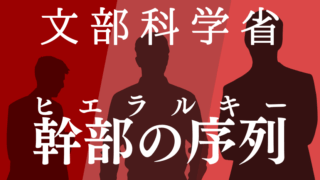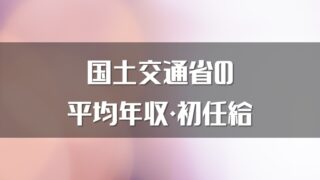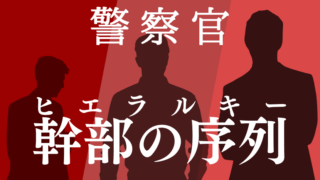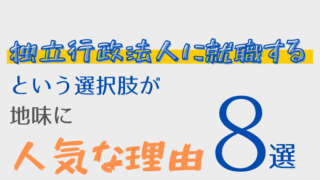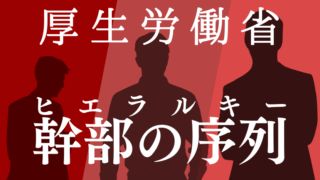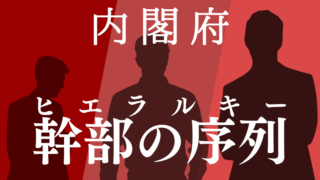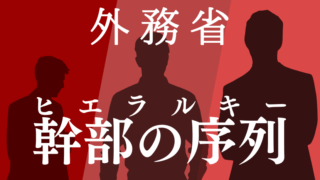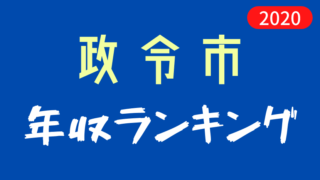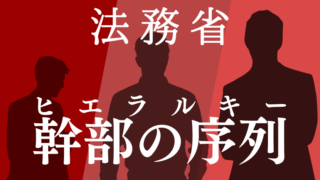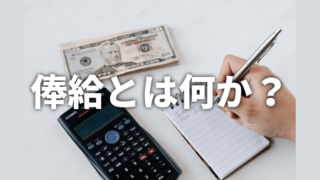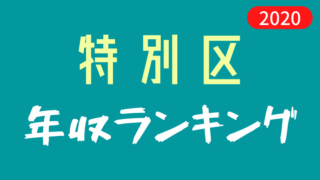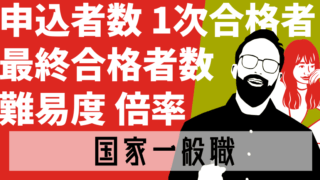目次
2025年4月、人事院は国家公務員の給与改定の基礎資料となる民間企業の給与実態調査を4月23日から6月13日まで実施すると発表しました。
これは、国家公務員の給与が民間企業と比べて適正な水準にあるかを判断するためのもので、例年の流れからすると今年も月給の「引き上げ勧告」が出される可能性が高まっています。これが実現すれば、4年連続の給与増となります。
ただし、こうした報道が出るたびに、「公務員の給料は高すぎる」「税金の無駄だ」といった批判的な意見が飛び交います。
一方で、「民間よりも待遇が悪い」「もっと報われるべき」との声も少なくありません。
つまり、公務員の給与水準をめぐる議論は今なお賛否が分かれるテーマなのです。
本記事では、人事院調査の仕組みや給与の決まり方に加え、公務員の現状や課題、そして今後必要とされる対応について掘り下げていきます。
公務員の給与はどう決まるのか?

国家公務員の給与は、民間との格差を是正するため、人事院が年1回実施する「民間給与実態調査」に基づき調整されます。
この調査では、従業員数50人以上の事業所を対象に、約1万1900件のデータが収集され、基本給・ボーナス・住宅手当・シニア職員の処遇などが分析されます。
しかし、この調査対象については「基準が小規模すぎるのでは」との懸念も根強くあります。
県庁や政令市の職員と比較するには、100人以上の事業所のデータを参考にするべきではないかと感じられることもあります。
実際、かつては100人以上の企業が対象だった時期もあり、比較対象の精度が低下しているとの印象は否めません。
公務員の給与は本当に高いのか?比較の“落とし穴”

公務員の給与水準が「高すぎる」と批判される背景には、比較の基準がバラバラであるという問題があります。
例えば、三大都市圏にある大手企業と比べれば、公務員の年収は決して高いとは言えません。
一方、地方都市の中小企業と比べると、相対的に高く見えることもあります。
また、公務員の給与体系は業種間の格差が少なく、年功的であるため、努力や成果に対する金銭的なインセンティブが乏しいと感じる職員も少なくありません。
さらに、公務員は数年ごとの異動によって業務内容が大きく変わることが多く、財務から都市計画、生活保護の現場まで幅広い分野を担当します。
このような仕組みは「ゼネラリスト育成」にもつながりますが、特定分野の専門性を高めるには不向きであり、民間でいう「キャリアの軸」が見えにくくなることもあります。
就職氷河期世代は“割を食ってきた”存在
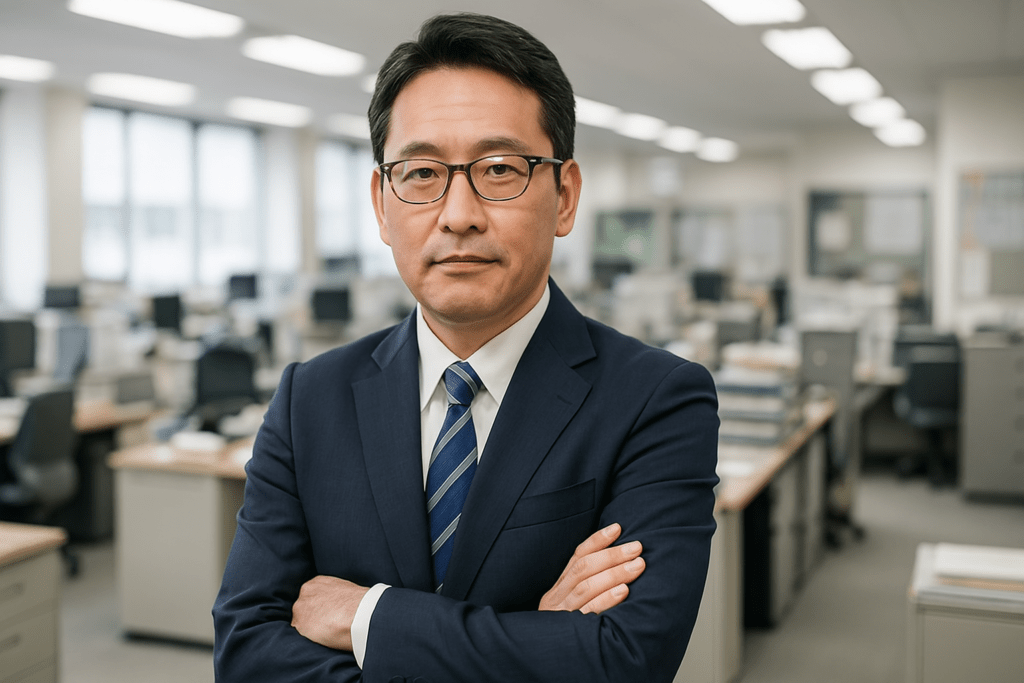 今回の給与調査にあたり、忘れてはならないのが「就職氷河期世代」への処遇改善の視点です。
今回の給与調査にあたり、忘れてはならないのが「就職氷河期世代」への処遇改善の視点です。
この世代は、1990年代後半から2000年代初頭の厳しい採用環境をくぐり抜けて公務員となった層であり、採用人数の少なさに加え、昇給や昇進の機会にも恵まれなかったケースが多く見受けられます。
現在では中堅〜管理職手前の立場となっていますが、待遇面では若年層に比べて相対的に不利な状況にあると感じます。
これまでの制度が“平等”を重視してきた結果、むしろ「世代間の不平等」を生んでしまった側面もあるのではないでしょうか。
今後の給与改定においては、単なるベースアップではなく、こうした世代ごとの待遇格差にも目を向けた調整が求められます。
若者が公務員を避ける時代に突入する一方、再任用・非常勤依存にも限界が
 現在、若者の間で「公務員離れ」が進んでいます。
現在、若者の間で「公務員離れ」が進んでいます。
採用試験の倍率は年々低下しており、「かつてのような安定職」としての魅力だけでは人材を引き寄せられなくなっています。
一方、給与水準の高さを前面に打ち出した大阪府和泉市では、「日本一初任給が高い」というPRが功を奏し、50倍の応募が殺到するという成功例もありました。
このような事例を見ると、やはり優秀な人材は「条件の良いところ」に自然と集まるものだと実感します。
逆に、低賃金・高負荷のまま人材確保を怠った地方自治体では、心を病んで休職する職員や、民間企業へ転職する若手が増加しており、公務の質そのものが揺らぎつつあるように感じられます。
また近年、公務員組織では定年退職後の再任用職員や、会計年度任用職員への依存が進んでいます。
フルタイム正規職員の採用枠が縮小する一方で、非正規的な雇用形態が主流になりつつある現場も多くなっています。
退職後も生活のために働き続けざるを得ない高齢職員が増える中で、次世代へのスムーズな業務引継ぎが行われていないという課題もあります。
公務員制度全体の持続可能性という観点からも、今後の人事政策には抜本的な見直しが必要だと感じます。
まとめ
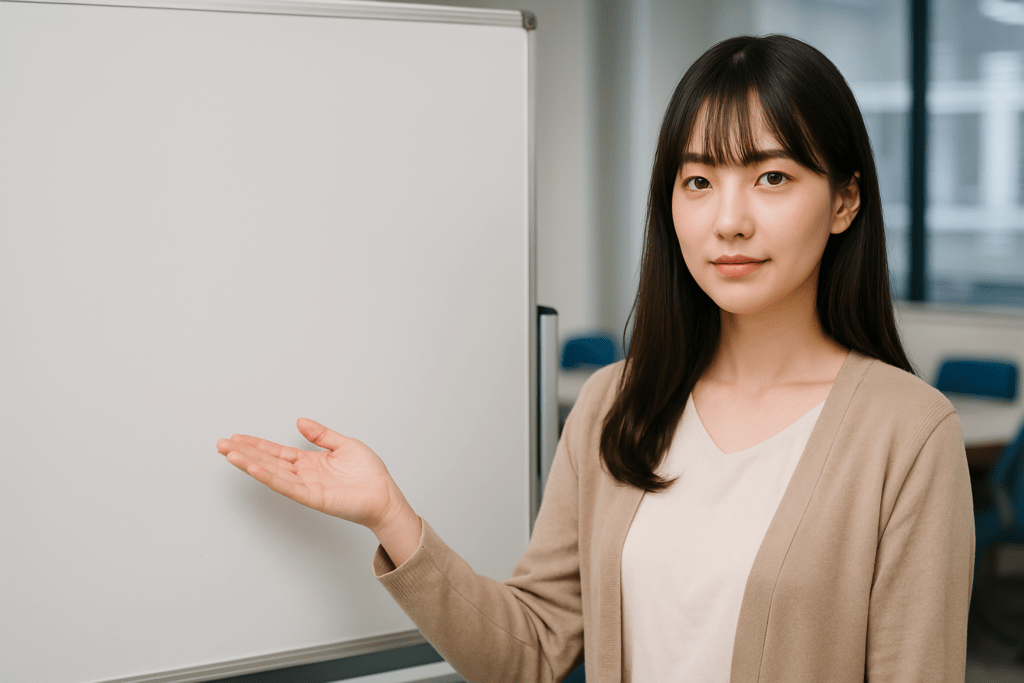 公務員の給与に関する議論は、「高いか安いか」だけで完結するものではありません。
公務員の給与に関する議論は、「高いか安いか」だけで完結するものではありません。
むしろ、採用難、異動の負担、世代間格差、非正規化の進行といった多面的な問題と密接に関係しています。
今後は、人事院による調査の精度向上と柔軟な給与勧告に加えて、国や自治体が公務員制度そのものの意義や魅力を、国民に向けて丁寧に伝えていく努力も必要だと感じます。
待遇面の改善はもちろんですが、公共の利益のために働くという「職業としての価値」を再発信することが、これからの人材確保のカギになるのではないでしょうか。