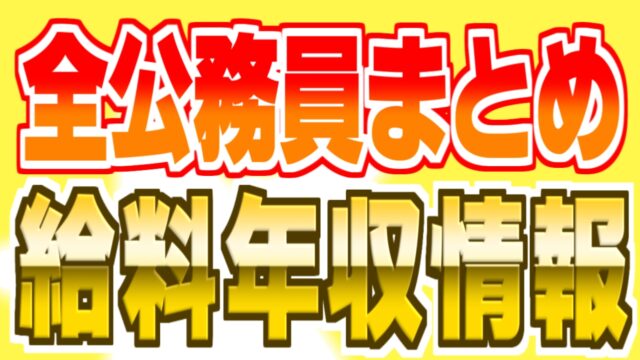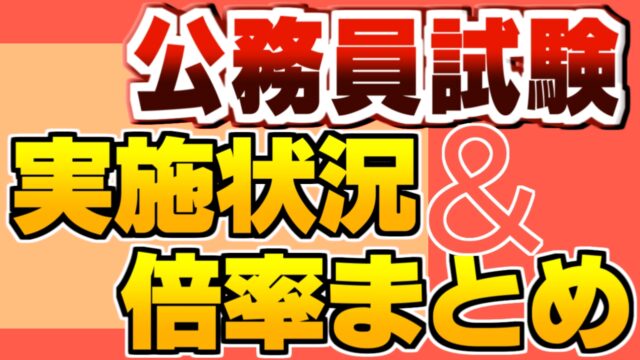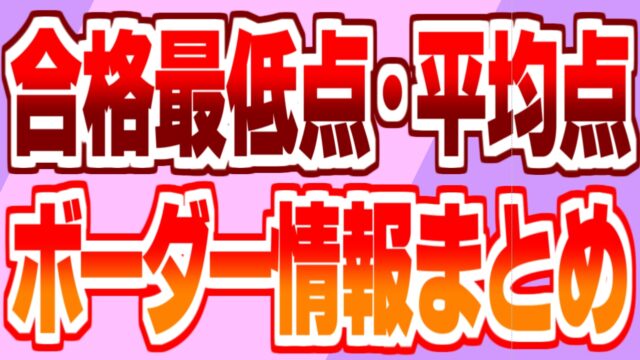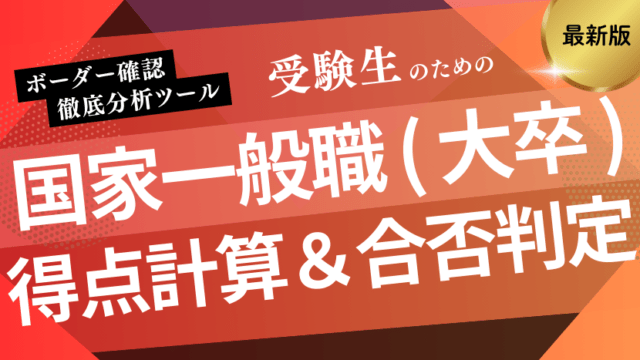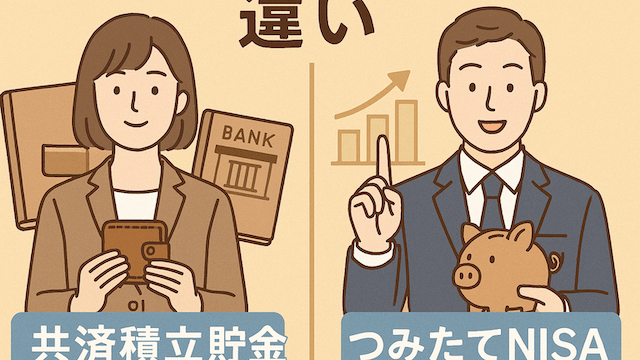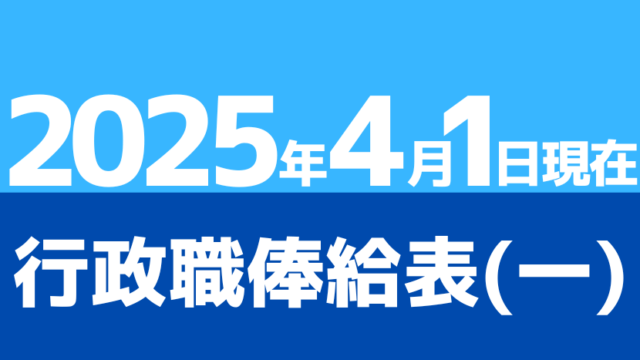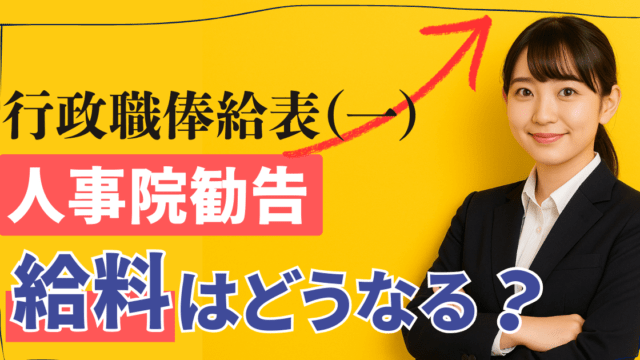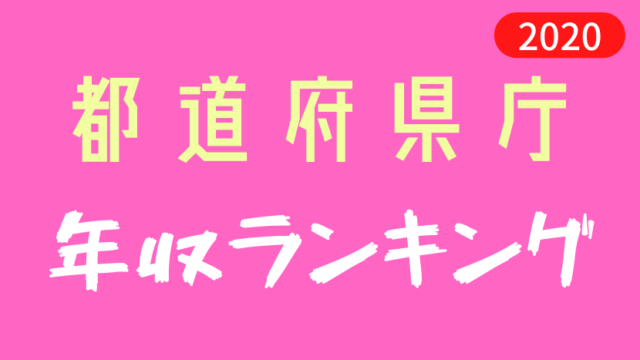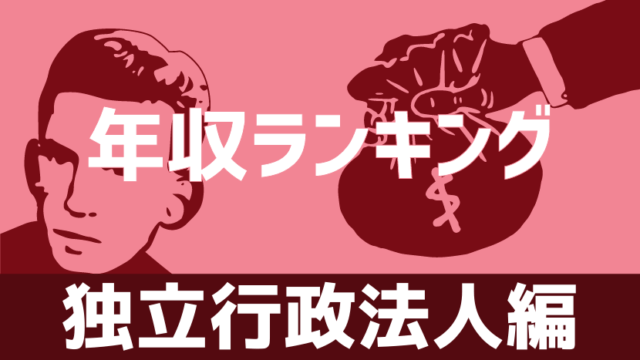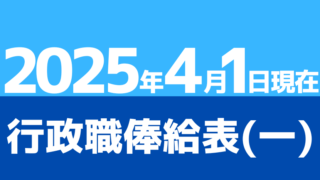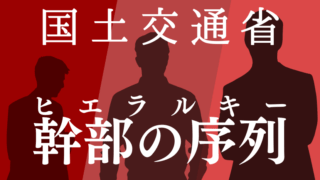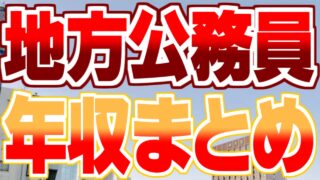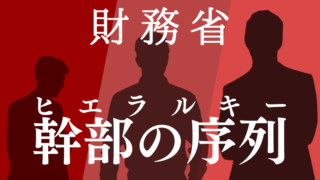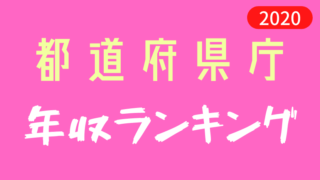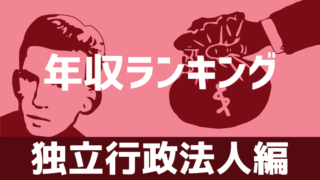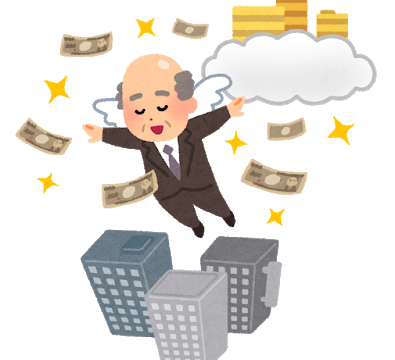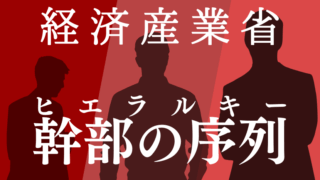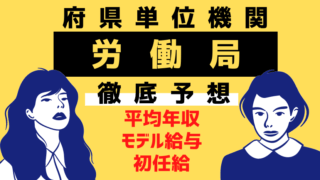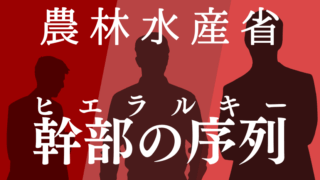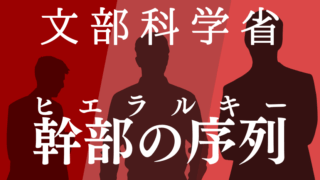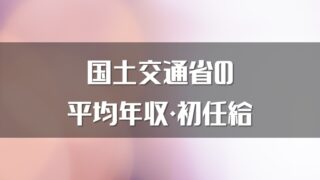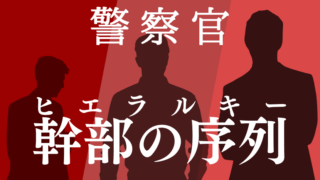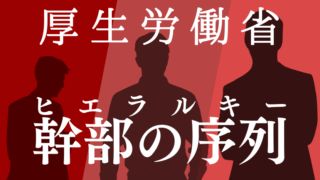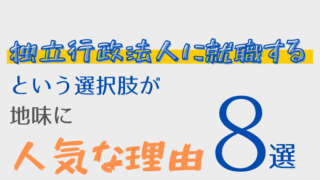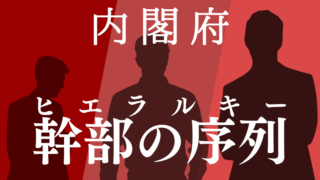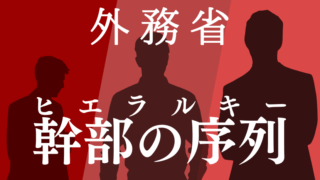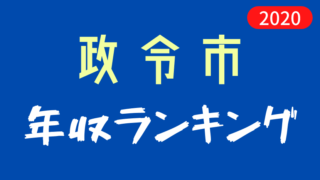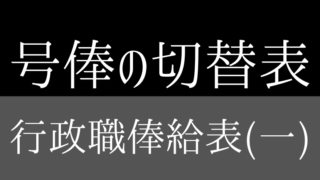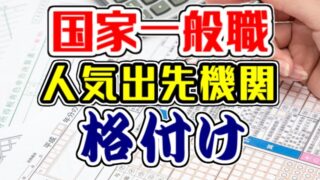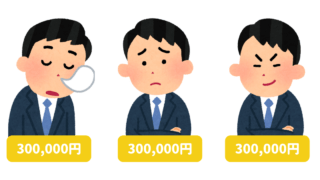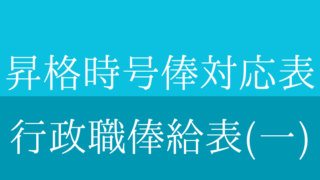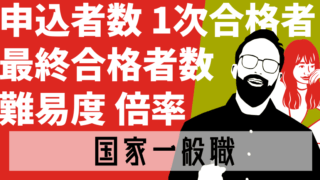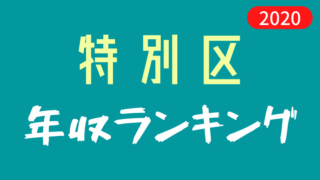目次
この用語のポイント
・「俸給」=公務員の給料の土台になる基本給(俸給月額)
・俸給は俸給表(給料表)で決まる
・地域手当やボーナスは俸給をもとに計算される
30秒でわかる解説!
俸給(ほうきゅう)とは、公務員の給料のうち
原則として毎月支払われる「基本給(俸給月額)」
のことです。
公務員の給料は、大きく分けると
- 俸給(基本給)
- 諸手当(地域手当・通勤手当など)
- 期末・勤勉手当(ボーナス)
で構成されています。
このうち、すべての土台になるのが「俸給」です。
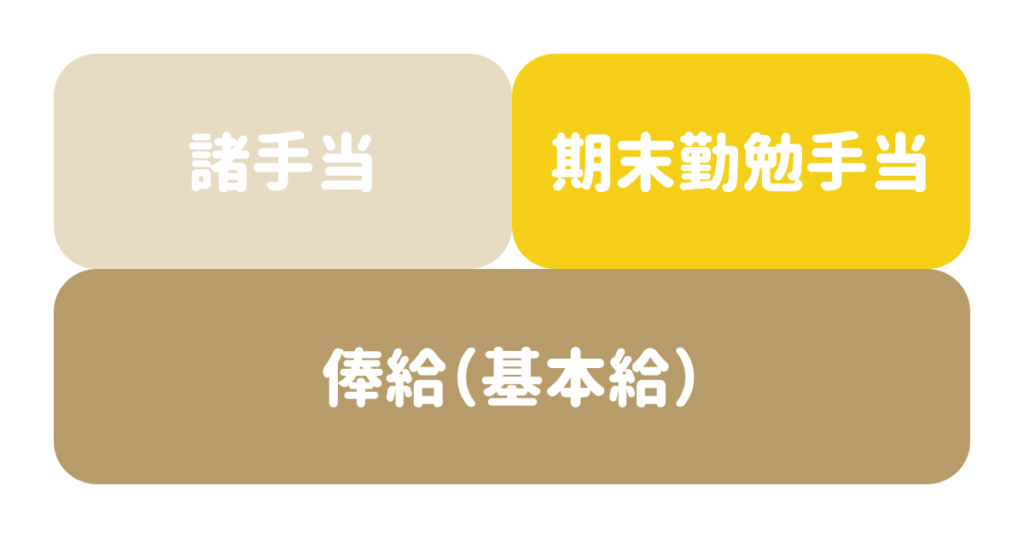
たとえば、
- 地域手当
- 残業代
- 期末・勤勉手当(ボーナス)
は、いずれも俸給をもとに計算されます。
より深く理解したい方へ
俸給はどうやって決まるのか?
公務員の俸給は、
俸給表(給料表)
と呼ばれる表で決まります。
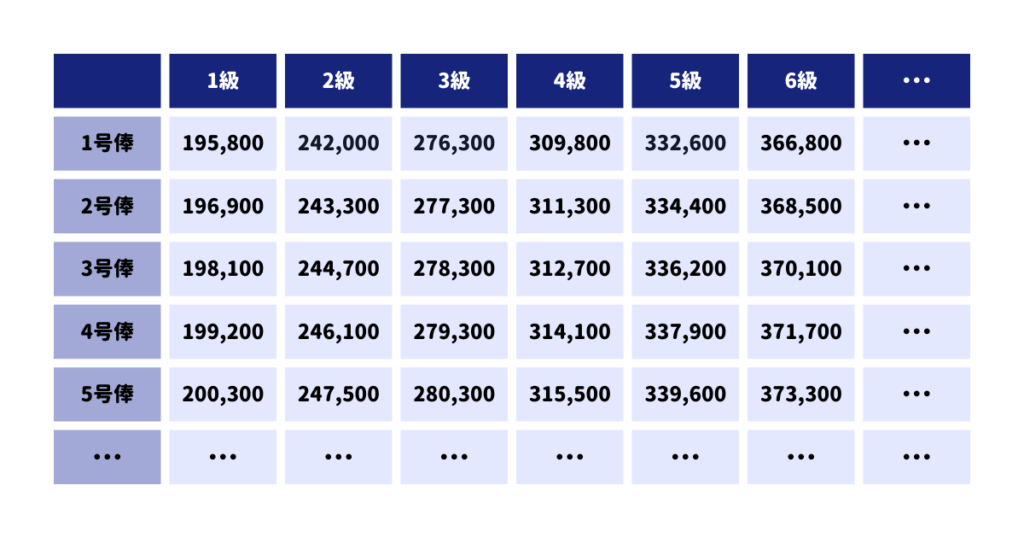
俸給表(ほうきゅうひょう)は
国家公務員の基本給が書いてある表
です。
公務員の給料は、上司の気分で決まったり、「今年はなんとなくこれくらい」で決まったりはしません。
ちゃんとしたルールで決まっています。
そのときに使われるのが、俸給表です。
俸給は「級 × 号俸」で決まる
俸給は、
職務の級 × 号俸
で決まります。
俸給表には、
- 職務の級
- 号俸
がずらっと並んでいて、
その交差したマスに「毎月の基本給の金額」が書いてあります。
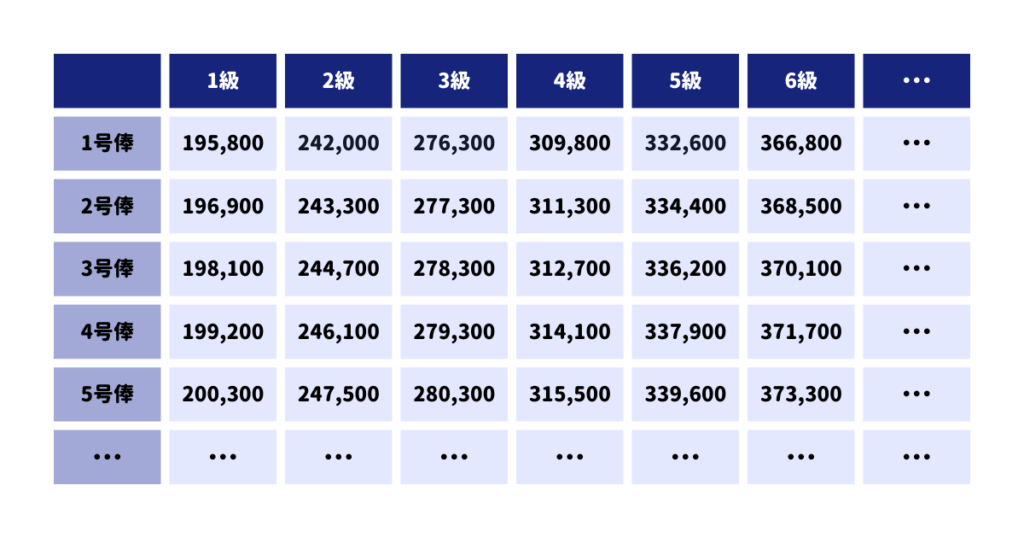
「職務の級」は、
その人が担当している仕事のレベル
を表します。
仕事の
- 複雑さ
- 困難さ
- 責任の重さ
などを基準にして決められます。
たとえば、
・決まった仕事を担当する段階
・チームをまとめる段階
・組織全体を考えて判断する段階
のように、仕事にはレベルがあります。
この「仕事の段階ごとのランク分け」が、職務の級です。
 「号俸」は
「号俸」は
同じ職務の級の中での、給料の位置
です。
もう少しやさしく言うと、
同じレベルの仕事をしている人たちの中で、
「どのあたりの給料か」
を表す番号です。
例えば、こんな感じです。
ある職場に、1級の人が3人いました。
みんな、仕事のレベルとしては同じです。
ただし、経験や評価には差があります。
- 今年入ったばかりの人
- 5年目の人
- 10年目の人
では、給料がまったく同じでは不自然ですよね。
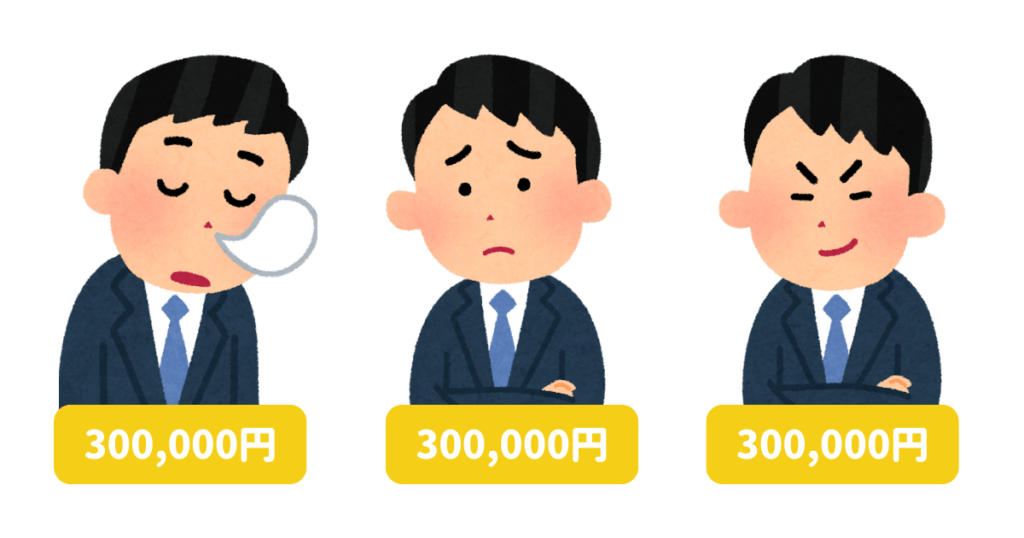 そこで登場するのが、号俸です。
そこで登場するのが、号俸です。
○級の中には、
1号俸
2号俸
3号俸
…
30号俸
のように、
という細かい段階が用意されています。
この
「どの段階にいるか」
を表すのが、号俸です。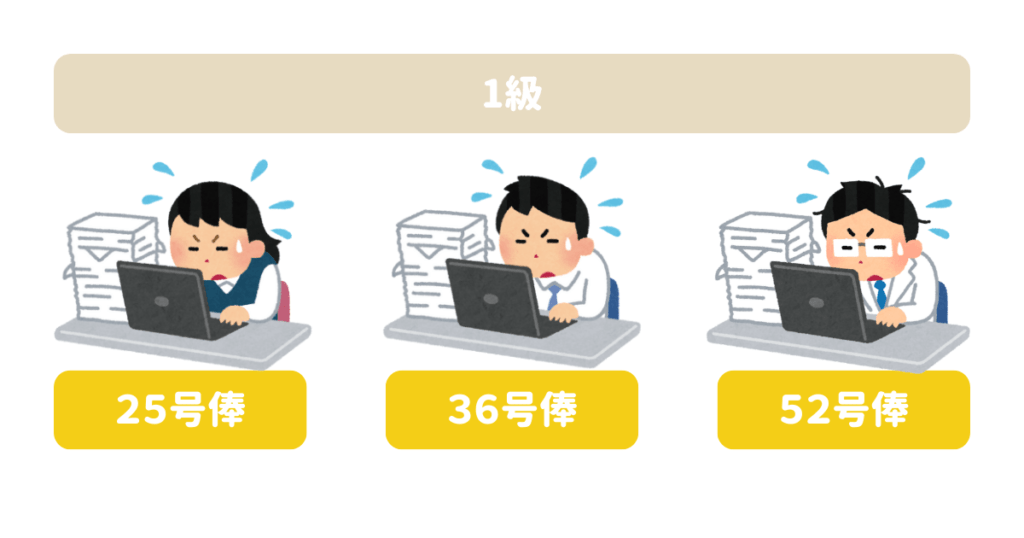
俸給が「土台」になる理由
俸給が土台と言われるのは、
手当やボーナスが俸給を基準に計算されるからです。
たとえば、
- 地域手当 → 俸給の一定割合
- 残業代 → 俸給をもとに時間単価を計算
- ボーナス → 俸給 × 支給月数
という形になります。
つまり、俸給が上がると、
- 毎月の給料
- 手当
- ボーナス
の多くに影響します。
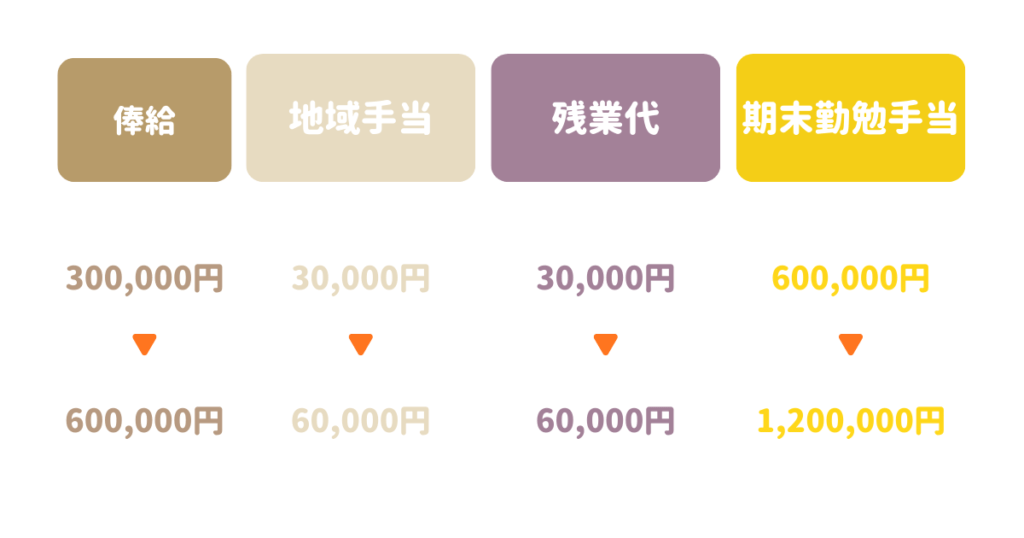
ざっくりまとめ!
「俸給」とは、
公務員の給料の土台になる基本給(俸給月額)
と覚えておきましょう。