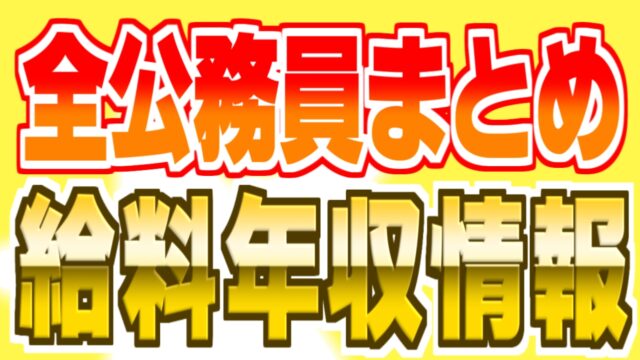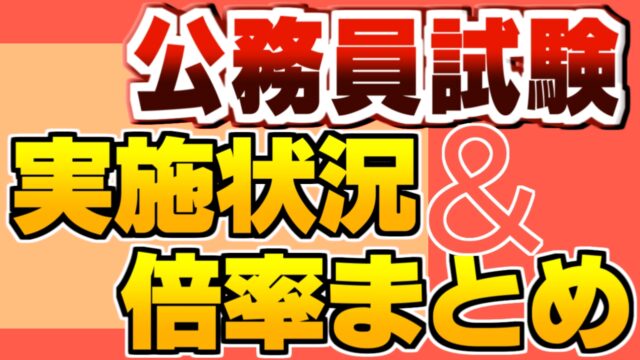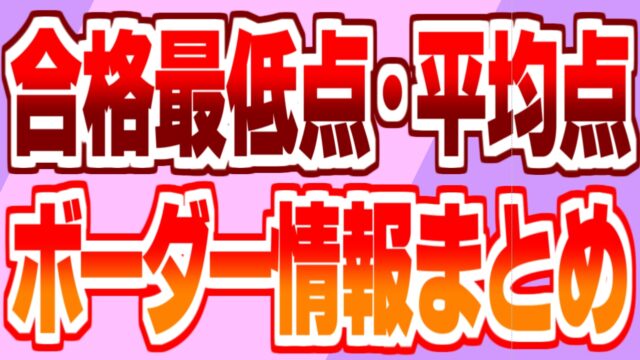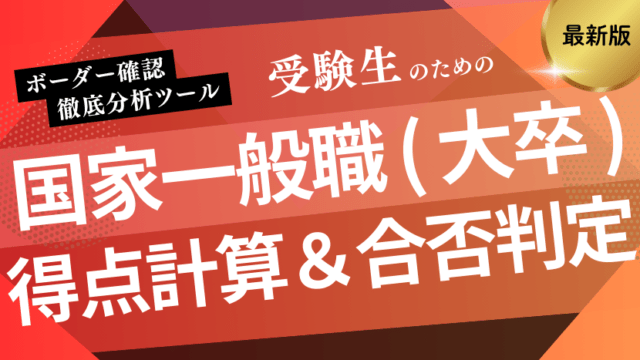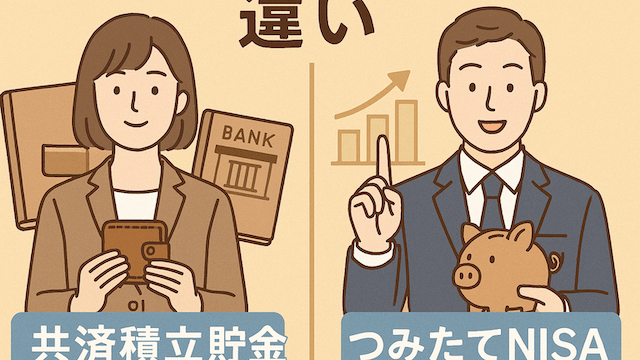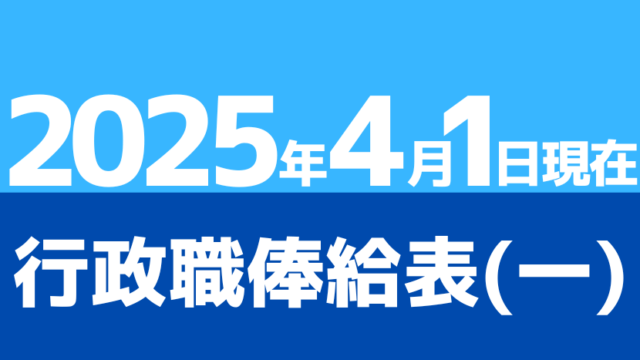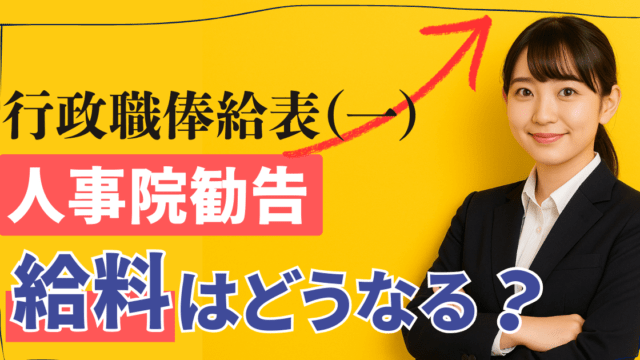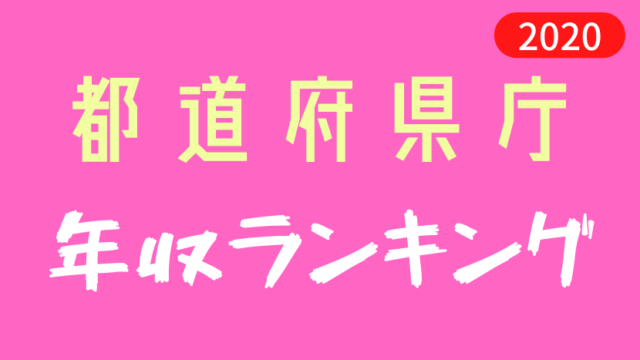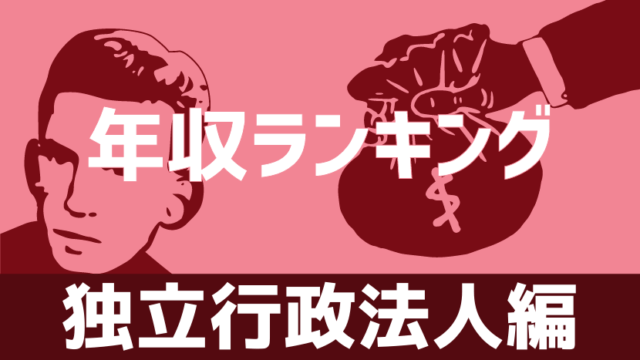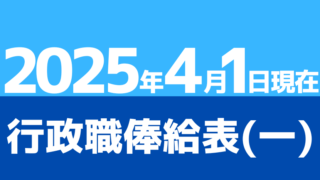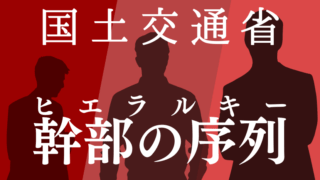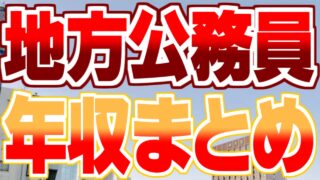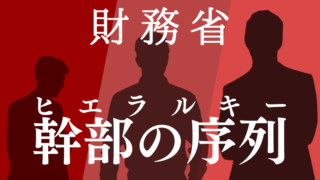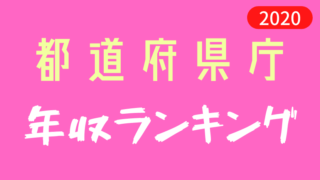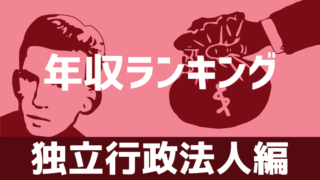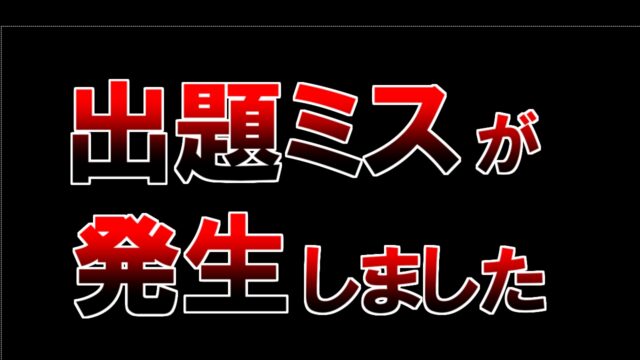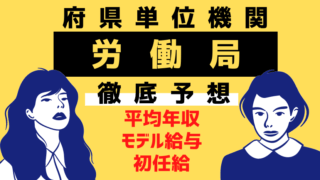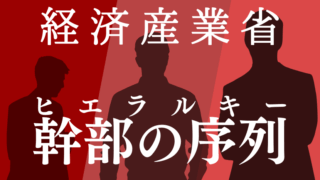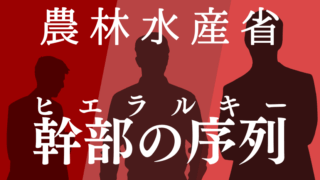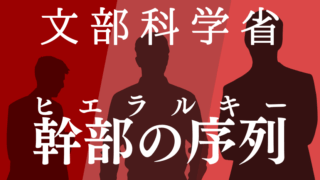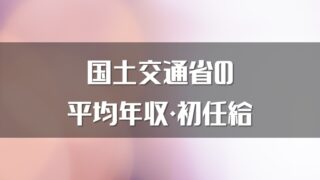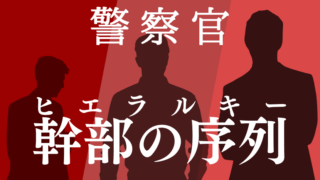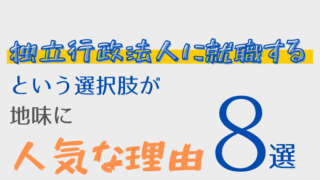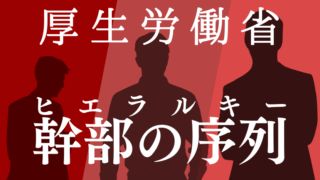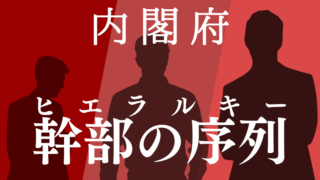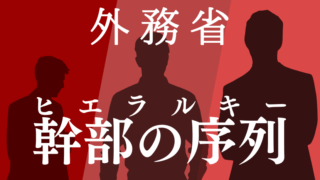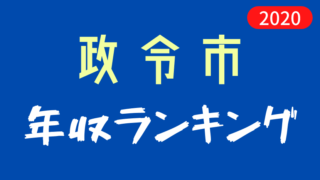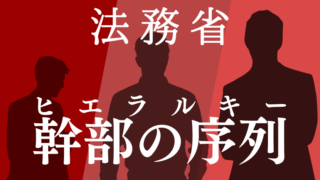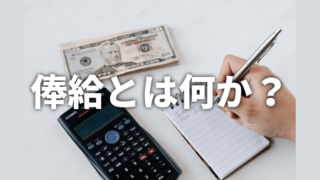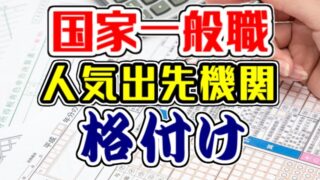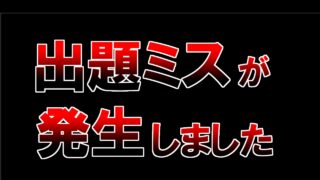目次
2025年4月24日、読売新聞が報じた「町職員が水道料の確定申告失念、延滞税など31万円発生」のニュースは、公務員に求められる職務責任の重さと、それを支える体制の脆弱さを浮き彫りにするものでした。
島根県川本町のケースでは、簡易水道および農業集落排水処理事業に関する消費税の確定申告を職員が失念し、その結果として延滞税・加算税含めて約31万円の支出が生じたとされています。
町としては管轄の税務署へ連絡のうえ申告・納付を済ませ、関係職員への文書訓告という対応を取りましたが、この一件は「担当者のミス」として片づけられるほど単純ではありません。
むしろ、こうしたミスがどの自治体でも起こり得る“構造的な問題”として認識されるべきだと感じます。
本記事では、今回の事例をもとに、地方自治体における業務運営の現実と、ヒューマンエラーが発生しやすい環境の背景を掘り下げて考察します。
なぜ申告ミスが起きたのか?
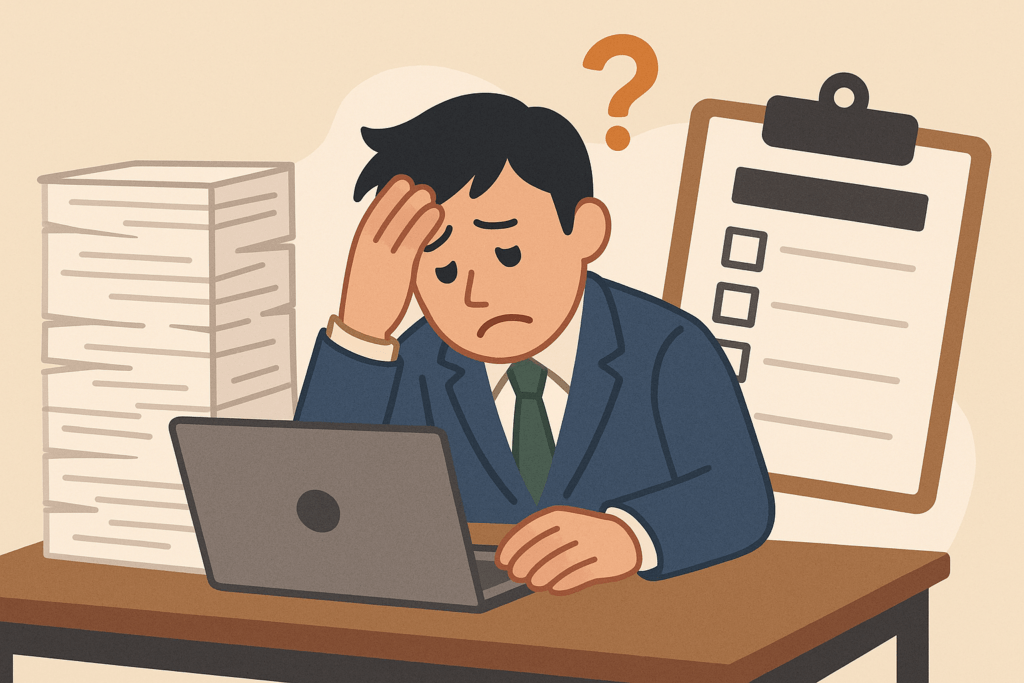 確定申告という重要な業務が失念され、チェック体制も機能していなかった背景には、人的リソースと業務フローの歪みがあります。
確定申告という重要な業務が失念され、チェック体制も機能していなかった背景には、人的リソースと業務フローの歪みがあります。
地方自治体では、少人数の職員が多岐にわたる業務を一手に担っていることが一般的です。
特に小規模な町村では「1人が担当する範囲が広すぎる」「副担当が存在せず、業務の属人化が進んでいる」といった状況が常態化しています。
今回の川本町のケースも、まさにその典型と言えるでしょう。
担当者が長期休暇に入っている間、誰も確定申告の進捗状況を把握できず、課長や課長補佐もフォローしきれなかったという点に、それが如実に表れています。
仮に担当者が1人ではなく、チーム体制が敷かれていたならば、ここまでの事態には至らなかった可能性が高いと考えます。
「異動文化」と「職務不明瞭」が招く引き継ぎの形骸化
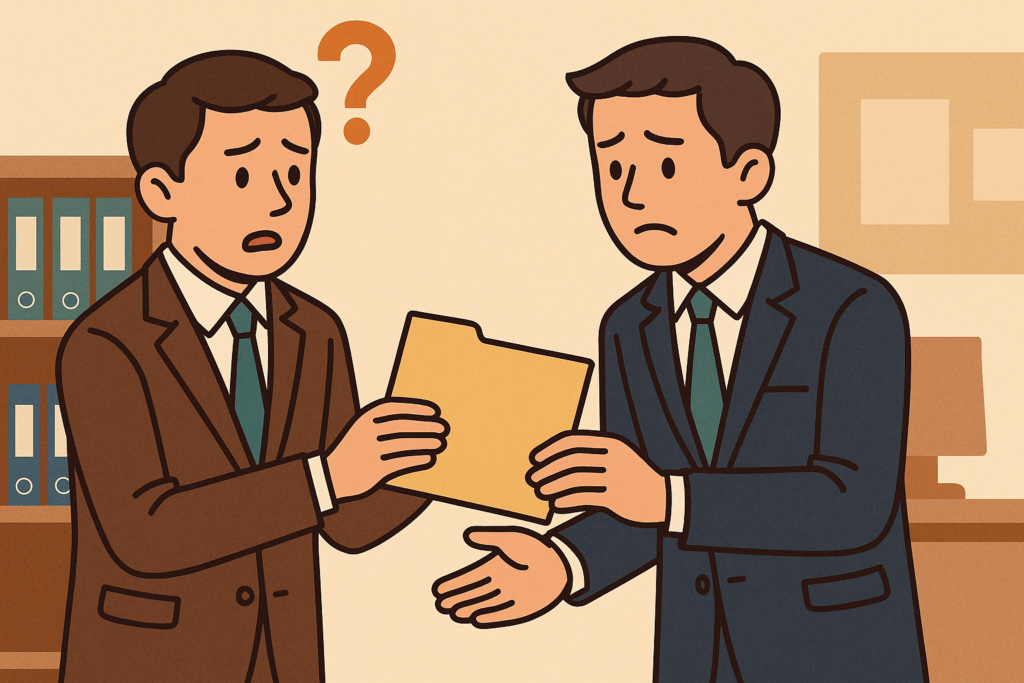 公務員組織では、2~3年単位の異動が一般的で、異なる業務・分野へ次々と配置転換される仕組みがあります。
公務員組織では、2~3年単位の異動が一般的で、異なる業務・分野へ次々と配置転換される仕組みがあります。
この「異動文化」は組織的な視野拡大や公平な人事運用を目的としたものでありながら、現場レベルでは大きな弊害も生んでいます。
実際、「3〜4年で仕事を覚えてきたところで異動」「前任者からの引き継ぎ資料だけを頼りに見様見真似で業務を始める」といった状況は多くの職員が経験する現実です。
さらに、業務マニュアルが整備されていなかったり、属人的な知識で処理していたりする業務も多く、異動者が「何を」「いつ」「どうやって」やればよいのか全く分からないまま業務に就かざるを得ないこともあります。
上司も同様に異動してきたばかりで、その部署の業務に精通していないことも珍しくありません。
その結果、業務の進捗確認やダブルチェックが形骸化し、ミスが発生しても誰も気づけないという事態が起こるのです。
外注化もできない…限られた予算と人材の中で
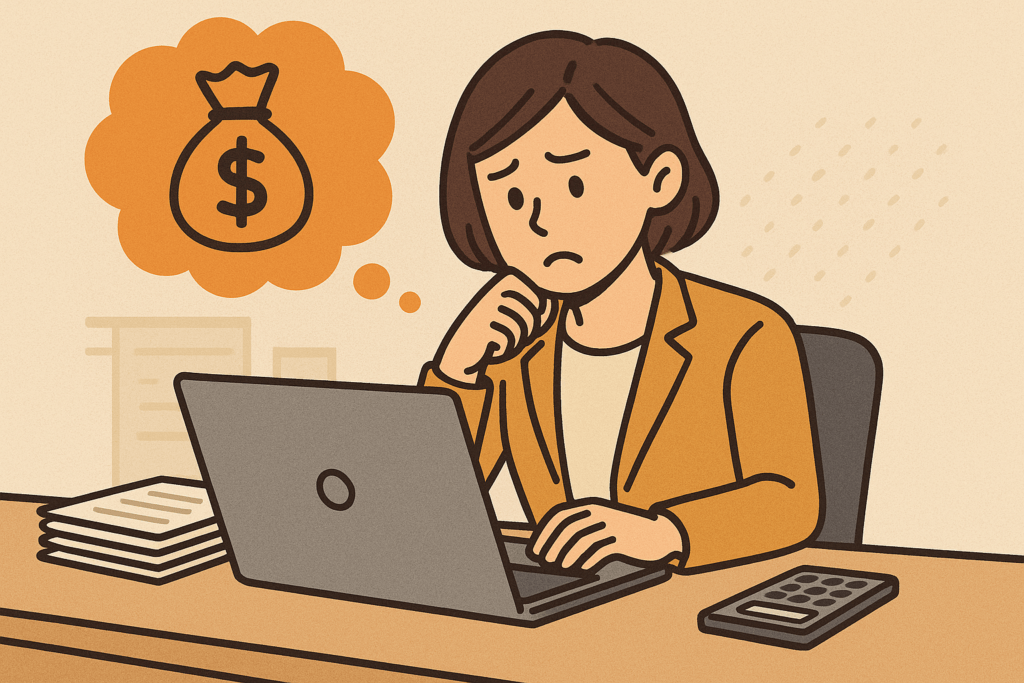 「確定申告を手作業で行っていた」と聞けば、民間企業に勤める人であれば驚かれるかもしれません。
「確定申告を手作業で行っていた」と聞けば、民間企業に勤める人であれば驚かれるかもしれません。
本来ならば専門家への委託や、専用ソフトによる自動化が望ましい業務です。
しかし、現実の自治体業務では、そうしたリソースを確保するだけの予算が組まれていないことも多々あります。
特に水道事業や農業排水処理などは、独立会計で運営されることが多く、予算の柔軟な運用が難しい分野でもあります。
「必要性は分かっていても、外注にかけられる予算がない」という判断が先に立ち、結果として“人力”に頼らざるを得ない状況になっているように感じます。
このような状況では、業務ミスを「怠慢」や「職員の質」に還元して語ることは危険です。むしろ、体制としての限界にメスを入れる必要があります。
公務員組織に求められる「仕組み」重視の発想
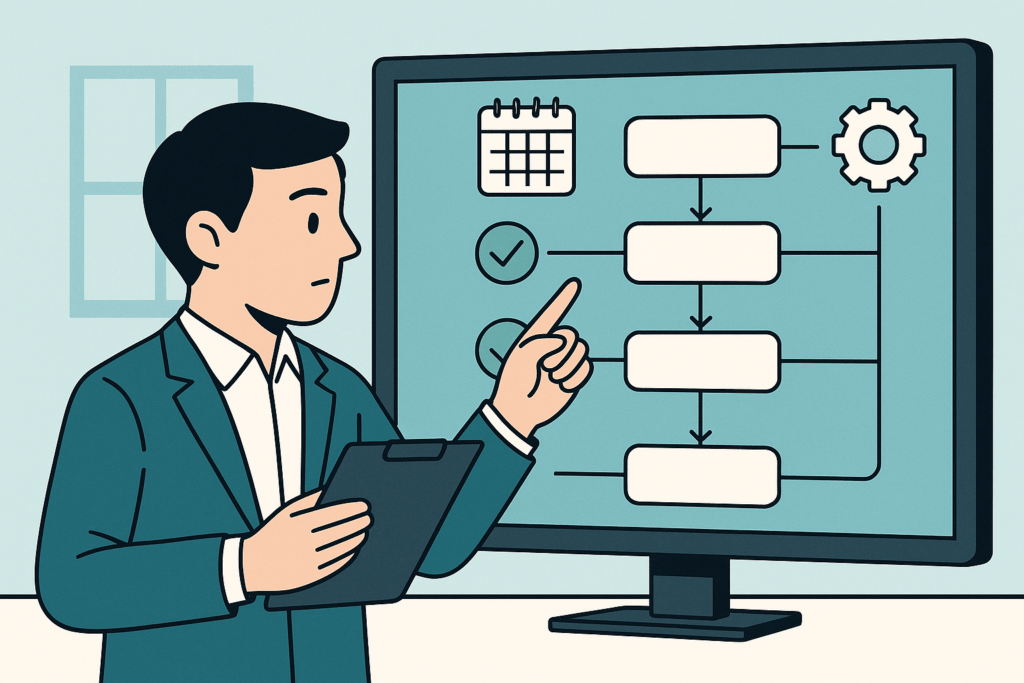 今回のようなヒューマンエラーを防ぐためには、「誰がやってもミスしない」業務フローの構築が不可欠です。
今回のようなヒューマンエラーを防ぐためには、「誰がやってもミスしない」業務フローの構築が不可欠です。
つまり、担当者の能力に依存するのではなく、システム的・組織的に抜け漏れを防げる仕組みを整えることが必要だと感じます。
たとえば、
- 年間スケジュールの共有化と見える化
- タスク管理ツールやチェックリストの導入
- 異動時の引き継ぎマニュアルの標準化
- 「副担当制度」や「タスク共有会」の導入
といった施策が現実的かつ有効です。
また、職員研修も単なる座学ではなく、「どのように業務を引き継ぐか」「異動後すぐにキャッチアップするにはどうすべきか」といった、実務に直結したテーマを扱うことが効果的です。
人を責めるより、仕組みを見直す視点を
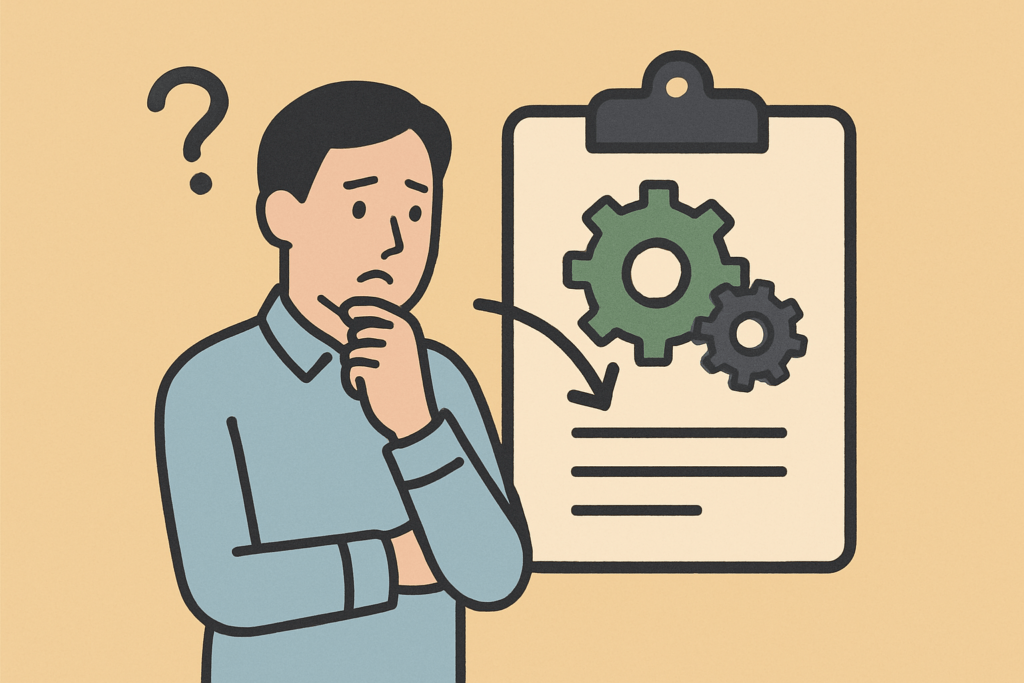 ミスをした職員への処分が公表されると、「公務員は甘い」「責任感がない」といった批判が噴出しがちです。
ミスをした職員への処分が公表されると、「公務員は甘い」「責任感がない」といった批判が噴出しがちです。
しかし、今回の事例を見る限り、問題の本質は個人ではなく組織の設計ミスにあると感じます。
現場は限られた人員と時間の中で、制度改正や事務移管、複雑化する住民ニーズに対応しながら業務を進めています。
そうした背景に目を向けなければ、同様の問題は形を変えて繰り返されるでしょう。
今後、公務員を志す方や現場で働く職員にとっては、「自分の能力」以上に「組織のしくみ」に関心を持つことが求められる時代になっていると実感します。
行政の信頼を守るためにも、「人ではなく仕組みで支える自治体運営」への転換が、今こそ必要ではないでしょうか?