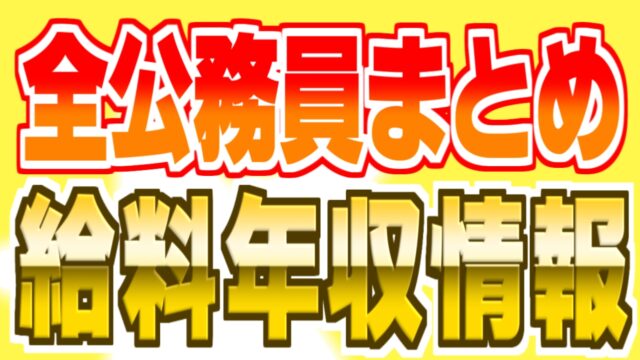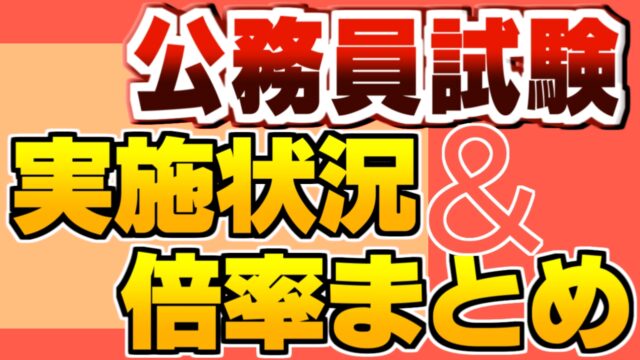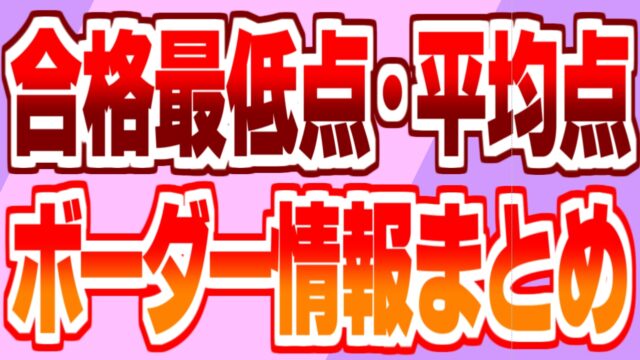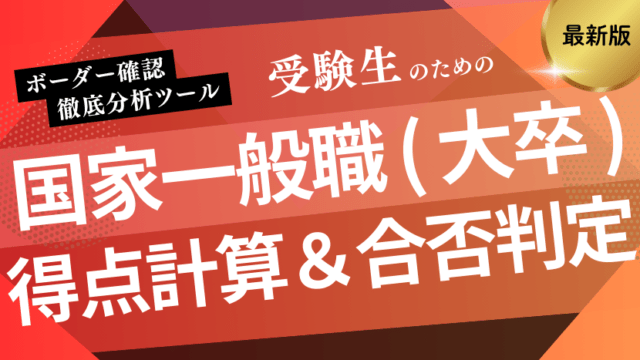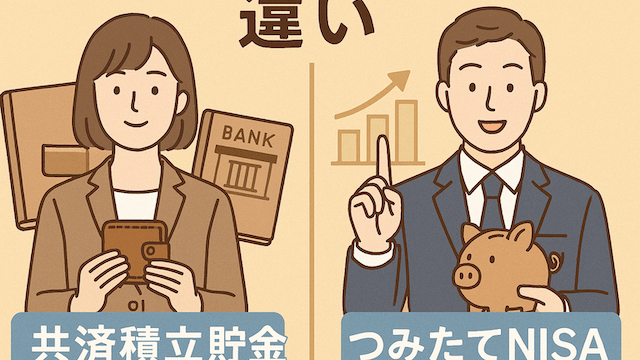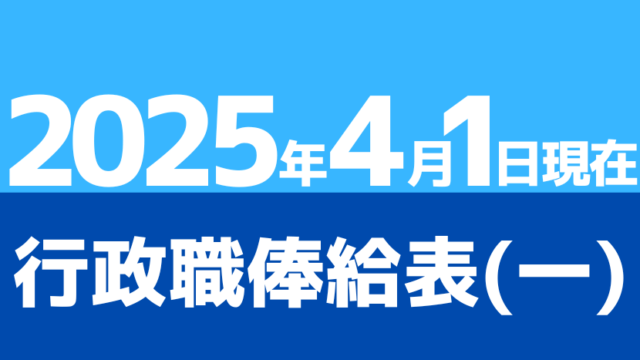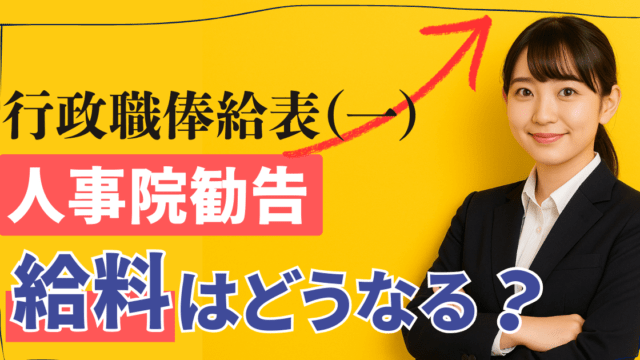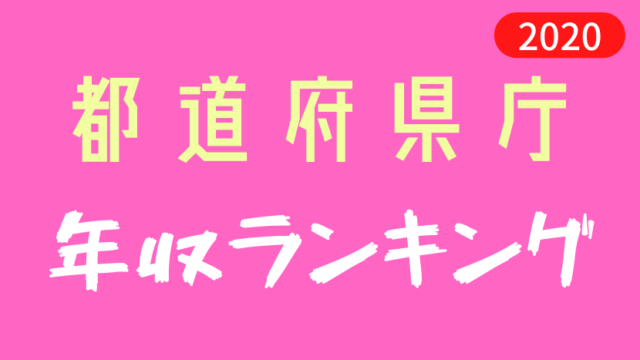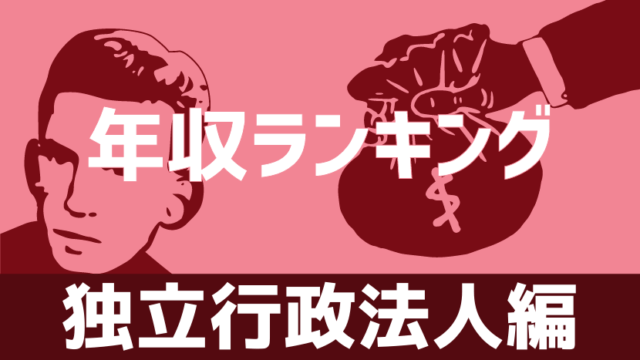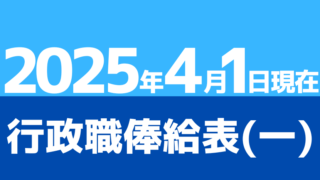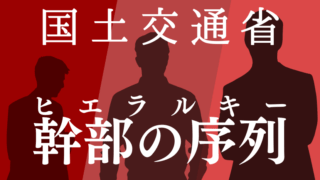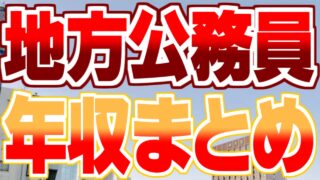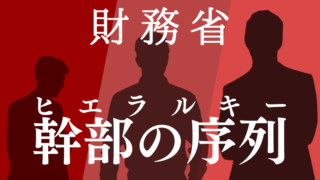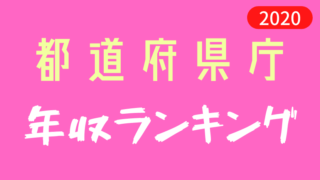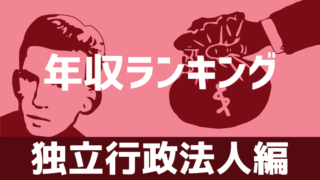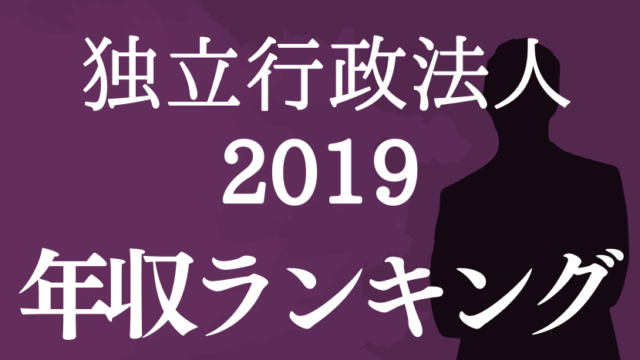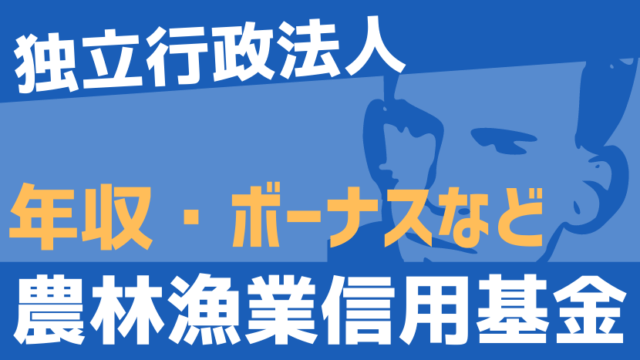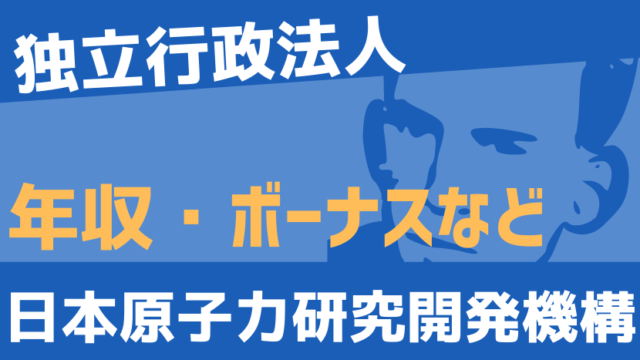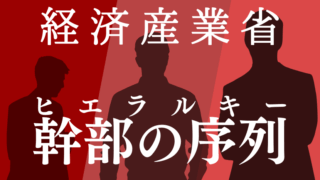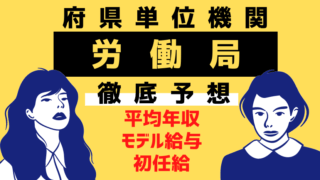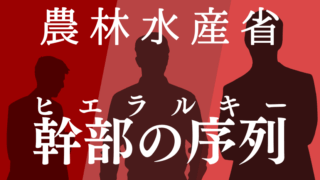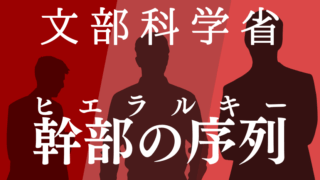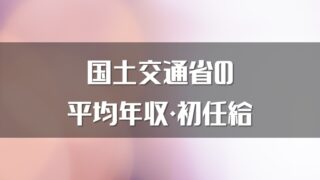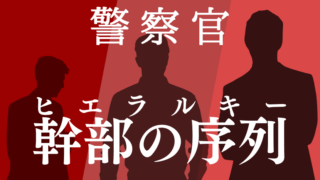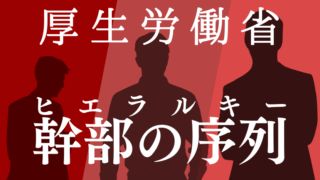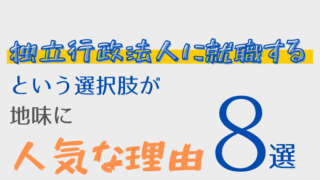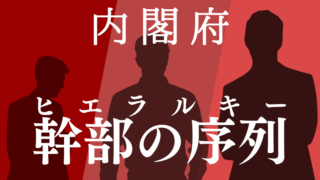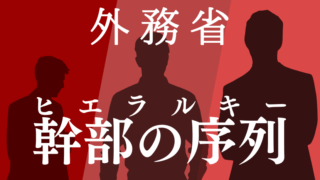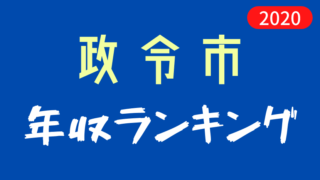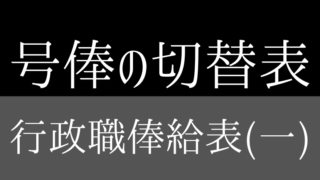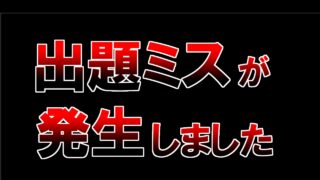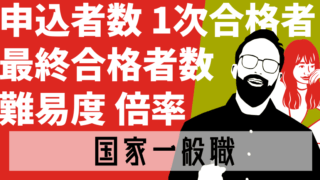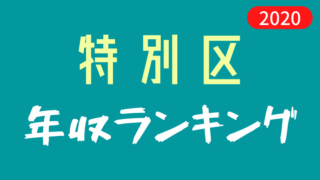目次
就活生の皆さんは、「安定した収入・地位」「充実したワークライフバランス」を求めて大企業や公務員を目指すことが多いでしょう。
しかし、大企業は競争が激しく、公務員になるには難関の試験勉強が必要です。そこで近年注目されているのが、独立行政法人(略して独法)への就職です。
独立行政法人とは、国が直接は行わないが民間では担いにくい公益事業を行うために設立された組織で、「準公務員」「みなし公務員」とも呼ばれる、公務員と民間企業の中間的な存在です。
職員は法律上は公務員ではなく労働基準法が適用されるなど公務員との違いもあります。
それでも独法への就職は、安定志向の学生を中心に地味に人気となっています。その理由を以下に8つ紹介します。
理由その1.給与水準が高く待遇が安定している
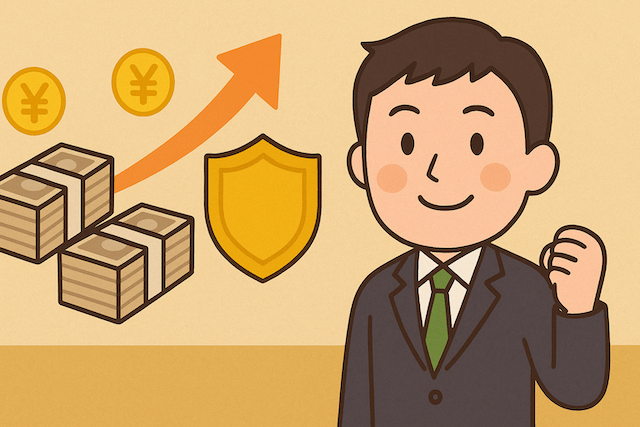
独立行政法人の給与水準は概ね国家公務員に準じており、若手のうちから比較的高めです。
30歳で年収500万円、40歳で600万円程度が一般的と言われ、リストラもほぼ「99.9%ない」ほど雇用が安定しているとされています。
一部の法人では同年代の公務員を上回る高給与(30歳で600万円、40歳で800万円以上)を得ているケースもあります。
高い給与水準の背景には、独法が扱う事業は民間の参入が難しい特殊分野で競争が少ないことが挙げられます。
競合が少ない分、継続して価値を生み出せるため収益基盤が安定し、その結果として職員の待遇も手厚くできると考えられています。
さらに、公務員と異なり労働基準法の適用で残業代が100%支給される点も魅力です。
公務員は予算制約で一定時間以上の残業代が出ない場合もありますが、独法職員は法律に則り時間外手当が満額支給されるため、サービス残業が少なく適正な待遇が守られています。
理由その2.公務員に近い安定性・福利厚生
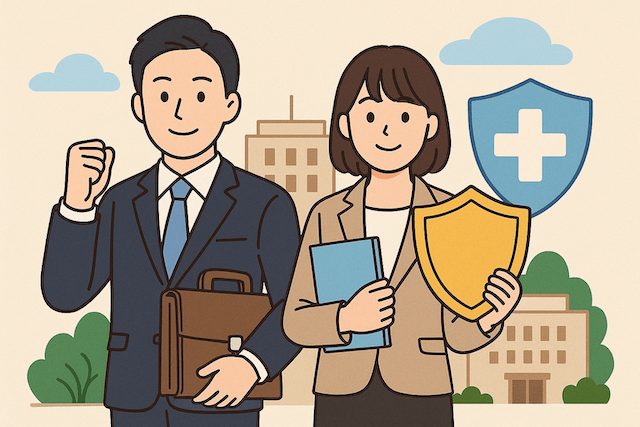
独立行政法人の職員は国家公務員並みの手厚い福利厚生を受けられます。
具体的には通勤手当、時間外勤務手当、住居手当、扶養手当といった諸手当が充実し、通勤手当は月5万5千円まで、住居手当も月2万8千円まで支給される法人が多いです。
休暇制度もほとんどの法人で完全週休二日制が導入され、年次有給休暇や夏季・冬季休暇、特別休暇も取得可能となっています。
初年度有給休暇は15日、翌年度以降は20日付与(未消化分は20日を上限に繰越可)という水準が一般的で、公務員と遜色ない充実ぶりです。
さらに、独法職員は共済組合にも国家公務員共済として加入でき、場合によっては職員宿舎が用意されることもあります。
こうした福利厚生の充実に加え、雇用の安定性も魅力です。
独立行政法人は政府系の機関なので倒産の心配がほとんどなく、景気に左右されにくい安定した身分を得られます。
民間企業のような業績不振による大規模なリストラは現在ほとんどなく、仮に組織再編(統廃合)があっても職員の雇用確保が最優先とされ、統合先の法人や所管省庁への配置転換で対応するのが通常です。
また人事体系は年功序列色が強く、着実に勤め続ければ昇給・昇格していく仕組みになっています。
こうした点は公務員と共通しており、「一つの職場で定年まで腰を据えて働きたい」という人に独法はうってつけの職場と言えるでしょう。
理由その3.ノルマなし・公共性重視で働きやすい
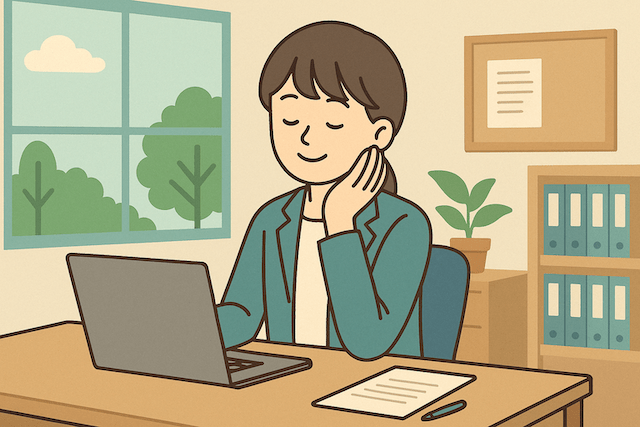
民間企業と比べた場合の独法就職のメリットとして大きいのは、仕事のプレッシャーの少なさです。
多くの独立行政法人職員は営業ではなく事務系ポジションのため、毎月の厳しいノルマ(営業目標)が課されることはありません。
利益追求が主目的ではなく公共の利益のための業務であるため、数字に追われるようなプレッシャーも少なく、職場の雰囲気は全体的にのんびりしています。
実際、「ノルマがないおかげで職場はまったりとしており、日々のワークライフバランスを大切にできる」といった声もあります。
営業成績に追い立てられることがないため、メンタル的な負担が軽く、仕事の質に集中しやすい環境です。
このため都市銀行や証券会社など厳しいノルマに晒されがちな業界から独法へ転職する人も多いと言われます。
また、独法職員には労働基準法が適用される関係で労働環境のチェックもあり、残業代も全額支給されるため「サービス残業」が横行しにくいのも特徴です。
もちろん部署や時期によって残業自体は発生しますが、無償で深夜まで働かされるといったブラックな働き方になりにくく、民間企業より働きやすい職場が多いと考えられます。
仕事の性質上「お客様」に直接対応する機会も少なく(国民全体が相手という広いスケールのため)、対人ストレスが少ないという意見もあります。
総じて、独立行政法人は公共性重視の穏やかな職場風土であり、「激しい競争よりも安定した環境で落ち着いて働きたい」という就活生にとって魅力的な選択肢でしょう。
理由その4.全国転勤が少なくライフスタイルを維持しやすい
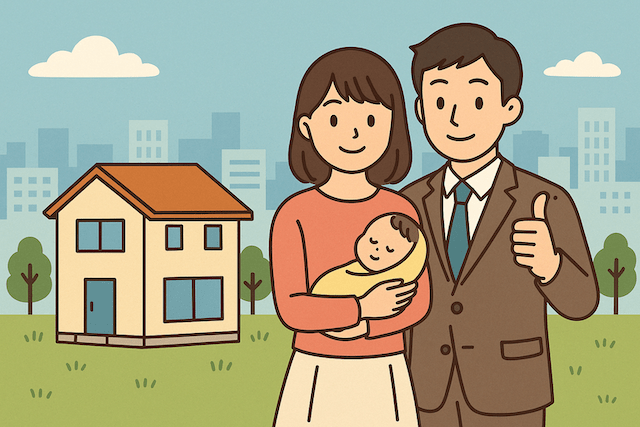
「転勤の有無」はキャリア選択の大きなポイントです。
全国規模で転勤の可能性がある企業や官庁だと、将来ライフスタイルが大きく変わる可能性があります。
その点、多くの独立行政法人は全国転勤がないか、あっても少ない傾向にあります。
法人によっては本部と支部が複数存在する場合もありますが、民間の総合職ほど頻繁に勤務地が変わることはありません。
むしろ採用段階から「全国転勤なし・勤務地1か所のみ」と明記している独法も多く、地域限定で腰を落ち着けて働けます。
このため、結婚や子育て、自身や家族の生活拠点を重視したい人にとって独法は魅力的です。
転居をともなう異動がほとんどなく、地域に根差した働き方ができるので、長期的なライフプランを立てやすいでしょう。
もちろん一部には全国展開の独法もありますが、それでも民間大手ほど転勤リスクは高くなく、ワークライフバランス志向の就活生には安心できる職場選びとなっています。
理由その5.採用は公務員試験なしで応募しやすく、倍率も程々
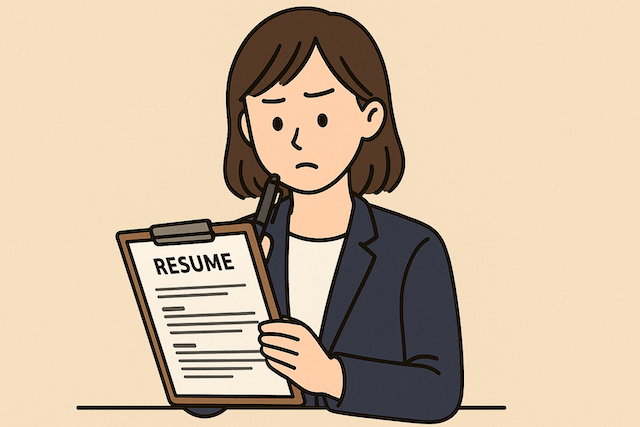
独立行政法人の採用試験は公務員採用試験とは別枠で行われます。
国家一般職・総合職などのような統一試験を受ける必要はなく、各法人ごとに個別の採用活動を行っているのが特徴です。
したがって独法の職員になるために公務員試験を受ける必要はありません。
新卒の場合、マイナビやリクナビなど就職サイトに求人が掲載されるため、民間企業と同じようにエントリーシートを提出し、グループディスカッションやSPI試験、そして複数回の面接を経て内定を得る流れになります。
このように、公務員志望者が避けて通れない筆記試験対策が不要なので、大学在学中に長期間勉強時間を割く必要がありません。
その分、サークル活動やアルバイト、インターンなど学生生活の経験を積みつつ就活に臨める利点があります。
では採用難易度(倍率)はどれくらいかという点ですが、一概には言えないものの法人によって幅があります。
人気の独法では応募者もそれなりに多く、高倍率になるケースもあります。例えば住宅都市整備を行う「UR都市機構(都市再生機構)」では、毎年の採用人数が80名程度に対し推定採用倍率50倍前後とも言われることもあり、決して簡単に入れるわけではありません。
また宇宙研究で人気の高いJAXAや、国際協力を担うJICAなども志望者が多く難関です。一方で知名度の低い独法は応募者数自体が少なく、就活の穴場的な存在になっている場合もあります)。
企業名として派手さはなくとも平均年収が高かったりする独法もあり、こうした狙い目の法人を探すことで採用競争を勝ち抜ける可能性も高まります。
総じて、公務員試験組とは別ルートで挑戦できる独立行政法人は、就活生にとって選択肢を広げるチャンスとなっているのです。
理由その6.社会貢献度が高く専門性の高い仕事に携われるやりがい
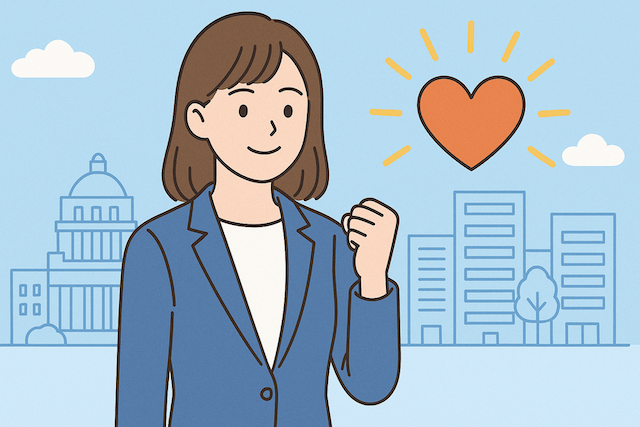
独立行政法人で働くことのやりがいとして、多くの職員が口にするのが「社会に役立っている実感」です。
独法の業務は国民生活の安定や社会・経済の発展に直接関わる公共性の高い仕事であり、世の中をより良くする使命を帯びています。
民間企業のようにひたすら利益を追求するのではなく、国の政策の一端を担い社会貢献度の高い仕事に携われるため、日々の業務の先に国民の生活向上という目に見える成果を感じることができます。
例えば環境保全や医療・福祉、教育や文化振興など、独法ごとに扱うテーマは異なりますが、そのどれもが国民にとって必要不可欠な分野です。
自分の携わるプロジェクトが社会の課題解決や暮らしの質向上に繋がっていると実感できることは、大きなモチベーションとなるでしょう。
さらに、独立行政法人の職場では若いうちから専門性の高い仕事を任せてもらえる傾向があります。
各法人はそれぞれ特定のミッション・事業領域を持っており、職員はその分野で専門知識やスキルを深めていくことになります。
金融、環境、医療、人材育成、文化振興、研究開発など、法人ごとに扱う業務は多岐にわたりますが、担当分野に特化したスペシャリストとして経験を積めるのが魅力です。
これは公務員でよくあるジョブローテーション(部署異動)とは対照的で、独法では基本的に一貫したキャリア形成が可能です。
特定領域のプロとして専門能力を高めつつ、国の政策実行にも貢献できるため、大きなスケールの仕事に挑戦する醍醐味を若手から味わえるでしょう。
このように、社会のためになる実感と自身の専門スキル向上の両方が得られる点が、独立行政法人で働く大きなやりがいとなっています。
理由その7.多様な独立行政法人が存在し、自分に合った分野を選べる
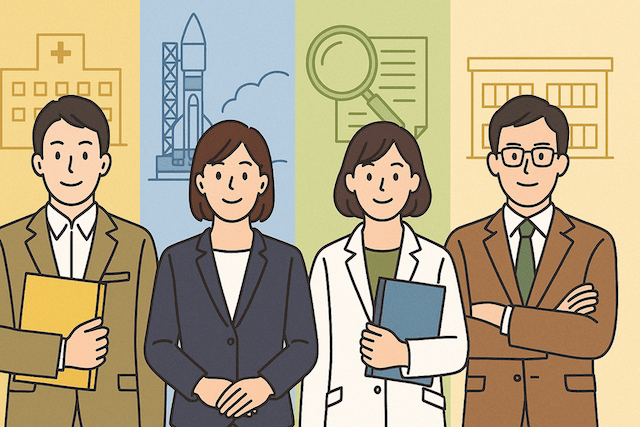
一口に独立行政法人と言っても、その分野や業務内容は実に様々です。
「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」のように宇宙開発・研究を行う法人もあれば、「製品評価技術基盤機構(NITE)」のように工業製品の安全評価や技術基盤整備を担う法人もあります。
また、全国の国立病院を統括する「国立病院機構」や、雇用支援を行う「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のように福祉・医療分野に関わる法人もあります。
以下に代表的な独立行政法人の例をいくつか挙げます。
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構(厚生労働省所管) – 高齢者や障害者の雇用支援、職業能力開発支援を行う。全国各地に職業能力開発校や障害者職業センターを設置し、誰もが働きやすい社会づくりに寄与している。
- 国立病院機構(厚生労働省所管) – 全国に140以上の病院を運営する日本最大級の医療ネットワーク。地域医療の中核として高度な医療サービスを提供し、医療人材の育成にも貢献している。
- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)(文部科学省所管の国立研究開発法人) – 日本の宇宙開発を担う機関。ロケット打ち上げや人工衛星の開発運用、国際宇宙ステーション計画への参加など最先端の研究開発プロジェクトを推進している。
- 製品評価技術基盤機構(NITE)(経済産業省所管) – 工業製品の安全性評価や認証、バイオテクノロジーや計量標準の整備などを行う技術系の法人。消費者が安全・安心に製品を利用できるよう技術的基盤を提供している。
このように、独法には多彩なジャンルの法人が存在し、自分の興味・関心のあるフィールドで社会貢献することが可能です。
研究開発型の法人から、文化・教育・国際協力を担う法人、現業的なインフラ整備を担う法人まで、その数は87にのぼります。
就活生にとって、「民間か公務員か」だけでなく「第三の選択肢」として独法を検討する際、自分の専門や志向に合った法人を選べるというのも人気の理由の一つでしょう。
たとえば理系で研究志向の学生ならJAXAや産業技術総合研究所などが視野に入りますし、国際派の人はJETRO(日本貿易振興機構)やJICA(国際協力機構)などが候補になります。
安定を求めつつ自分のやりたい仕事にも携われる場が見つかる点で、独立行政法人の多様性は就職先として大きな魅力です。
理由その8.日本年金機構への就職も安定志向の学生に人気
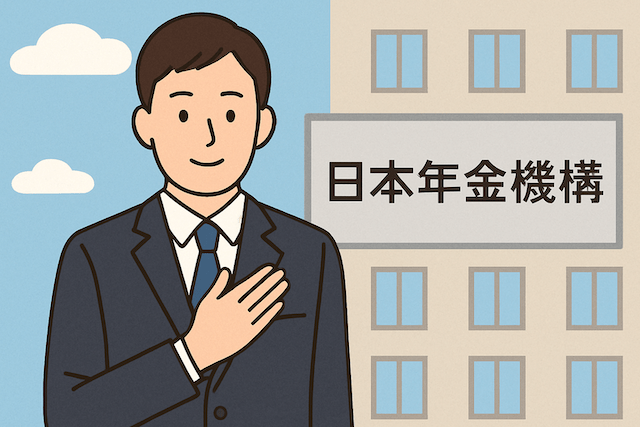
最後に、厳密には独立行政法人ではないものの、同様の安定した就職先としてぜひ紹介しておきたいのが「日本年金機構」です。
日本年金機構は厚生労働省所管の特殊法人で、公的年金の運営を担っています。
法律上は独法とは異なる区分ですが、その性質や働き方は独法職員に近く、就活生からも安定志向の職場として人気があります。
実際、日本年金機構の職員待遇は独法と同様に国家公務員に準じており、平均年収は600〜700万円台と高水準で、全国転勤についても、生活の基盤を置く都道府県(本拠地)を設定し、異動は本人の意向や適性を踏まえて本拠地にある年金事務所を中心に行われます。
採用人数も毎年一定数(50名以上)あり、新卒者に門戸が開かれています。公的年金という社会インフラを支える使命感と、安定した労働環境を両立できることから、「独法ではないけれど第2の独法的な就職先」としてしばしば名前が挙がります。
実際、独法を志望している就活生が併願先として年金機構を受けるケースも多いようです。
日本年金機構は全国各地の年金事務所での勤務が基本で、地域に根差して人々の生活を支える仕事ができます。
給与や福利厚生も先述の通り安定しているため、将来にわたって腰を据えて働きたい人には魅力的でしょう。
独立行政法人への就職を検討するなら、この日本年金機構も視野に入れてみることをおすすめします。
まとめ
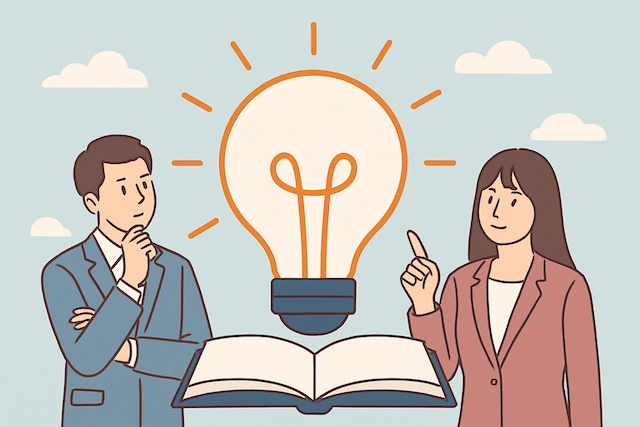
以上、独立行政法人に就職するメリットを8つ挙げてきました。
ノルマがなく、そこそこ高い給料と安定した身分で定年まで働ける――これらは就活生にとって非常に大きな魅力であり、独法が“隠れた人気”となっている理由です。
さらに社会への貢献実感や専門スキルを積める点も、独法就職が注目される背景にあります。
まさに大企業と公務員の「いいとこ取り」とも言える独立行政法人ですが、もちろん全ての法人が画一的に恵まれているわけではありません。
法人ごとに業務内容や待遇には差があり、中には期待ほどではない職場も存在します。
そのため、「思っていたのと違う…」とミスマッチを防ぐためにも、志望する法人の情報をしっかり集めておくことが大切です。
各独法の公式採用ページや職員の声、内定者の体験談などをチェックし、自分に合った職場か見極めましょう。
独立行政法人への就職は、公務員試験組とは異なるルートで安定したキャリアを築ける狙い目の選択肢です。大企業一本に絞らず視野を広げることで、自分にとってベストな就職先が見つかるかもしれません。安定とやりがいを両立できるフィールドとして、独法や日本年金機構といった選択肢もぜひ検討してみてください。きっとあなたの将来設計にマッチする職場が見つかることでしょう。