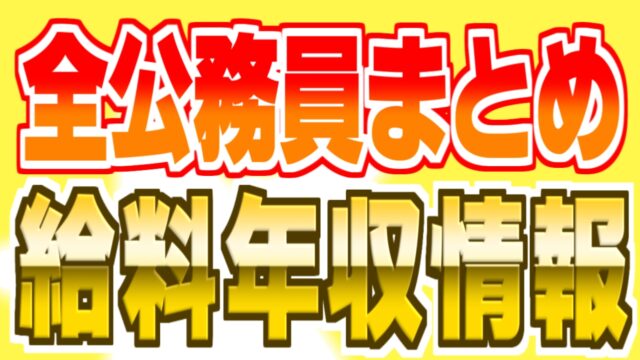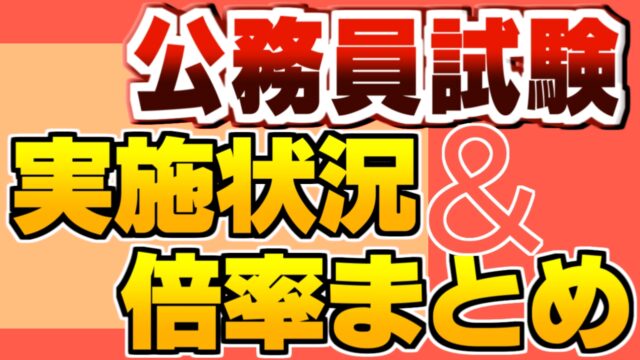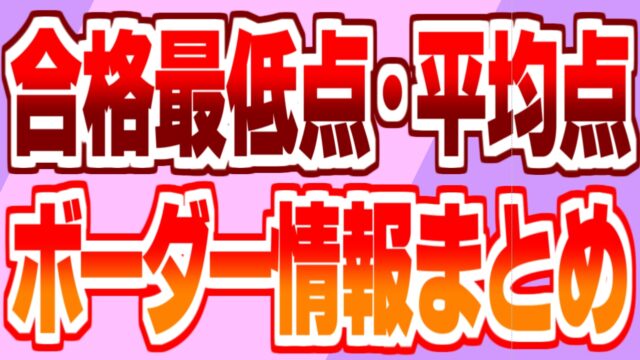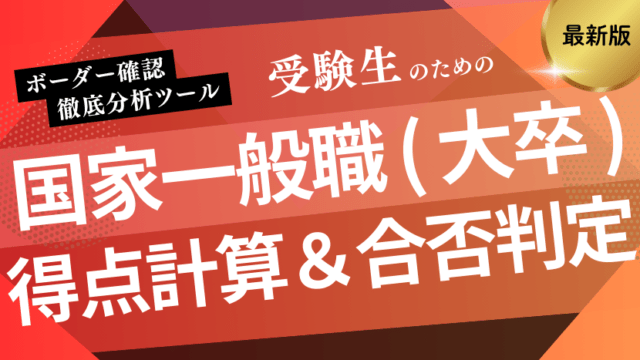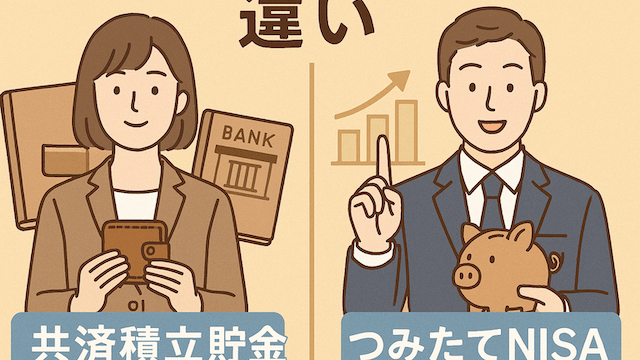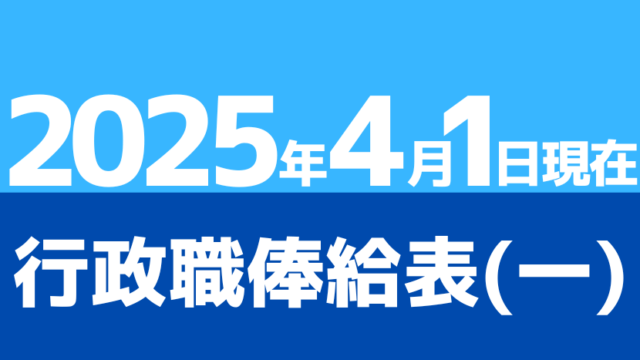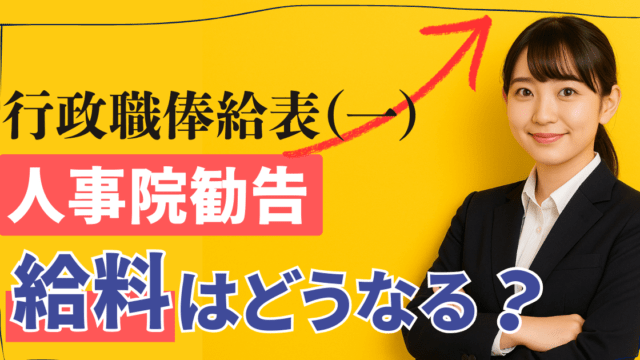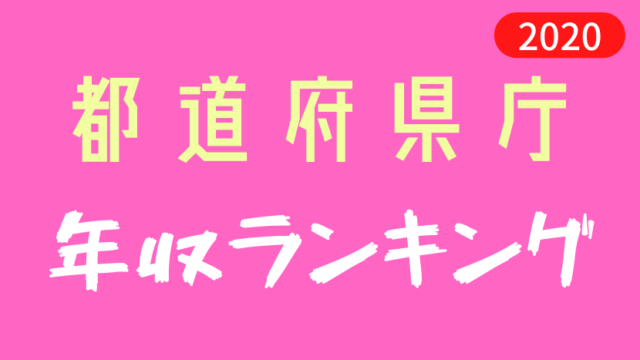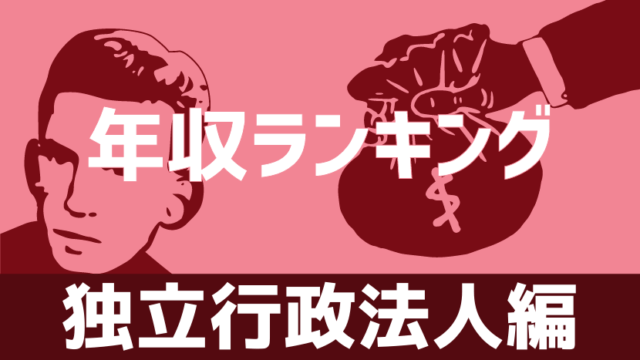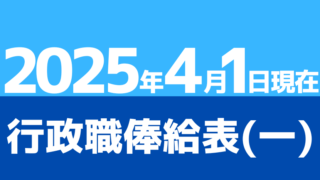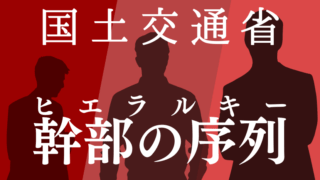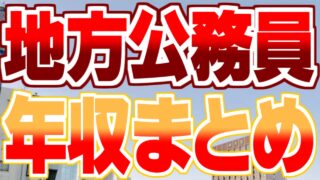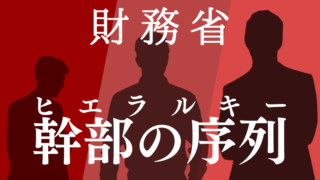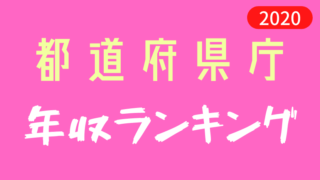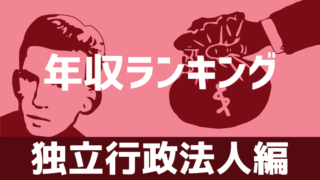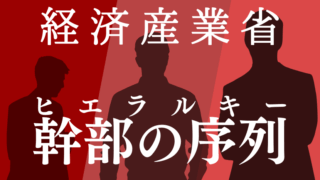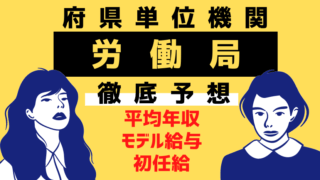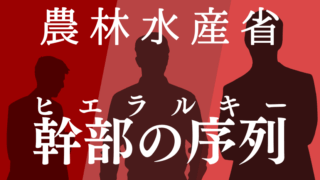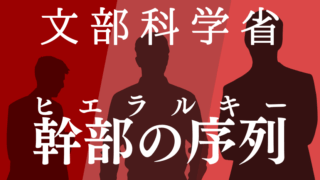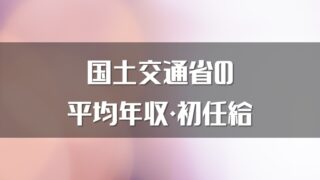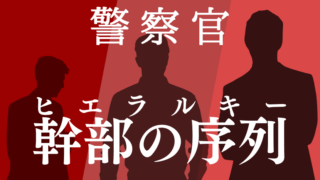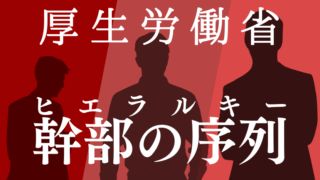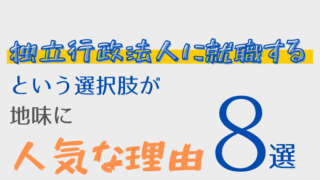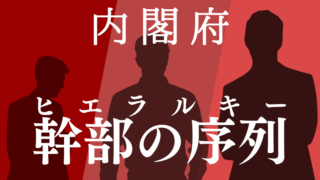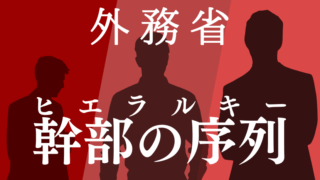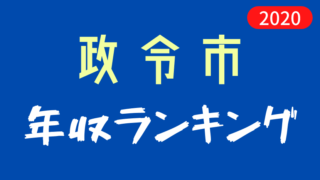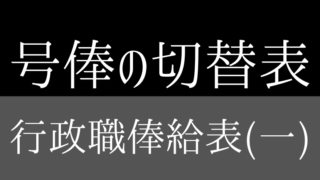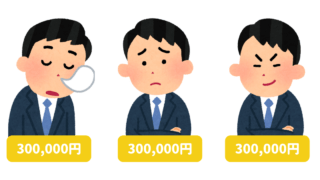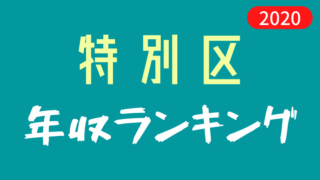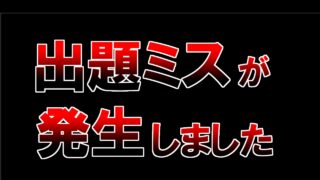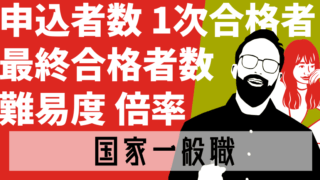目次
2025年末から2026年始めにかけて、公務員は年末年始休暇として何日休めるのでしょうか。
国家公務員・地方公務員を問わず共通する法律上の規定や、具体的な日程、職場ごとの運用例について詳しく説明します。
さらに学校職員(教員)の冬休みや、民間企業・他業界の正月休みとの違いについても比較し、公務員の休暇事情をわかりやすく解説します。
公務員の年末年始休暇は法律で6日間と定められている
公務員(国の行政機関や地方公共団体職員)の年末年始休暇は、行政機関の休日に関する法律によって毎年固定で12月29日から翌年1月3日までの6日間と定められています。
この期間は官公庁は業務を行わない正式な休日となり、国家公務員・地方公務員いずれも基本的に共通です(地方自治体でも同様の規則で閉庁日が定められています)。
つまり、公務員の年末年始の休み日数は法律上6日間ということになります。
ただし実際には、この前後に土日祝日が重なることで連休が延びるケースが多く、年によって休暇期間は変動します。
年末年始休暇6日間はあくまで最短の日数で、暦の並びによっては9連休前後になる年もあります。
公務員の年末年始休暇は毎年同じ日付ですが、週末との組み合わせ次第で長さが大きく変わる点がポイントです。
2025年~2026年の年末年始休暇の日程(9連休)
2025~2026年の年末年始休暇は暦の並びが公務員にとって好条件となり、実質9連休になります。具体的な日程を見てみましょう。
仕事納め(年内最終登庁日):2025年12月26日(金)
※12月27日(土)と28日(日)は通常の週末休み
年末年始休暇(行政機関閉庁期間):2025年12月29日(月)から2026年1月3日(土)まで
※この6日間が法律で定められた公務員の年末年始休日です。
週末休(年始):2026年1月4日(日)
※年末年始休暇最終日の翌日が日曜日のため、この日も引き続き休日となります。
仕事始め(年明け初出勤日):2026年1月5日(月)
上記のように2025年は12月29日(月)から休みに入るため、その直前の週末と繋げて2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)の9日間が連続した休みとなります。
これは公務員の年末年始休暇としては最大級の長さで、普段より長い冬休みになるでしょう。
今年(2025年)のように土日と繋がる年は長期連休となり、一方で暦の並びによっては6日間程度(例えば年末年始期間の前後に平日が挟まる場合)は最小限の連休となります。
仕事納め(御用納め)について補足すると、公務員の場合は毎年12月28日頃までに年内の業務を終了し、最後の勤務日に「仕事納めの式」や職場の大掃除が行われる慣例があります。2025年は12月29日が法律上の休日のため、12月26日(金)が実質的な仕事納めとなり、多くの職場で年内最終日のセレモニーや挨拶がこの日に行われるでしょう。
反対に仕事始め(御用始め)は毎年1月4日頃ですが、2026年は1月4日が日曜日のため1月5日(月)が公務員の仕事始めとなります。
年末年始休暇との組み合わせ
公務員は年末年始休暇中は基本的に全員休みで、通常業務は停止します。
危機管理や緊急対応が必要な部署を除き、行政職など大多数の公務員はこの期間に出勤することはありません。
一部の自治体では、防災担当職員などが交代で待機当番(いわゆる日直)につき、災害対応など非常時に備えるケースがありますが、一般の事務系職員は年末年始はしっかり休める職場がほとんどです。
有給休暇との組み合わせについても見てみましょう。
公務員は年間20日の年次有給休暇が付与されますが、忙しさなどから平均取得日数は年間10日程度と消化しきれないケースが多いのが現状です。
そのため各職場では、「せっかくの連休だから前後に1~2日有休を足して長めの休みにしよう」という風潮もあります。
特に年末年始は他の時期に比べて業務予定が少なく(年内の業務は仕事納めまでに一段落していることが多いため)、有休を取りやすい時期でもあります。
具体的な休暇取得例として、2025年の場合を考えてみます。
公式には12月26日(金)まで勤務がありますが、職員によっては12月26日を有給休暇に充てて12月25日(木)までに仕事を納め、年末年始休暇に前倒しで入る人もいるでしょう。
こうすると12月26日から休暇となり、実質10連休(12月26日~1月4日)を確保できます。
また逆に、年始の1月5日(月)を有給取得して休みを延長し、ゆっくり休養を取る人もいるかもしれません。
もっとも、年末年始休暇前後の有休取得は各職場の業務状況によりますので、部署によっては難しい場合もあります。
それでも「年末年始休暇+有給」で長期休みにすること自体は可能であり、むしろ計画的な有休消化が推奨される傾向にあります。
なお、公務員の年末最後の勤務日には年末調整(所得税の年末調整事務)や翌年予算準備など事務処理が立て込みますが、これらは通常12月中旬までに完了するため、年末休暇直前は比較的余裕が生まれる時期です。
各種締め処理を終えた安心感もあって、年末年始休暇は公務員にとって一年の中でも取りやすい大型休暇と言えるでしょう。
地方自治体や職場ごとの違い
法律で定められた年末年始休暇は全国共通ですが、細かな運用は自治体や職場によって多少異なる場合があります。
例えば「年末閉庁日」という言い方で各自治体が住民向けに案内を出すことがあります。
多くの市区町村では「年末は○月○日まで開庁、翌○月○日より開庁」といった形で広報され、基本的にその閉庁期間が12月29日~1月3日にあたります。
しかし、暦によっては実質的な業務最終日が前倒しになることがあります。
2025年の場合、自治体の窓口業務は12月26日(金)までとなり、12月27日以降は閉庁となります。
土日が絡むため公式の「閉庁期間」は12月29日~1月3日ですが、住民サービスの観点では12月27日(土)から窓口がお休みに入る形です。
このように最終開庁日が平日より前倒しになるケースでは、自治体によって周知の仕方が異なります。
例えば「年内の業務は○月○日まで」といった告知や、必要に応じて28日(月)を臨時休業にして職員の計画休暇取得日とする自治体もあります(※一般的ではありませんが、一部自治体では独自に12月28日を閉庁日と定めることもあります)。
もっとも、法律で定められた範囲以外に公務員の休暇日を増やすには条例や規則が必要になるため、大半の役所では暦通りに休暇を運用しています。
したがって職場ごとの差は、「仕事納め式の有無」「最終日の午後は早帰りが認められるか」「交替制職場の当番体制」など運用面での違いが中心でしょう。
行政サービス上は全国ほぼ一律に年末年始休業となるため、公務員本人だけでなく国民にも浸透した休暇期間と言えます。
学校職員(教員)の年末年始休暇はどう違う?
教育公務員である学校職員や教員も、公務員としての身分である以上、基本的には年末年始休暇(12月29日~1月3日)は他の職員と同様に保障されています。
ただし学校の勤務形態や学校行事の都合上、一般の官公庁職員とは少し事情が異なります。
まず、生徒の冬休み期間があります。
多くの学校では12月下旬から新年にかけて冬休みとなり、例えば2025年度の場合、終業式が12月25日頃に行われてから新学期の始業式まで学校教育活動は停止します。
生徒が登校しない期間中、教員も授業や生徒対応の必要がなくなります。
そのため学校現場では年末年始休暇より前から休みの雰囲気になりますが、教員は公務員として12月29日~1月3日以外の平日は本来勤務日です。
部活動の指導や研修、事務作業などで12月26日~28日や1月4日~6日あたりに出勤する教職員も例年います。
しかし近年は、教員の長時間労働是正の観点から「学校閉庁日」を設定する教育委員会が増えてきました。
学校閉庁日とは、学校管理下で教職員も含め校内を完全閉鎖し、生徒も教員も原則立ち入らない日を指します。
多くの自治体では夏休み・冬休み期間中の一部を学校閉庁日としており、年末年始では12月29日~1月3日の公的休暇に加え、その前後の平日も閉庁日とするケースがあります。
例えばある自治体では12月25日~1月5日を学校閉庁期間と定め、教員も一斉に休暇取得を促す取り組みをしています。
このように学校現場では、生徒の休みに合わせて教職員もまとまった休みを取りやすくする運用が行われています。
まとめると、教員の年末年始休暇は形式上は他の公務員と同じく6日間ですが、実態としては生徒の冬休みに準じて前後も含め休める場合が多いと言えます。
ただし部活動の大会引率や学校行事の準備などで出勤が必要なケースもあり、学校ごとに事情は異なります。
一般の官公庁勤務公務員より柔軟な反面、公務員の中でも職務都合で休暇が前後することがある点が教員の特徴です。
民間企業や他業界の年末年始休暇との比較
公務員の年末年始休暇がカレンダー通り確保されるのに対し、民間企業や他の業界では休暇日数やスケジュールが企業ごと・業種ごとに異なります。
ここでは公務員と民間等の違いをいくつか比較してみましょう。
官公庁(公務員)
12月29日~1月3日(6日間)が法定の休日期間。土日とつながる年は最大9連休程度になります。基本的にこの期間は全国一律で役所は閉庁します。
一般企業(民間)
法定の定めはありませんが、多くの企業は官公庁と同じく12月29日~1月3日を会社休業日とするところが多いです。したがって民間でも6日程度の年末年始休暇を設ける企業が一般的です。
ただしサービス業や交替制勤務の職場ではこの限りでなく、休業日は各社の就業規則によります。
金融機関(銀行など)
銀行は銀行法により12月31日~1月3日がお休みと法律で定められており、これに土日が重なる形で年末年始の休業日が決まります。
2025-2026年の場合、銀行は12月31日(水)~1月4日(日)の5連休となります。証
券取引所も大発会(年明け最初の取引開始日)が1月4日以降となるなど、金融業界は官公庁よりやや短めの休暇です。
医療機関(病院など)
医療分野には全国一律の休業規定はありませんが、多くの病院は年末年始は官公庁に準じた期間を休診としています。
その場合、公立私立を問わず12月29日~1月3日(土日含め最大9日程度)の休みとなる病院が多いです。
とはいえ急病人への対応が必要なため、休日救急の当番医制度や救急外来はこの期間中も機能しています。
小売・サービス業
デパートやスーパー、コンビニなど小売業は年末年始も営業するところが多く、一律の休みはありません。
例えば小売店では元日(1月1日)のみ休業、あるいは年中無休で営業するケースもあります。サービス業(娯楽施設、交通機関、宿泊業など)でも繁忙期となる業態が多いため、公務員のような長期休暇とは無縁の職場も少なくありません。
反対に製造業などでは年末年始に工場稼働を止め、1~2週間の長期休暇とする企業もあり、業種ごとの差が大きいのが民間の特徴です。
このように、公務員の年末年始休暇は「公務員だから特別に長い」というより、法律で保障された最低限の休息と位置付けられます。
他業界でも同程度の休みを確保するところは多いものの、それ以上に休めるかどうかは企業次第です。
反面、サービスインフラを担う業界では休みが短かったり交代勤務で対応したりと、公務員より厳しい勤務形態も見られます。
まとめ:公務員の年末年始休暇はしっかり休める貴重な期間
2025年~2026年の年末年始休暇は公務員にとって9連休と長期の休みになります。
法律で定められた6日間の休暇に土日が重なり、例年になく長い正月休みとなるため、この機会にしっかり英気を養うことができるでしょう。
年末の仕事納めを無事終えたら、公務員は心置きなく正月休みに入ることができます。
現役公務員の皆さんにとって、年末年始休暇は年度末や新年度の繁忙期に備える充電期間でもあります。
しっかり休むことは大切ですが、長期休暇明けの仕事始めにスムーズに業務再開できるよう、休みの後半には生活リズムを整えることも心がけましょう。
また、公務員は有給休暇も活用しやすい環境にあります。この年末年始に有休を組み合わせることでさらに長く休める場合は、勇気を持って取得してみるのも一案です。
休暇制度を上手に活用し、充実した年末年始を過ごしてください。