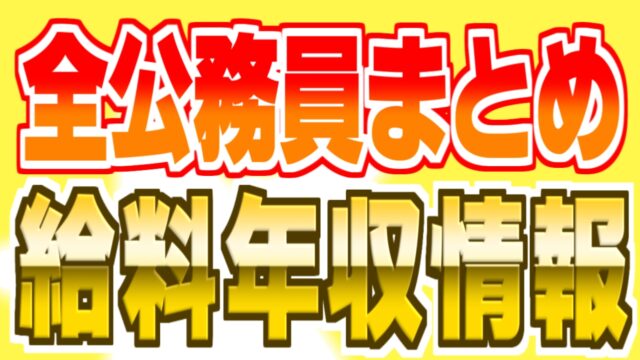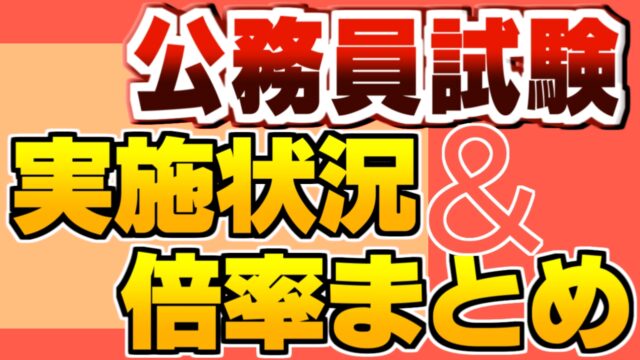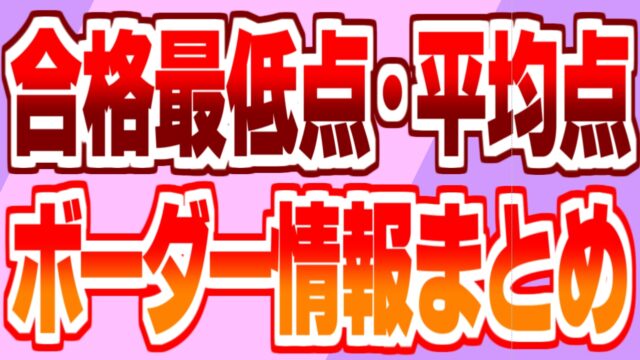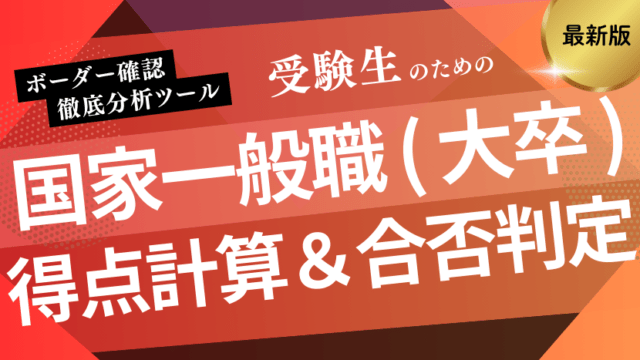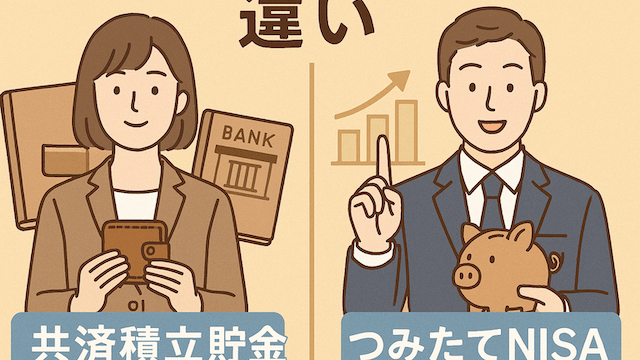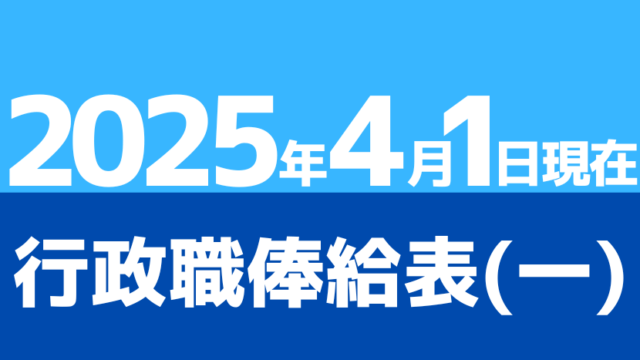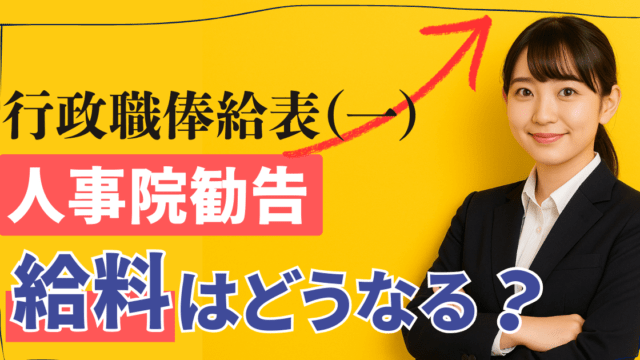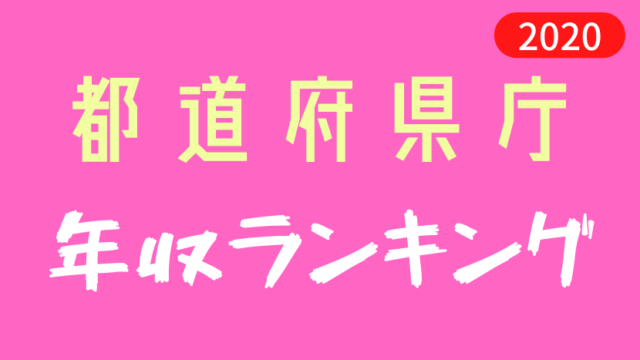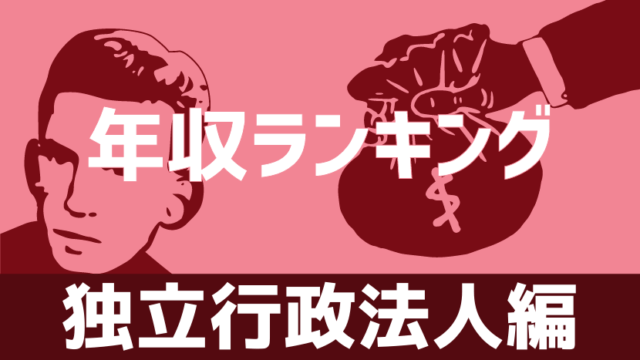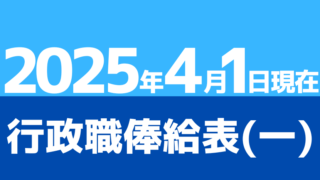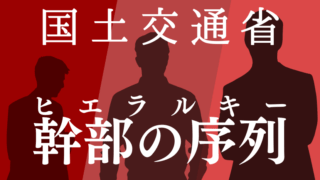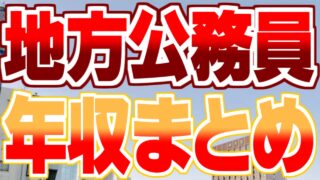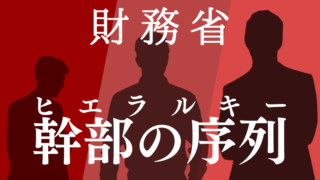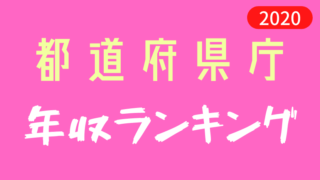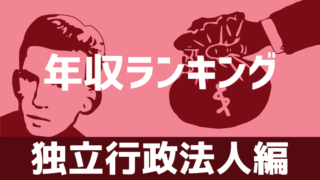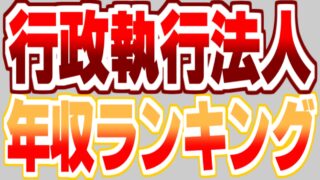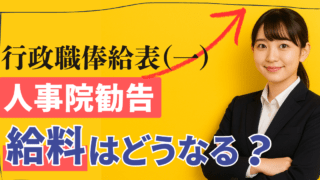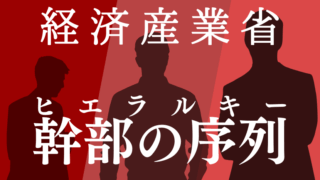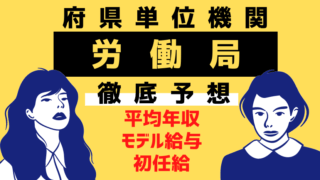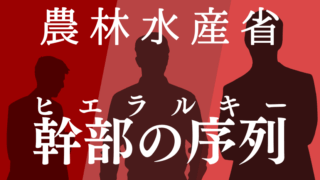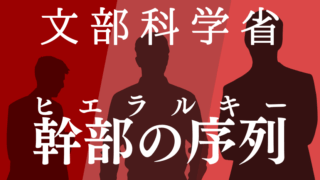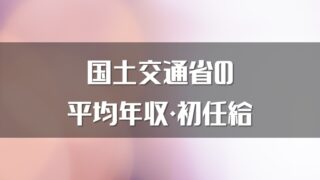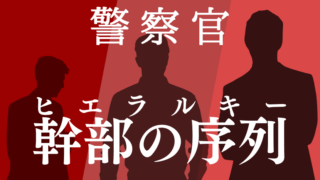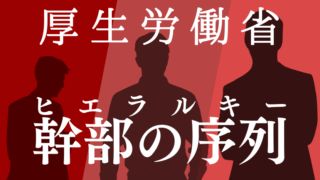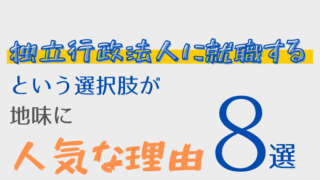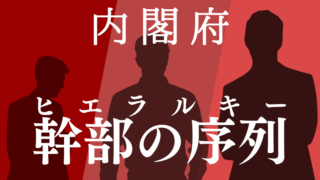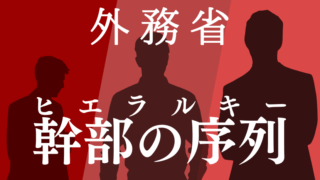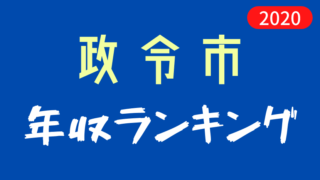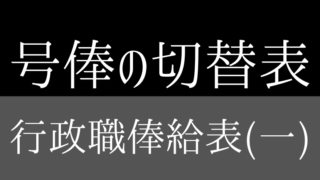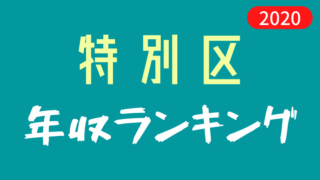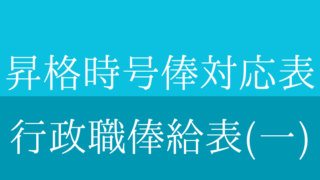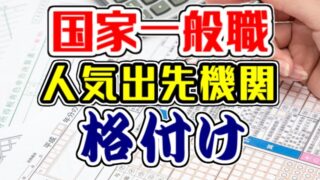目次
国家公務員の給与や働き方に関する人事院勧告は、毎年多くの関心を集めます。特に社会で活躍する20代、30代の皆さんにとっては、自身のキャリアや将来設計にも関わる重要な情報です。
令和6年の人事院勧告では、約30年ぶりとなる高水準の「ベースアップ」勧告が行われるなど、注目すべきポイントが多数あります。この記事では、令和6年人事院勧告の全体像とその影響を詳しく解説します。
この記事を読めば、人事院勧告の基本的な仕組みから、給与や手当、働き方の具体的な改正内容まで、必要な情報を過不足なく理解できるでしょう。今後のご自身のキャリアや生活を考える上で、ぜひ参考にしてください。
令和6年人事院勧告とは?基本的な考え方
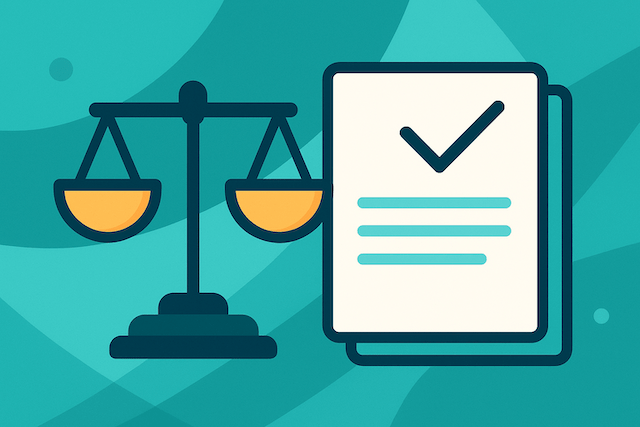
まず、人事院勧告がどのようなものなのか、その基本的な仕組みから見ていきましょう。
人事院勧告制度の役割
国家公務員は、憲法で保障されている労働基本権(争議権や団体協約締結権など)の一部が制約されています。これは、国家公務員が国家の屋台骨を支える唯一無二の仕事をしており、その地位の特殊性や職務の公共性を踏まえているためです。
この制約に対する「代償措置」として設けられているのが、人事院の給与勧告制度です。人事院は、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するため、国家公務員の給与について国会及び内閣に勧告を行う責務を負っています。勧告は、給与水準だけでなく、俸給制度や諸手当制度の見直しも含む包括的なものです。
人事院が適正な処遇を確保することは、職員の士気を高め、優秀な人材を確保することにつながり、能率的な行政運営を維持する上で基盤となります。
情勢適応の原則(民間準拠)とは
人事院勧告の最も基本的な考え方は、「民間準拠」です。これは、経済や雇用情勢などを反映して民間企業で決定される給与水準と、国家公務員の給与水準とのバランスをとるという原則です。
具体的には、毎年、人事院が民間企業の給与実態を調査し、国家公務員(主に一般行政事務を行う行政職俸給表(一)適用職員)と比較します。比較対象となる民間企業は、企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所です。比較は、職種、役職段階、勤務地域、学歴、年齢などの要素を揃えた「同種・同等比較」(ラスパイレス比較)という精緻な方法で行われます。
この比較によって生じた公務員と民間の給与の較差を解消することを基本に、給与改定の勧告が行われます。

令和6年勧告の構成
令和6年8月8日に行われた人事院勧告・報告は、主に以下の要素で構成されています。
- 公務員人事管理に関する報告
- 一般職の職員の給与に関する報告
- 給与勧告(関係法律の改正勧告)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出
なぜ給与改定が必要なのか?人事管理の現状と課題
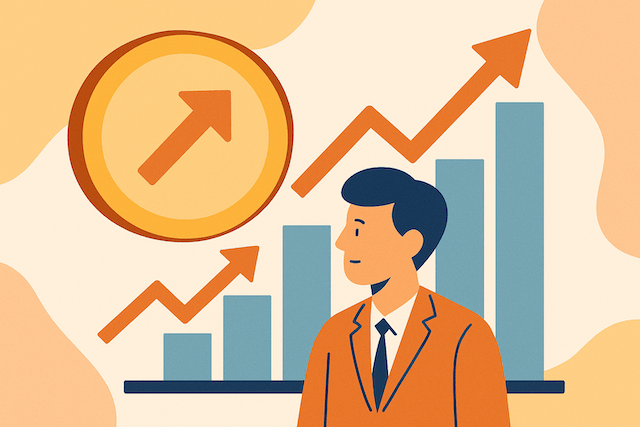
今回の勧告では、約30年ぶりの高水準となるベースアップが実現しました。なぜ、ここまで大きく給与水準を引き上げる必要があったのでしょうか?背景には、近年の民間給与の上昇だけでなく、国家公務員を取り巻く厳しい状況があります。
民間給与の上昇と官民比較
本年の民間給与調査の結果、公務員の給与水準が民間を下回っていることが確認されました。官民較差は月額11,183円、率にして2.76%となり、これは平成3年(額)、平成4年(率)以来の約30年ぶりの高水準です。この較差を埋めることが、民間準拠の原則に基づいた給与改定の基本的な理由です。
定期昇給分を合わせた月収の改善率は約4.4%に相当します。
国家公務員の人材確保の危機
国家公務員は、社会経済や国際情勢が激しく変化する中で、高度に複雑化・多様化する課題に直面しています。こうした状況で公務組織を維持し、パフォーマンスを向上させるためには、優秀な人材を確保し、育成することが不可欠です。
しかし、国家公務員の人材確保の現状は「危機的な状況にある」と報告されています。その要因として、以下の点が挙げられています。
- 長時間労働の常態化: 必ずしもやりがいと結びつかない長時間労働が問題視されています。
- 民間企業との比較での給与競争力の低下: 人材獲得で競合する民間企業と比較して、競争力があるとはいえない給与水準が課題とされています。特に、企業規模50人以上の企業との比較に偏りがあるのではないか、比較対象企業規模の引き上げが必要との指摘もあります。
- 若年層のキャリア意識の変化: 若年層は、将来的な転職も視野に入れ、仕事での成長を重視する傾向があります。長期雇用前提で、採用年次や職能を重視した従来型の人事管理が、若年層にとって魅力的に映らなくなっています。
- 離職者の増加: 特に若年層の離職者数が増加しており、公務組織の維持が困難になる懸念もあります。
このような状況を改善し、多様で有為な人材を確保するため、給与制度の見直しを含む抜本的な施策が必要とされています。優秀な人材の採用と定着(リテンション)が、人事管理の最優先課題と位置づけられています。
給与制度のアップデート:6つの視点

今回の給与制度の改定は、人材確保や組織パフォーマンス向上といった現代の人事管理上の課題に対応するため、多角的な観点から行われています。その基本的な考え方は、以下の6つの視点に集約されます。
- 若年層の採用等におけるより競争力のある給与水準の設定: 人材確保の困難性を踏まえ、初任給や若年層の給与水準を引き上げ、採用市場での競争力を高めます。
- 職務や職責をより重視した俸給体系等の整備: 民間企業の変化も踏まえ、人材確保や組織パフォーマンス向上の観点から、職務・職責に応じた俸給体系とします。管理職員の処遇改善も含まれます。
- 能力・実績をより適切に反映した昇給・ボーナスの決定: 勤務成績をより適切に給与に反映し、職員のモチベーションを高めます。
- 地域における民間給与水準の反映: 全国に官署がある公務において、地域の民間賃金を適切に反映し、人事配置の円滑化を図ります。地域手当の見直しが行われます。
- 採用や異動をめぐる様々なニーズへの適応: 人材確保の困難性やライフスタイルの多様化に対応し、採用や異動の円滑化に資する手当を見直します。通勤手当や単身赴任手当、再任用職員の手当が含まれます。
- その他環境の変化への対応: 家族の在り方やライフスタイルの多様化を踏まえ、生活補助的な手当を見直します。扶養手当の見直しが行われます。
これらの視点に基づき、具体的な給与制度のアップデートが提案されています。
具体的に何が変わる?俸給・諸手当の改正内容

ここからは、皆さんが最も気になるであろう、給与や諸手当に関する具体的な改正内容を見ていきましょう。
俸給
俸給表全体が引き上げ改定されます。特に、若年層と管理職層に重点が置かれています。
- 初任給・若年層の水準大幅引き上げ: 民間水準を大きく下回っている地域を考慮し、初任給を大幅に引き上げます。特に、行政職(大卒程度・高卒者)及び総合職(大卒程度)の初任給が重点的に引き上げられます。これは令和6年4月に先行実施されます。若手・中堅の優秀者が早期に昇格した場合のメリット拡大も図られます。
- 係長以上は職責重視、本府省課室長級を抜本見直し: 係長級から本府省課長補佐級では、各級の最低額が引き上げられます。本府省課室長級(課長、室長クラス)については、その重い職責に見合う処遇とするため、俸給体系を抜本的に見直し、昇格に伴う給与上昇が大きくなる仕組みとします.
- 能力・実績を反映した昇給: 成績優秀者が、より大きな給与上昇を確保できるよう、昇給制度も見直されます。
地域手当
地域ごとの民間賃金を適切に公務員給与に反映させるため、地域手当の仕組みが見直されます。
- 支給地域・級地区分の見直し: 現在の市町村単位から、都道府県単位を基本とします。ただし、都道府県庁所在地や人口20万人以上の中核的な市については、個別に級地区分を設定します。級地区分も現在の8段階から5段階に削減し、大括り化します。最新の民間賃金データを反映して指定されます。
- 異動保障の期間延長: 異動により地域手当の支給割合が下がる場合の影響を緩和する「異動保障」の期間が、現在の2年間から3年間に延長されます. 3年目の支給割合は、異動等前の60%となります。
- 激変緩和措置: 支給割合が引き下がる地域では、低下幅が4ポイントを超えないように抑制し、1年ごとに1ポイントずつ段階的に実施されます(令和7年度から令和9年度にかけて)。引上げについても段階的に実施されます。
- 今後の見直し期間短縮: 見直し期間に関する規定を廃止し、今後はより短期間で見直しを行います。
通勤手当・単身赴任手当
多様化するワークスタイルやライフスタイルに対応し、採用や異動の円滑化を図るため、通勤手当と単身赴任手当が見直されます。
- 通勤手当の支給限度額引き上げ等: 交通機関を利用する場合の支給限度額が月15万円に大幅に引き上げられます。この範囲内であれば、新幹線等の特別料金も全額支給されます。
- 支給要件の緩和・拡大: 採用に伴い新幹線通勤や単身赴任が必要となった職員にも手当が支給されるようになります。また、新幹線等に係る通勤手当について、通勤時間が片道30分以上短縮されることを求める要件などが廃止され、育児や介護等の事情で転居した職員も支給対象に含まれるよう要件が見直されます。
扶養手当
家族の在り方の多様化や、民間の配偶者手当見直しの動向を踏まえ、扶養手当が見直されます。
- 配偶者に係る手当の廃止: 民間企業での見直しや、配偶者の働き方に中立な制度構築に向けた政府全体の取組を踏まえ、配偶者に係る扶養手当は廃止されます。
- 子に係る手当の増額: 配偶者手当の廃止によって生じる原資を用いて、子に係る手当額が1人あたり10,000円から13,000円に引き上げられます。
これらの見直しは、受給者への影響を考慮し、2年間で段階的に実施されます.
ボーナス(特別給)
職員のモチベーション向上や民間との競争力強化のため、ボーナス(勤勉手当、期末手当)についても見直しが行われます.
- 勤勉手当の成績率上限引き上げ: 勤務成績に応じて支給される勤勉手当において、特に高い業績を挙げた職員への支給上限が、平均支給月数の2倍から3倍に引き上げられます。
- 特定任期付専門人材のボーナス拡充: 高度の専門知識を持つ特定任期付職員についても、勤務成績をより反映できるよう、期末手当と勤勉手当を支給する体系に再編されます。
定年前再任用職員等の手当拡大
定年の段階的引き上げに伴い、60歳以降も勤務する定年前再任用短時間勤務職員等(暫定再任用職員を含む)についても、人事運用の変化を踏まえ、処遇が見直されます。
- 異動円滑化に資する手当の新設: 異動を伴う配置にも対応できるよう、現在支給されていない手当のうち、地域手当(異動保障などの特例的なもの)、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)、寒冷地手当が新たに支給されます。
管理職員特別勤務手当
重い職責を担う管理職員の処遇改善として、管理職員特別勤務手当が見直されます。
- 平日深夜勤務の対象時間帯拡大: 災害対応などの臨時・緊急の必要による平日深夜勤務について、現在の午前0時〜午前5時から、午後10時〜午前5日までに対象時間帯が拡大されます。
- 支給対象職員の拡大: 俸給の特別調整額支給職員に加え、指定職職員や専門スタッフ職職員(2級以上)なども支給対象に含まれるようになります.
これらの給与・手当に関する改正措置の多くは、令和7年4月1日から実施されます(初任給・若年層の水準引き上げなど先行実施や段階実施されるものもあります).
柔軟な働き方・Well-being実現への取組
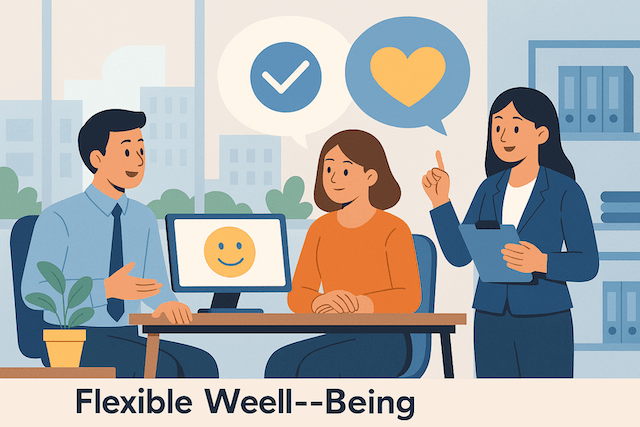
給与制度の見直しと並行して、職員一人一人がやりがいを持って能力を発揮できるよう、働き方に関する環境整備も進められます。これは、公務職場の魅力を向上させ、人材確保にもつながる重要な取組です.
時代に即した働き方の推進
多様なライフスタイルや価値観に対応した柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されます.
- 育児時間取得パターンの多様化: 現在1日2時間の範囲で取得できる育児時間に加えて、1年に10日相当時間数の範囲内で、1日あたりの上限時間数なく取得できるパターンが選択可能になります。また、非常勤職員の育児時間についても、対象となる子の範囲が小学校就学前の子に拡大されます.
- 超過勤務の免除対象拡大: 職員が請求した場合に超過勤務が免除される子の範囲が、小学校就学前の子に拡大されます.
- 子の看護休暇等の見直し: 対象となる子の範囲が小学校3年生までの子に拡大されるとともに、子の行事参加(入園・入学式、卒園式)や感染症に伴う学級閉鎖などにも利用できるよう、取得事由が拡大されます。非常勤職員の取得要件も緩和されます。
- 両立支援制度の利用に関する意向確認義務化: 妊娠・出産時や育児期の職員に対し、両立支援制度の周知や利用意向の確認・配慮が義務付けられます。介護についても同様の措置が講じられます.
これらの育児・介護に関する制度拡充は、民間労働法制の施行から遅れることなく実施されます.
- 勤務間のインターバル確保: 職員の健康確保やワークライフバランスのため、勤務間のインターバル(勤務終了から次の勤務開始までの休息時間)確保に向けた取組が進められます. 努力義務規定が導入され、目安として11時間のインターバル確保が推奨されています. 実態調査を通じて課題を把握し、改善を進めます.
- 兼業制度の見直し検討: 若手職員の自律的なキャリア形成やスキルアップ、専門人材の確保などを目的として、兼業制度の見直しが検討されます. 公正な執行確保といった課題も踏まえつつ、具体的な検討が進められます.
- 超過勤務の縮減: 長時間労働は、職員の健康や業務能率への影響に加え、公務の魅力低下につながる喫緊の課題とされています. 各府省のトップがリーダーシップを発揮し、業務の削減・合理化、職場風土・職員意識の改革、マネジメント強化を強力に進めることが求められています. 業務量に応じた要員確保や、国会対応業務の改善、人事・給与関係業務の改善なども進められます. 人事院による勤務時間調査・指導も強化されます.
- 人事管理のデジタル化: 業務効率化や職員の情報管理のため、人事管理分野のデジタル化が進められます. 各府省共通の勤務時間管理システムの整備などが計画されています.
Well-beingの土台づくり
職員が生き生きと働ける環境整備として、以下の取組も進められます.
- ゼロ・ハラスメントの実現: ハラスメントのない職場の実現に向けた取組が継続されます.
- 健康管理体制の充実: 心の健康だけでなく、身体の健康に関する相談窓口の拡充や、各府省の健康管理体制の強化が進められます. 長期病休者の職場復帰支援も強化されます.
今後の展望とまとめ

令和6年人事院勧告は、給与水準の引き上げだけでなく、人事管理上の様々な課題に対応するための包括的な見直しを含んでいます.
諮問会議中間報告では、優秀な人材の確保・定着、人的資本経営の発想を取り入れたパフォーマンス向上などが基本理念とされており、職務ベースの報酬設定、能力・実績主義の徹底、自律的なキャリア開発支援なども今後の重要な取組として挙げられています. 今後の人事行政諮問会議での議論も踏まえ、これらの施策の実装に向けた検討が進められます.
今回の勧告は、国家公務員が直面する複雑化・多様化する課題に対応し、国家の屋台骨を支えるという重要な役割を今後も果たしていくために、人材確保と組織の活性化を最優先課題として、給与・人事制度を現代の社会情勢に適合させるための重要な一歩と言えるでしょう.
20代、30代の皆さんにとって、今回の勧告で示された給与や手当の変更、そして柔軟な働き方やキャリア形成支援に向けた動きは、今後の公務員としてのキャリアを考える上で非常に参考になるはずです。これらの制度を正しく理解し、積極的に活用していくことが、ご自身の Well-beingと組織への貢献の両立につながるでしょう。
人事院は、今後も社会と公務の変化に応じた給与制度・人事管理制度の見直しを進めていくとしています. 最新情報を注視し、今後のキャリアに役立てていきましょう。