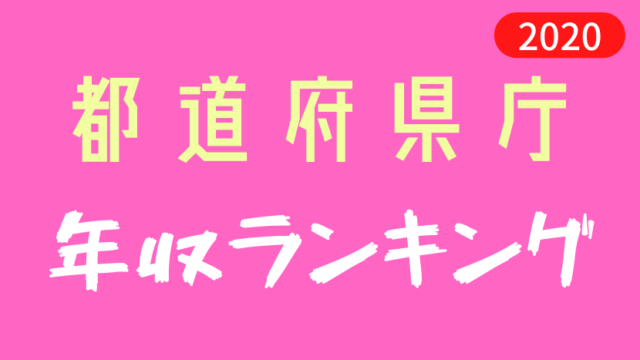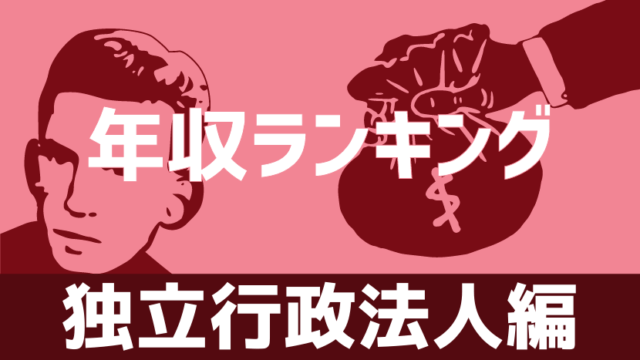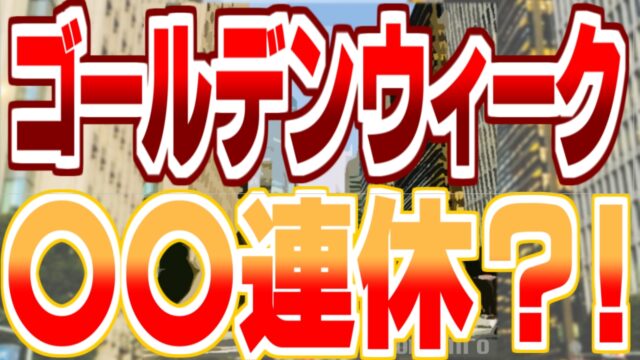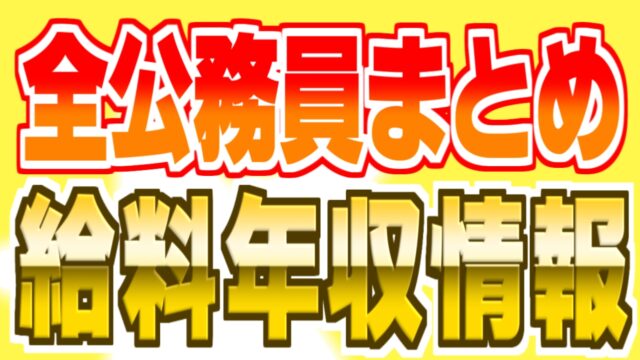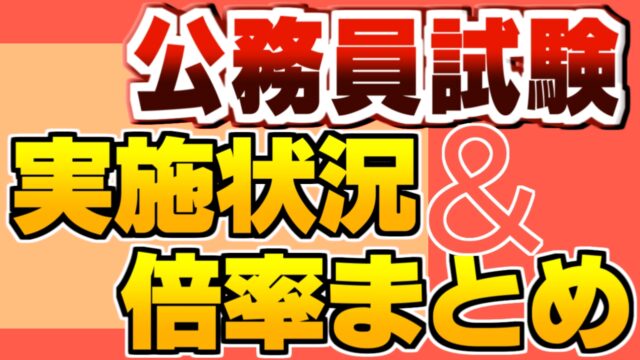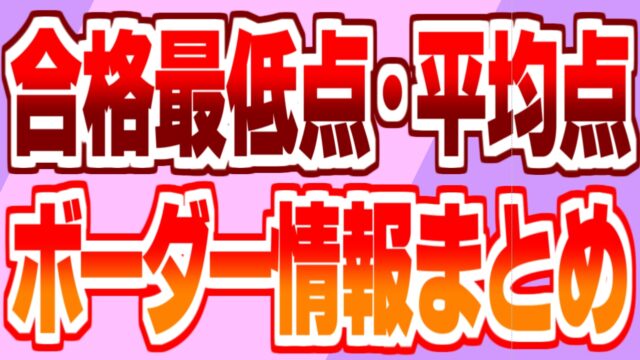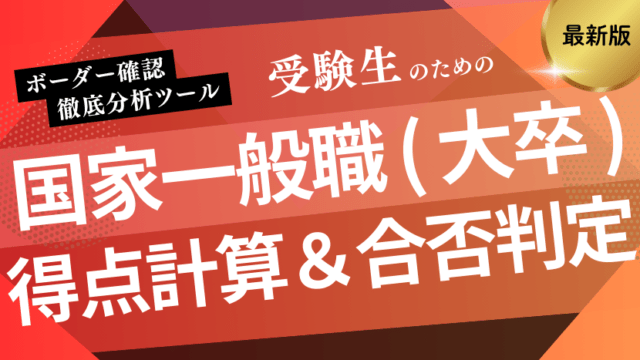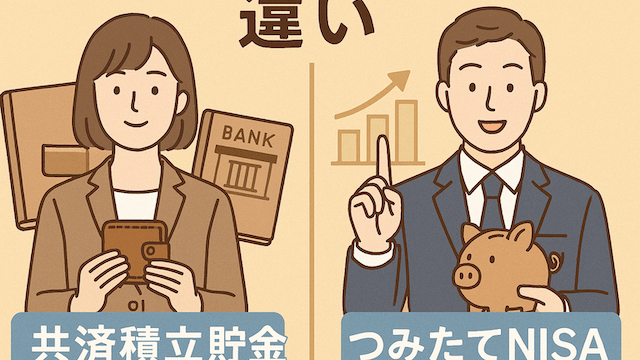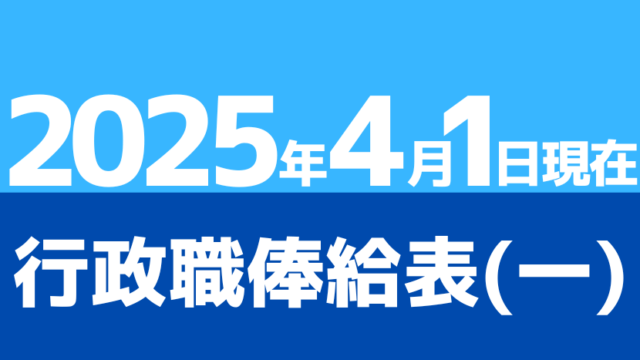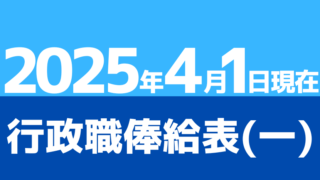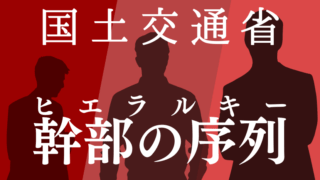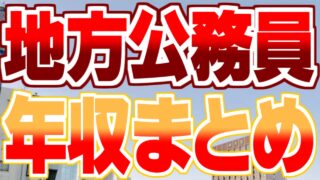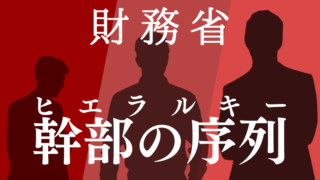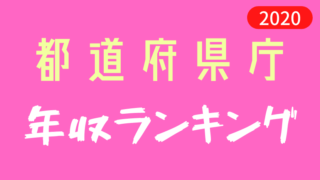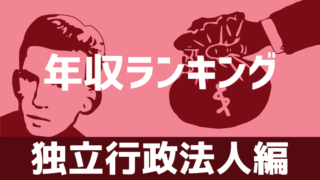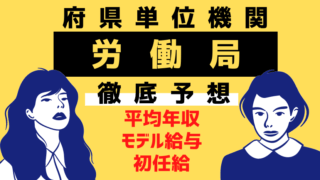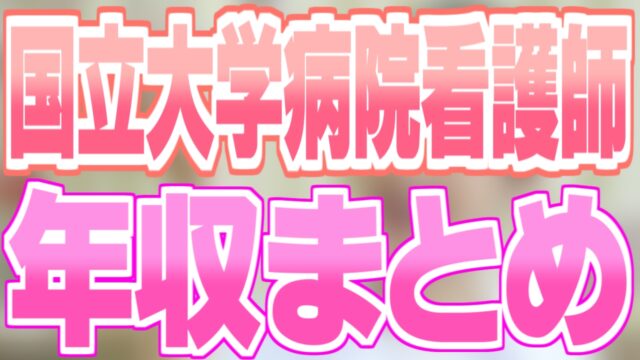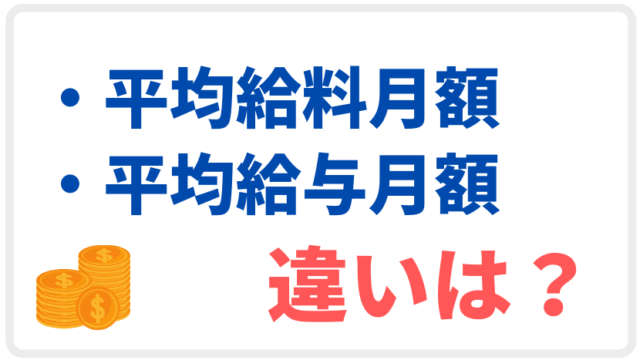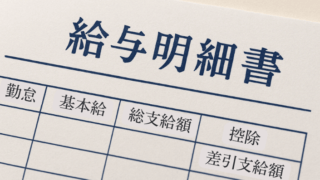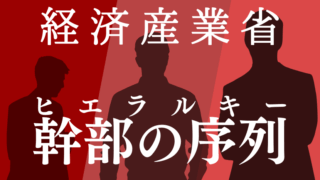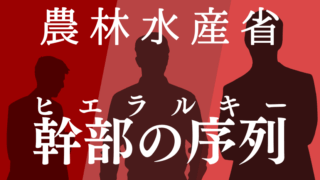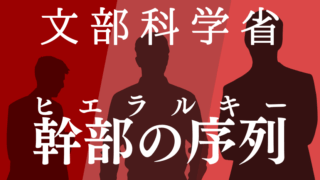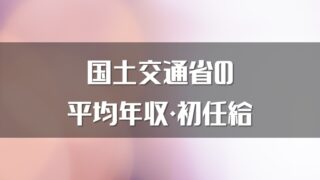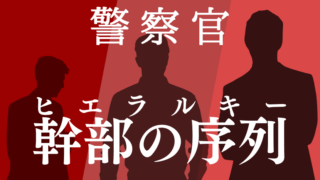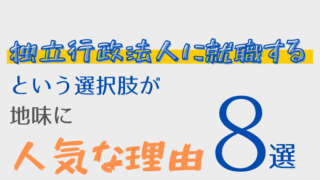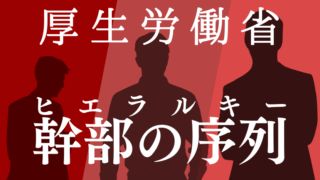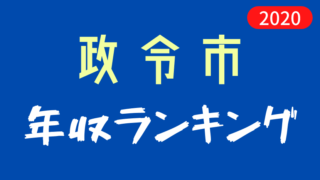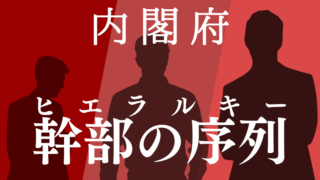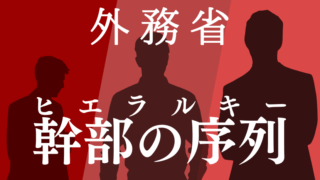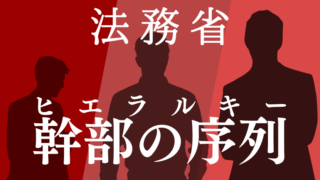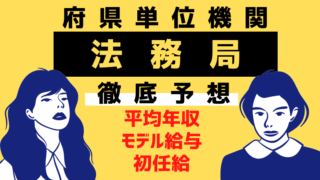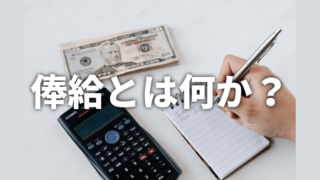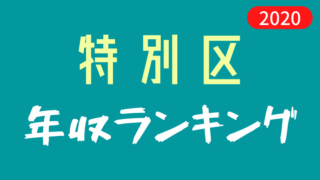目次
日本の公的年金制度は「2階建て」に例えられます。
すべての国民(20歳以上60歳未満)は1階部分である国民年金(基礎年金)に加入し、その上で会社員など給与をもらう人は2階部分として厚生年金に加入します。
公務員や私立学校の教職員も同様に国民年金には加入していますが、かつては厚生年金の代わりに共済年金(共済組合が運営する年金)に加入していました。
さらに公務員には独自の上乗せ部分として「職域加算」と呼ばれる3階部分の年金も存在していたのです 。まずはこのような年金制度の基本を押さえた上で、
共済組合の役割や共済長期・共済短期の違い、そして厚生年金との統合の流れについて、わかりやすく解説します。
共済組合の役割と共済制度の概要
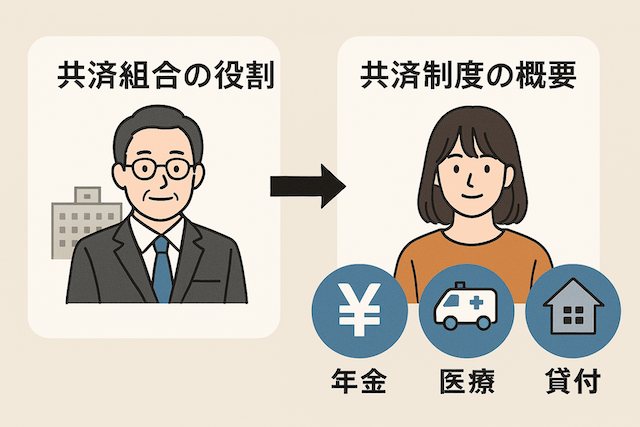
公務員(国家公務員・地方公務員)や私立学校職員などを対象に設けられているのが共済組合です。
共済組合とは、公務員や教職員が加入する保険組合で、民間企業の社会保険における健康保険組合や厚生年金基金に相当する役割を果たしてきました。
具体的には、共済組合は短期給付事業(医療保険)と長期給付事業(年金)の両方を運営し、組合員とその家族に対して医療費給付や年金給付を行っています。
加えて、組合員の福利厚生事業(保養所の運営や貸付制度など)も担っており、公務員の生活を幅広くサポートする仕組みとなっています。
なお共済組合への加入対象者は、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済など職域ごとに分かれています。
たとえば国家公務員であれば国家公務員共済に、地方公務員であれば地方公務員共済に、といった具合です。
共済組合の組合員となることで、公務員は在職中、自動的に共済組合を通じた年金・医療保障を受けることになります。
共済長期とは(共済年金の仕組み)
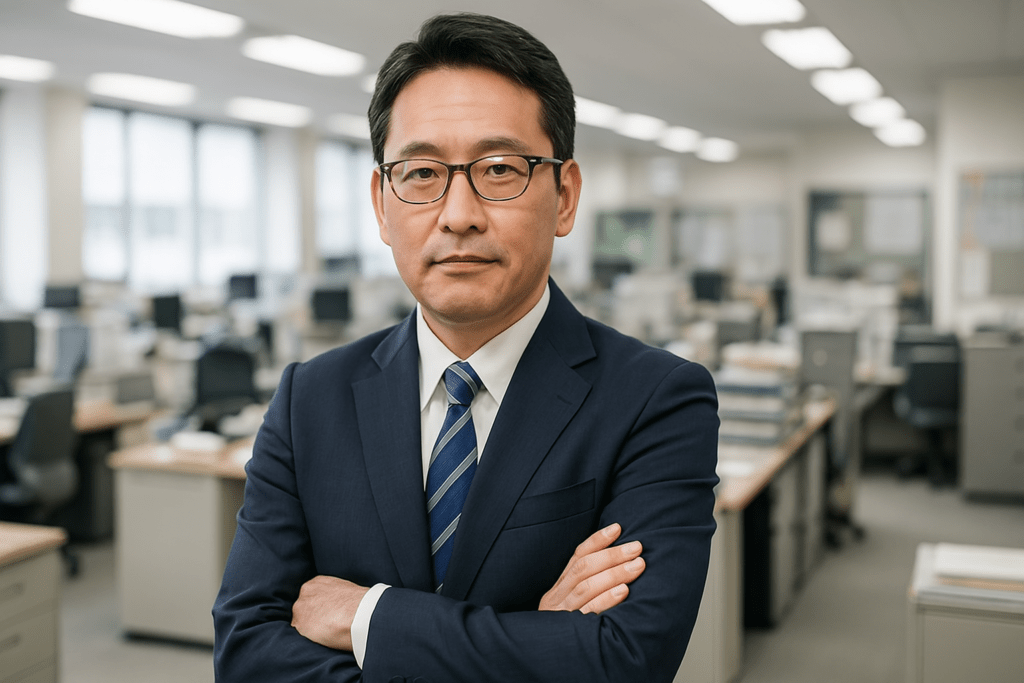 共済長期とは、共済組合が行う長期給付事業のことで、要するに公務員向けの年金制度を指します。
共済長期とは、共済組合が行う長期給付事業のことで、要するに公務員向けの年金制度を指します。
共済長期給付では、民間の厚生年金と同様に老齢年金(退職後に受け取る年金)、障害年金(公務中や私傷病で障害が残った場合の年金)、遺族年金(共済組合員が亡くなった場合に家族が受け取る年金)などが支給されます。
以前は厚生年金とは別立ての「共済年金」として運営されており、先述のとおり公務員等は国民年金+共済年金(+職域加算)という独自の年金枠組みになっていました。
共済年金(共済長期)の対象者は主に公務員と私立学校教職員で、民間企業の会社員が厚生年金に加入するのに対し、公務員等は各共済組合が運営する年金制度に加入していたのです 。
例えば、国家公務員であれば国家公務員共済年金、地方公務員なら地方公務員共済年金、私立学校の教師なら私学共済年金という具合に、自身の所属する共済組合を通じて長期給付(年金)の保障を受けていました。
共済年金は長らく公務員の退職後の生活を支える重要な柱として運用されてきましたが、この制度には厚生年金との給付水準の差や加入者数の違いなど、いくつか課題も指摘されていました。
共済短期とは(公務員の健康保険の仕組み)

共済短期とは、共済組合が行う短期給付事業のことで、公務員向けの医療保険制度を指します。
会社員が加入する健康保険(協会けんぽや健保組合)に相当し、公務員やその被扶養者(家族)は共済組合を通じて医療保障を受けます。
具体的な給付内容は民間の健康保険とほぼ同じで、病気やケガをしたときの療養の給付(医療費の7割を保険が負担し自己負担3割)、高額療養費や出産手当金、傷病手当金、埋葬料など各種給付が受けられます。
法律上、公務員向けの共済短期給付も民間の健康保険も公的医療保険として位置づけは同じであり、窓口で支払う医療費の自己負担割合が3割になるなど給付の内容に違いはありません。
ただし、保険料(掛金)の仕組みには若干の違いがあります。
共済組合の健康保険では、運営主体によって保険料率が定められており、その一部を国や自治体が負担しています。
そのため、加入者が負担する保険料は協会けんぽ等に比べて1割程度安い場合が多いと言われます。
また共済組合独自の附加給付(高額医療費の自己負担分をさらに減額してくれる制度)など、組合ごとに上乗せのサービスを提供しているケースもあります。
いずれにせよ、公務員であれば在職中は勤務先の共済組合の健康保険証を使い、退職後は一定の条件下で任意継続加入したり、他の公的医療保険(協会けんぽや国民健康保険など)に切り替えたりすることになります。
厚生年金との違いと制度統合の流れ
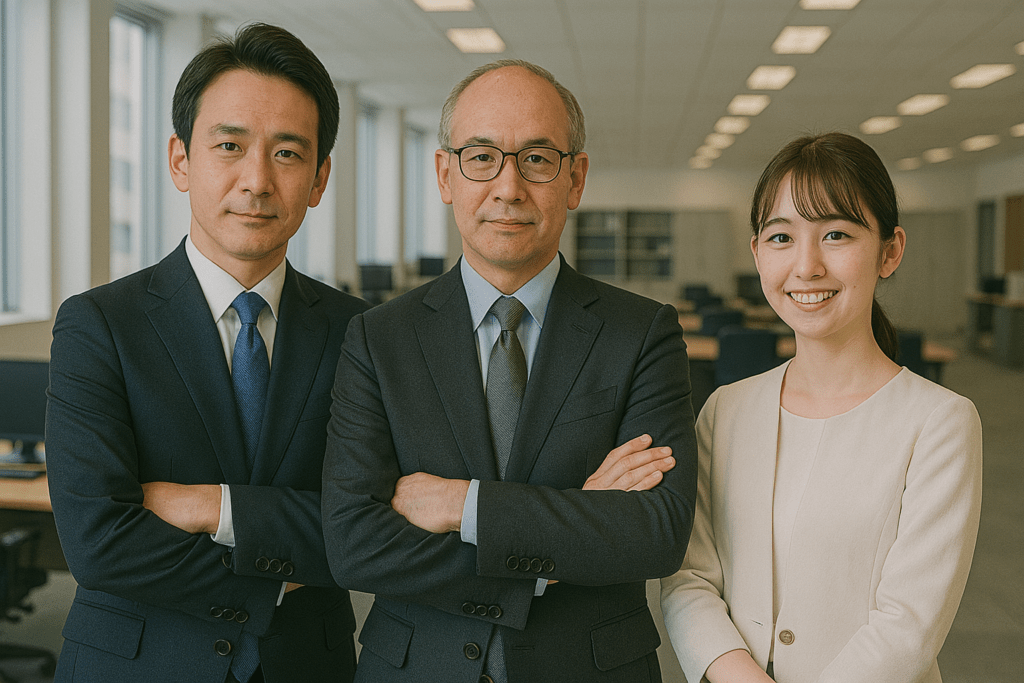
かつて別々に運用されていた厚生年金と共済年金ですが、制度の違いによる不公平をなくし、年金財政の安定を図るために統合が行われました。
公務員や私学教職員は長らく共済年金に加入していましたが、被用者年金(一階部分の国民年金に対する二階部分の年金)を一元化する目的で、2015年10月1日から共済年金は厚生年金に統一されています。
これにより、公務員も民間サラリーマンも同じ厚生年金に加入する仕組みとなり、年金制度上は職業による区別がなくなりました。
統合前は、共済年金の保険料率(掛金率)が厚生年金より低く設定され、公務員の方が同じ給料でも支払う保険料が少ない状況でした。
統合後は保険料率も厚生年金に揃えられ、共済側の保険料も同じ18.3%(労使折半)まで引き上げられました。
また、共済年金だけに存在した「職域加算」(3階部分の上乗せ年金)も廃止され、公的年金制度として公平な設計に改められています。
厚生年金と共済年金で異なっていた細かな給付条件についても見直しが行われ、多くの項目で制度の統一・調整がなされました。
制度統合の背景には、公務員も含めて被用者年金を一つにまとめることで加入者母数を増やし、将来の年金財政を安定させる狙いがありました。
実際、公務員・私学教職員の共済年金加入者(約442万人)を厚生年金側に取り込むことで財政規模が拡大し、リスク分散が進む効果が期待されています。
同時に「公務員だけ年金が優遇されている」という国民感情の改善(制度への信頼向上)も図られました。このようにして2015年以降、公務員の年金制度は厚生年金に一本化され現在に至っています。
現在の公務員の年金制度と共済組合の扱い

統合後の現在の公務員の年金制度は、基本的に民間の会社員と同じ厚生年金です。
新しく公務員になった人は厚生年金保険の被保険者となり、給料から厚生年金保険料が天引きされています。
年金給付も厚生年金として計算・支給されるため、「共済年金」という制度そのものは廃止されました。
したがって現役世代において、公務員だから特別に有利な年金がもらえるということはありません。かつて存在した職域加算も無くなり、年金については職業を問わず公平なルールになりました。
一方で、共済組合そのものが無くなったわけではありません。
先述のように共済組合は医療保険(短期給付)事業も担っているため、現在も公務員の健康保険は各共済組合が運営しています。
また、年金制度の一元化後も、窓口業務など一部では共済組合が関与しています。例えば年金の手続きでは、日本年金機構(年金事務所)だけでなく共済組合の窓口でも届出を受け付けるワンストップサービスが提供されています。
年金の給付に関しても、在職中に共済組合に加入していた期間がある人の場合、その期間分の年金は共済組合が決定・支給する仕組みが残っています(最終的な受取額は厚生年金として一括算出されます)。
要するに制度統合後も名称や運営主体が変わっただけで、共済組合員だった人の年金記録や給付はきちんと引き継がれているので安心です。
さらに、公務員の年金上乗せ部分だった職域加算の代替措置として、現在は年金払い退職給付という退職手当制度が設けられています。
これは公務員の退職金の一部を年金形式で受け取れるようにした仕組みで、厚生年金の枠外で運用されます。
民間企業でも企業年金があるように、公務員も共済年金廃止後はこのような別建ての制度で退職後の生活補助を行っています。
いずれにせよ年金本体(厚生年金部分)の給付額は公務員も民間も同水準となっています。
まとめ
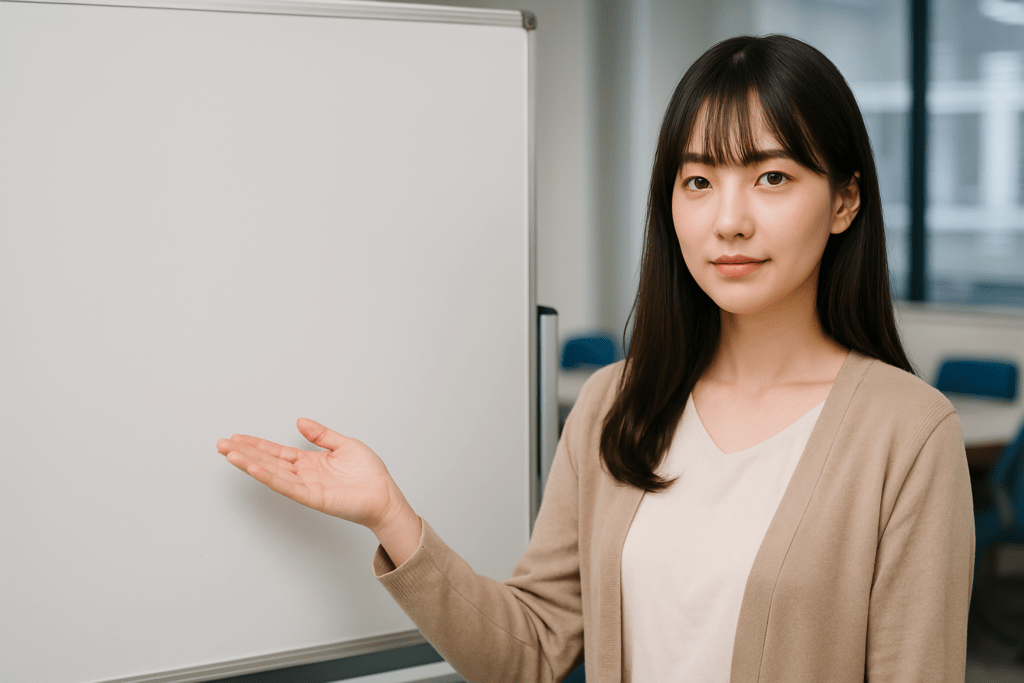
以上、共済長期とは何か、その仕組みと共済短期・厚生年金との違いについて説明しました。
ポイントを整理すると、公務員の年金(共済長期)は現在厚生年金に一本化されており、かつての共済年金と厚生年金の差異は解消されています。
一方、公務員の健康保険(共済短期)は引き続き共済組合が担っており、民間の健康保険と制度上は並列の関係です。
不明点があれば日本年金機構や各共済組合の公式サイトなどで最新情報を確認してみてください。
公的年金・公的医療保険の仕組みを正しく理解し、将来のライフプランに役立てていきましょう!