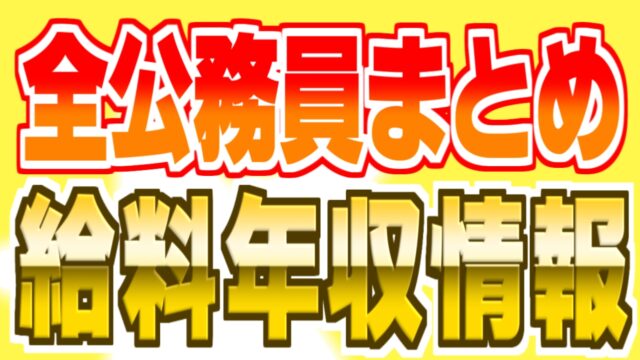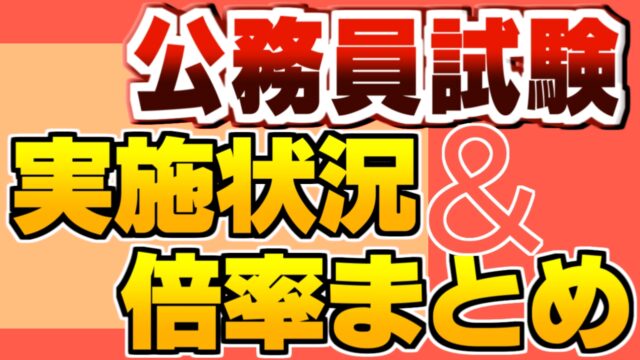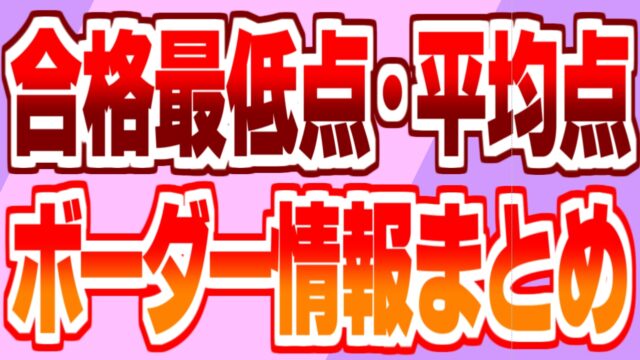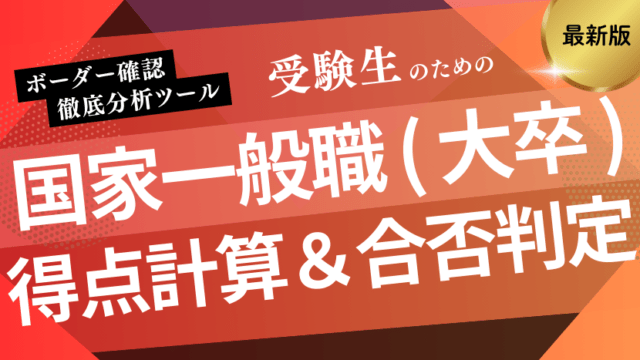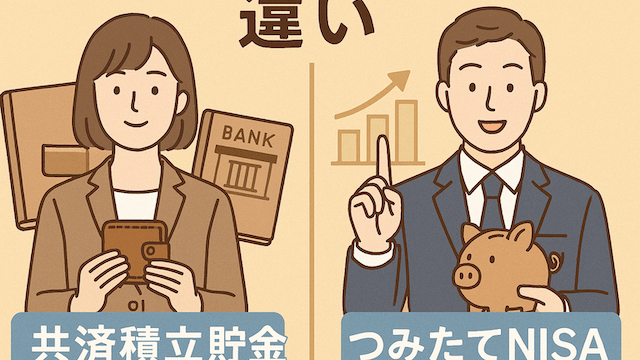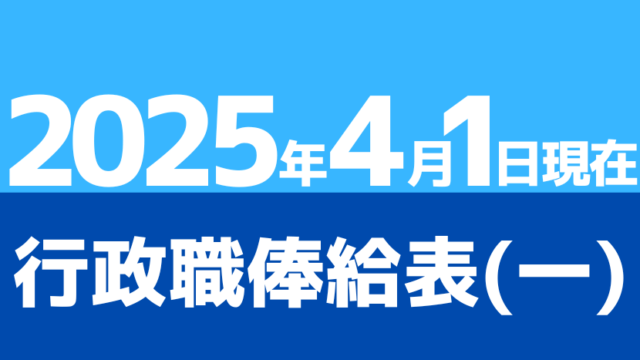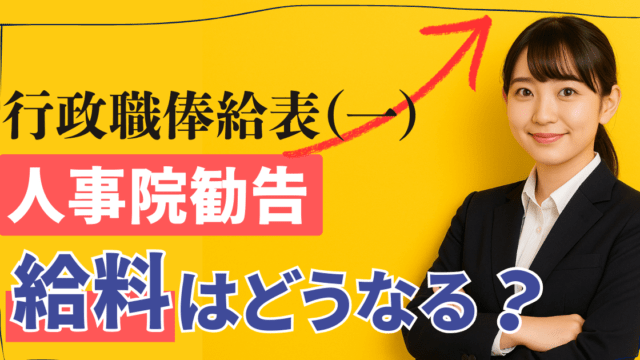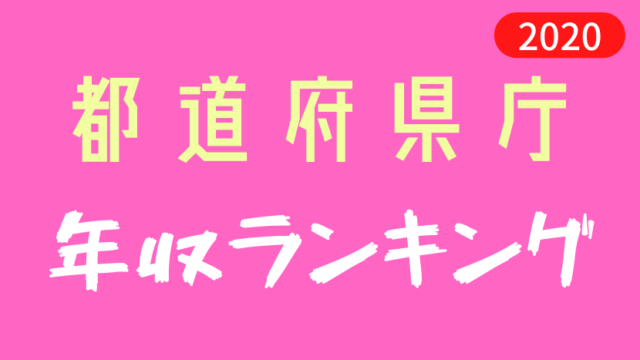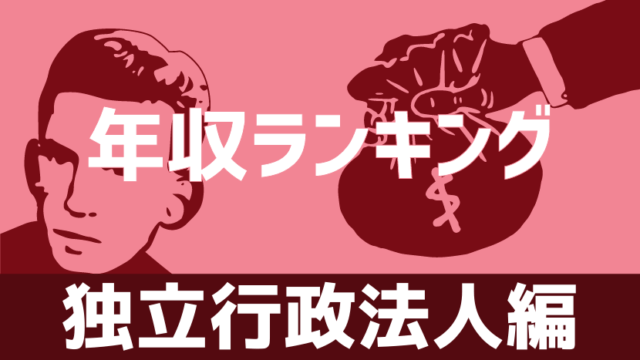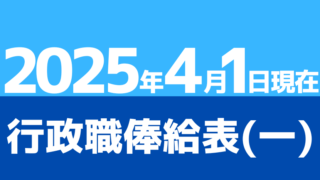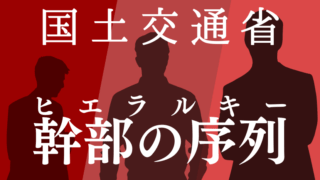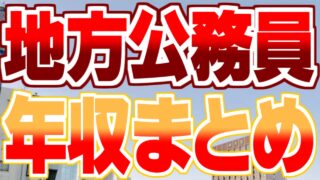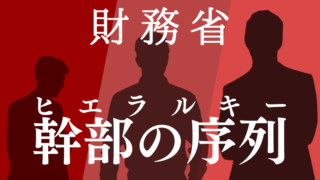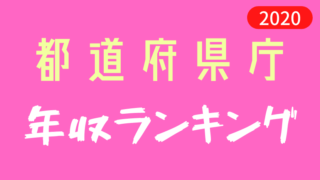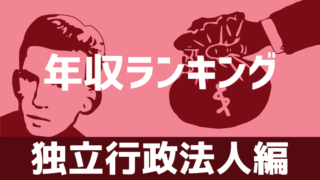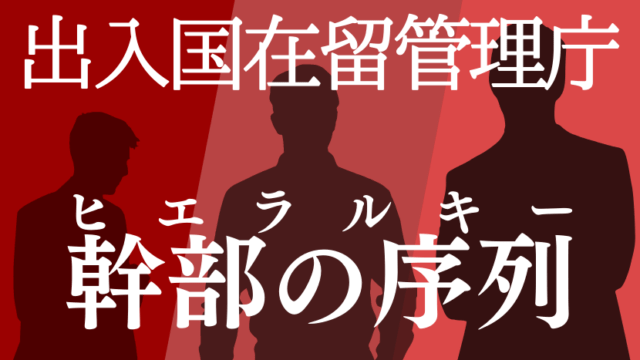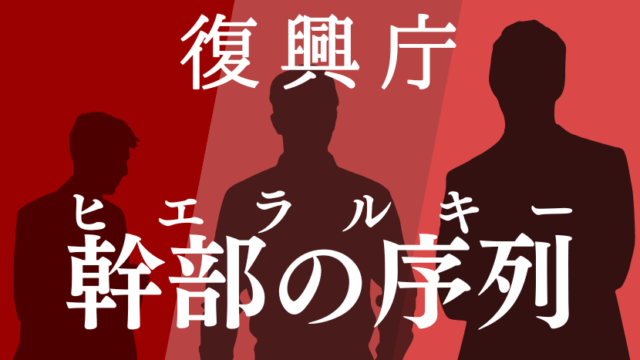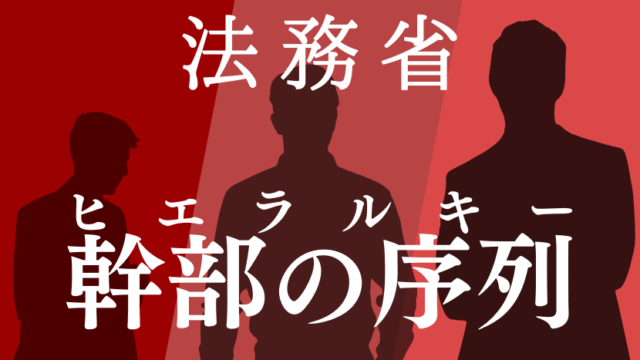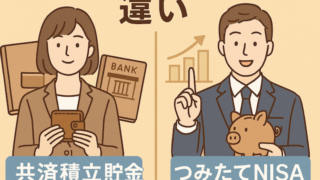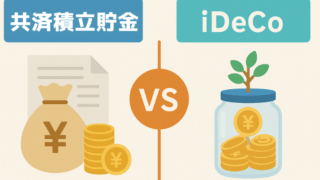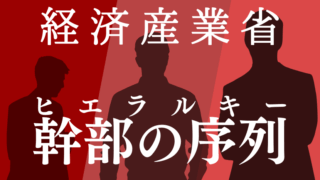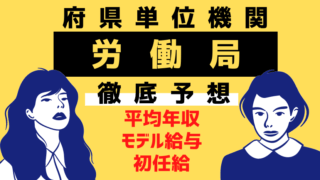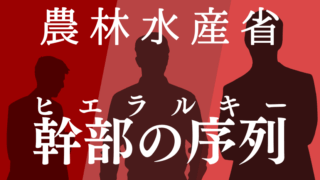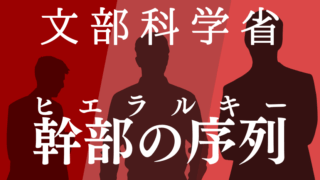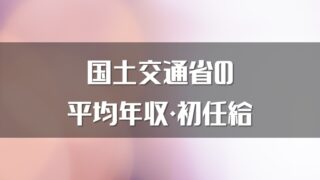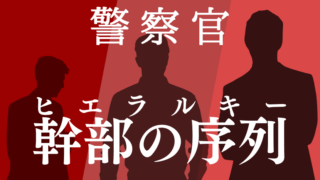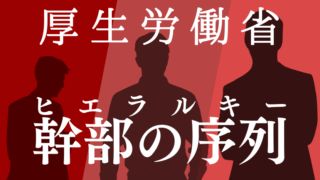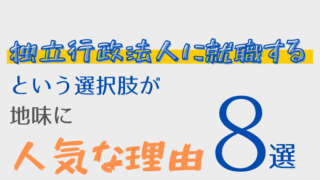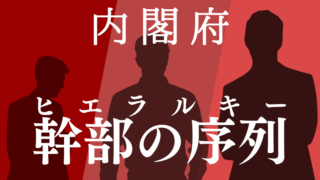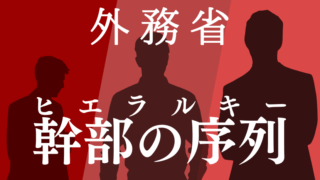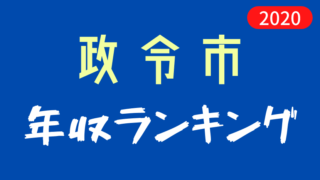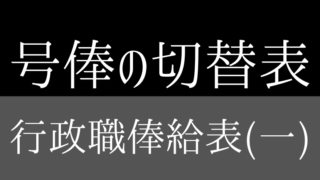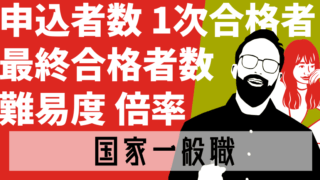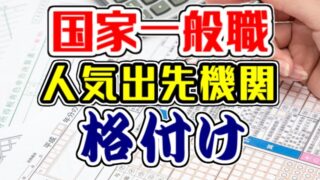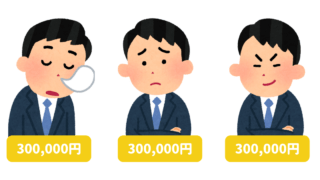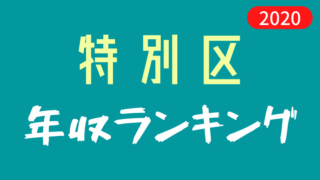目次
はじめに:なぜ「公務員=負け組」と言われるのか?
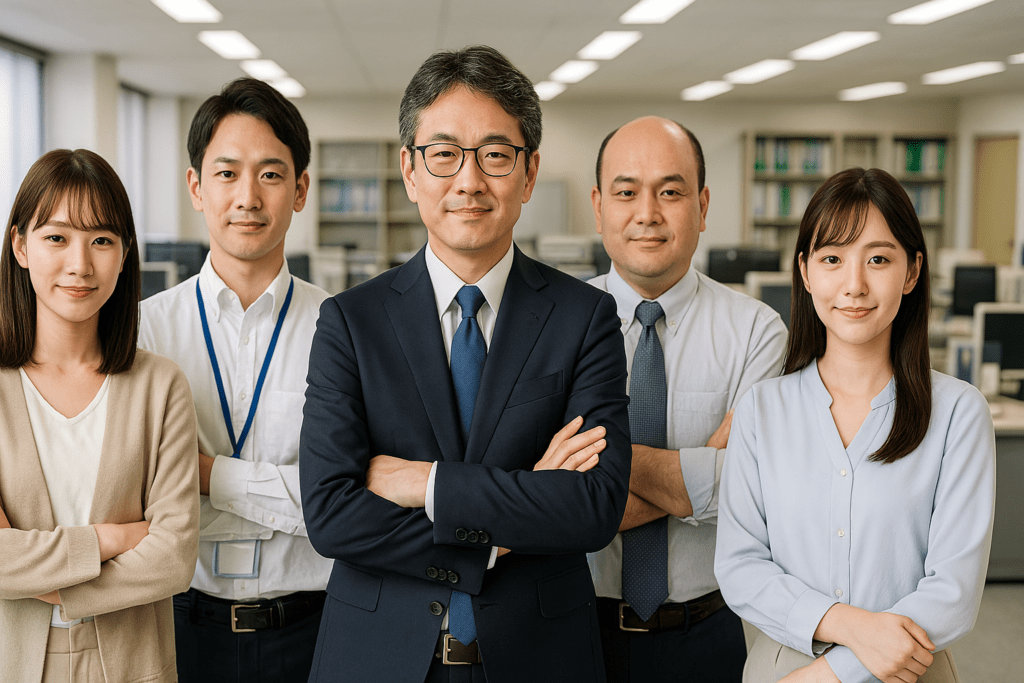
「公務員は負け組」「公務員なんてやめとけ」といったフレーズをSNSや掲示板で目にすることがあります。
一方で、「公務員は安定していて勝ち組」という意見も根強く、評価が分かれているのが現状です。
実際、「公務員 負け組 後悔」「公務員 将来性」といったキーワードで検索する人も多く、公務員のキャリアは本当に“負け組”なのか? という疑問を抱く人は少なくありません。
本記事では、この問いに正面から答えるために、公務員のメリット・デメリットや将来性をデータや声を交えて考察します。
公務員が「負け組」と言われる理由

公務員が「負け組」と揶揄される背景には、主に以下のような理由があります。
若手のうちは年収が低い
公務員の初任給は一般に民間企業より低く設定されています。
例えば地方公務員(大卒行政職)の平均初任給は約18.8万円で、民間大卒の初任給平均約23.7万円より5万円ほど安いというデータがあります。
このため、「民間で働いた方が稼げるのに、公務員を選ぶのは損だ」という見方が生まれがちです。
ただし公務員には安定した昇給や退職金など長期的メリットもあり、この点は後述します。
業務がルーティンワーク中心でやりがいがない
公務員の仕事は法律や前例に沿って手順通り進めるものが多く、部署によっては住民票の発行処理のように単調な事務作業の繰り返しになりがちです。
決まった業務を安定的にこなすのが得意な人には向いていますが、変化や成果を求める人には「退屈」「やりがいがない」と感じられやすいでしょう。
実際、「公務員は楽だけどやりがいはない」という声もネット上で散見されます。
成果が評価されづらく昇進が遅い
公務員の職場は年功序列色が強く、若手のうちはどれだけ頑張っても劇的な昇給や昇進は望みにくい傾向があります。
人事評価制度は存在するものの、民間のように明確な成果主義ではないため「努力が報われにくい」と感じる人もいます。
現に、公務員給与が年功序列で若手の昇給が緩やかなことに不満を持ち、「もっと早くキャリアアップ・高収入を目指したい」と民間企業へ転職する若手職員も増えています。
能力よりも勤続年数が重視される風土にフラストレーションを抱く人もいるでしょう。
以上のような理由から、向上心の強い人ほど公務員の環境を物足りなく感じ、「公務員は負け組だ」という評価を下しがちだと言えます。
しかし、これらは公務員の一側面に過ぎません。
次は逆に、公務員が「勝ち組」とされる理由にも目を向けてみましょう。
それでも「勝ち組」とされる理由
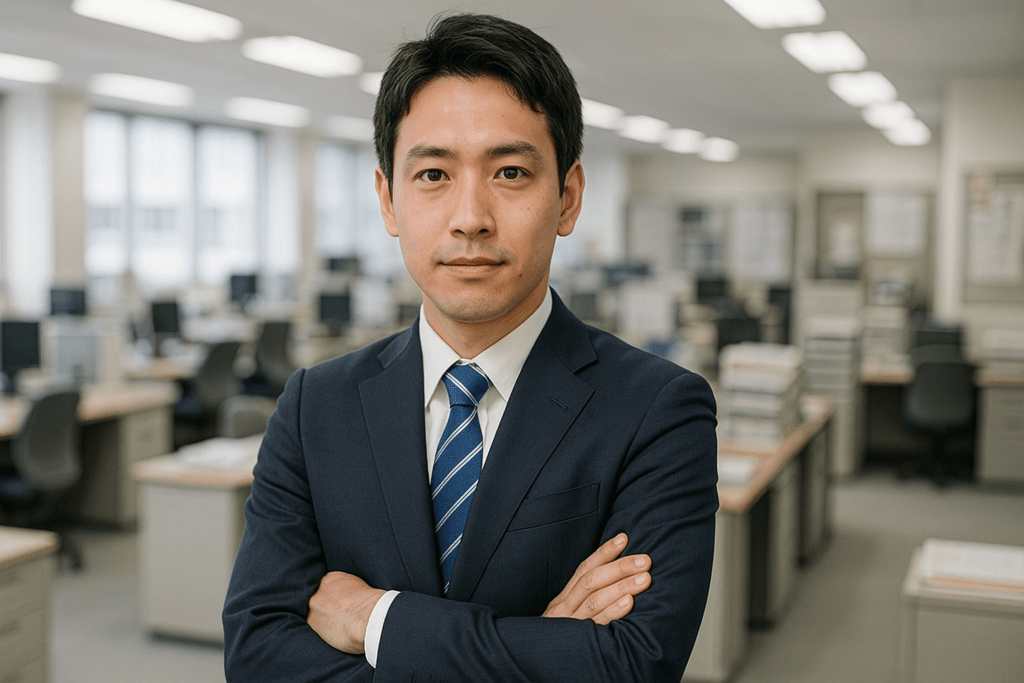
公務員には他の職業にはない 強みや魅力も多く、それゆえに「公務員=勝ち組」と考える人も少なくありません。その主な理由は以下の通りです。
雇用の安定性と継続性
公務員は景気に左右されにくく、解雇や倒産のリスクが極めて低い職業です。
近年、特に若い世代の地方公務員の離職が目立つようになったと言われるものの、地方公務員の離職率は民間企業に比べれば依然低いです。
公務員は腰を据えて長く働ける安定した職場であるこという意見は多く聞かれます。
勤勉に勤務を続ければ確実に昇給・昇進していく仕組みで、将来への不安が少ない点は大きな魅力です。
充実した福利厚生と退職後の保障
公務員は給与以外の手当や福利厚生が充実しており、安心して働ける環境が整っています。
住居手当・扶養手当など各種手当、充実した有給休暇制度、育児休業制度の整備、職員互助組織によるレジャー施設割引や共済保険など、企業にも劣らない福利厚生が用意されています。
公務員の共済年金は2015年に厚生年金と統合されましたが、依然として退職金制度や年金受給の安定性は魅力的です。
また、公務員という身分は社会的信用度が高く、住宅ローンが組みやすいといったメリットもあります。
ワークライフバランスの良さ
公務員は勤務時間や休暇制度が安定しており、プライベートとの両立が図りやすい仕事です。
原則として土日祝日が休みで、年間の休日は約125日程度確保されています。
年次有給休暇も年間20日付与され、消化率も7~8割と比較的高水準です。
部署によって繁忙期の残業はありますが、民間のいわゆる「ブラック企業」と比べれば休暇を取りやすく、育休・産休の取得実績も豊富です。
規則正しい勤務形態のため生活リズムが安定し、家族との時間や趣味に充てる時間を確保しやすい点で「公務員で良かった」と感じる人も多いようです。
以上のように、公務員は安定した収入と雇用、充実した制度によって生活基盤を築きやすい職業です。
そのため「仕事以外に大切なことがある」「仕事のために私生活を犠牲にしたくない」と考える人にとって、公務員の仕事は圧倒的に「勝ち」であり魅力的な選択肢だと言えます。
実際、公務員の低い離職率を支えているのはこうしたメリットの大きさに他なりません。
データで見る公務員の将来性

近年は少子高齢化やAIの進展により、「公務員の将来性が不安」「このままでは公務員も安泰ではない」との声も聞かれます。
しかし、一方で行政ニーズの変化に伴い、公務員という仕事は新たな役割を求められつつあります。データを交えながら、公務員の将来性を考えてみましょう。
まず、日本の人口減少は公務員にも影響を与え始めています。
総務省の統計によれば、地方公務員の総数は1994年の約328万人をピークに削減が進み、2021年には約280万人とピーク時より14.7%も少なくなっています。
特に地方の小規模自治体では人口流出と高齢化で職員採用数を抑制する動きがあり、将来的に公務員試験の受験者不足に陥る自治体も出てくる可能性が指摘されています。
実際、2021年には全国128市町村で新生児数が10人未満(うち2町村は0人)という状況で、20年後には地元から公務員志望者がいなくなる地域も懸念されています。
人口減による税収減から公務員数の見直しや給与抑制が議論される可能性は否定できません。
しかし一方で、少子高齢化により行政サービスの重要性自体はむしろ増しています。
高齢者へのきめ細かな支援や地域コミュニティの維持など、民間では担い手がいない分野で公務員の役割が拡大する余地があります。
過疎地域では住民数減少にもかかわらず一人ひとりへの対応ニーズが逆に増えるケースもあり、職員数を簡単には減らせないとの指摘もあります。
つまり、行政サービスの質を維持・向上するために、限られた人員で効率よく業務を行う工夫がこれまで以上に求められるでしょう。
その鍵の一つが「デジタル人材」の活用です。
国や自治体では現在、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進して行政の効率化とサービス向上を目指しています。
例えば一部の自治体では、新卒採用・中途採用で「デジタル職」という専門区分を新設し、基本情報技術者試験などIT資格の合格を要件にデジタル業務を担当できる人材を採用し始めています。ま
た、民間出身者を中途採用する自治体も増えており、ある調査では自治体の民間人材向け求人が2015年比で7倍以上に増加したというデータもあります。
国レベルでもデジタル庁の創設や各省庁での専門職採用など、公務員像は変わりつつあります。
これからはITスキルや改革マインドを持った公務員がますます求められる時代と言えるでしょう。
さらにAIの台頭についても悲観し過ぎる必要はありません。
確かにRPA(業務自動化)やAIチャットボットの導入で窓口対応や書類チェックなど定型業務は効率化されつつありますが、人間でなければ対応できない業務も多く残ります。
政策立案や住民対応の現場では高度な判断力や共感力が求められ、これらはAIに簡単に代替できない部分です。
むしろAIを活用してルーティン業務の負担を減らし、公務員はより創造的な仕事や住民サービスの質向上に注力できるチャンスとも言えるでしょう。
このように、公務員を取り巻く環境は大きく変化していますが、「将来性がない」と断じるのは早計です。
行政ニーズは形を変えて続いていくため、公務員にも時代に即したスキルや柔軟性が求められ、活躍の場がアップデートされていくと考えられます。
結局、公務員は負け組なのか?

結論から言えば、公務員が「勝ち組」か「負け組」かは一概には決められません。
冒頭の問いに対する答えはシンプルで、「公務員という仕事が自分に合っているか、そして自分が何を重視するかによって評価は変わる」ということです。
公務員という職業自体が負け組であるという見方は誤りであり、安定志向の人にとっては間違いなく魅力的なキャリアです。
実際、仕事以外に大切なことがある人や、無理せず安定収入を得たい人にとって、公務員ほど適した環境はありません。
こうした人々にとって公務員はむしろ「勝ち組」の選択肢でしょう。
一方で、仕事に対して強い向上心があり、成果をどんどん出して早く昇進したい人や、高収入を目指してリスクを取ってでもチャレンジしたい人にとっては、公務員の仕組みは物足りなく感じられるかもしれません。
そういう人が公務員を選ぶと「自分には合わなかった」と後悔する可能性が高く、公務員という働き方自体を「負け組だ」と感じてしまうでしょう。
要するに、公務員で幸せになれるかどうかはその人の価値観次第なのです。
安定した収入・雇用、社会貢献や市民の生活を支えるやりがいを重視するなら、公務員は非常にやりがいのある天職になりえます。
逆に、年収アップのスピードや仕事上の裁量の大きさ、競争的なビジネス環境を重視するなら、民間企業の方が向いているでしょう。
おわりに:進路選択の判断軸とは

最後に、進路選択における判断軸について考えてみましょう。
大切なのは世間のレッテル(「勝ち組」「負け組」)に惑わされず、自分が将来どんな人生を送りたいかを軸に考えることです。
仕事に求めるものは人それぞれです。経済的安定やワークライフバランス、社会的使命感を重視するなら公務員という選択は有力ですし、自己成長や高収入、イノベーティブな仕事を優先するなら他の道を選ぶべきかもしれません。
公務員には確かに「安定」という大きな強みがありますが、「安定=退屈」になるか「安定=安心」になるかはあなた次第です。
自分に向いている環境かどうか、譲れない条件は何かを見極めることが肝心です。
例えば、安定した公務員の道を選ぶにしても、デジタルなど新しいスキルを磨いておけば将来性は高まりますし、逆に民間を選ぶにしても公務員で培った経験(法律知識や調整力など)は無駄になりません。
進路選択に正解・不正解はありません。公務員だから勝ち組、民間だから負け組、といった極端な判断ではなく、自分の人生の軸に照らして後悔のない道を選ぶことが何より大切です。
そのためにも、公務員の現実的なメリット・デメリットや将来の展望を正しく理解し、自分に合ったキャリアかどうか冷静に見極めてください。本記事の内容が、その判断の一助になれば幸いです。